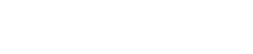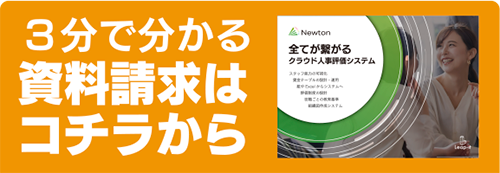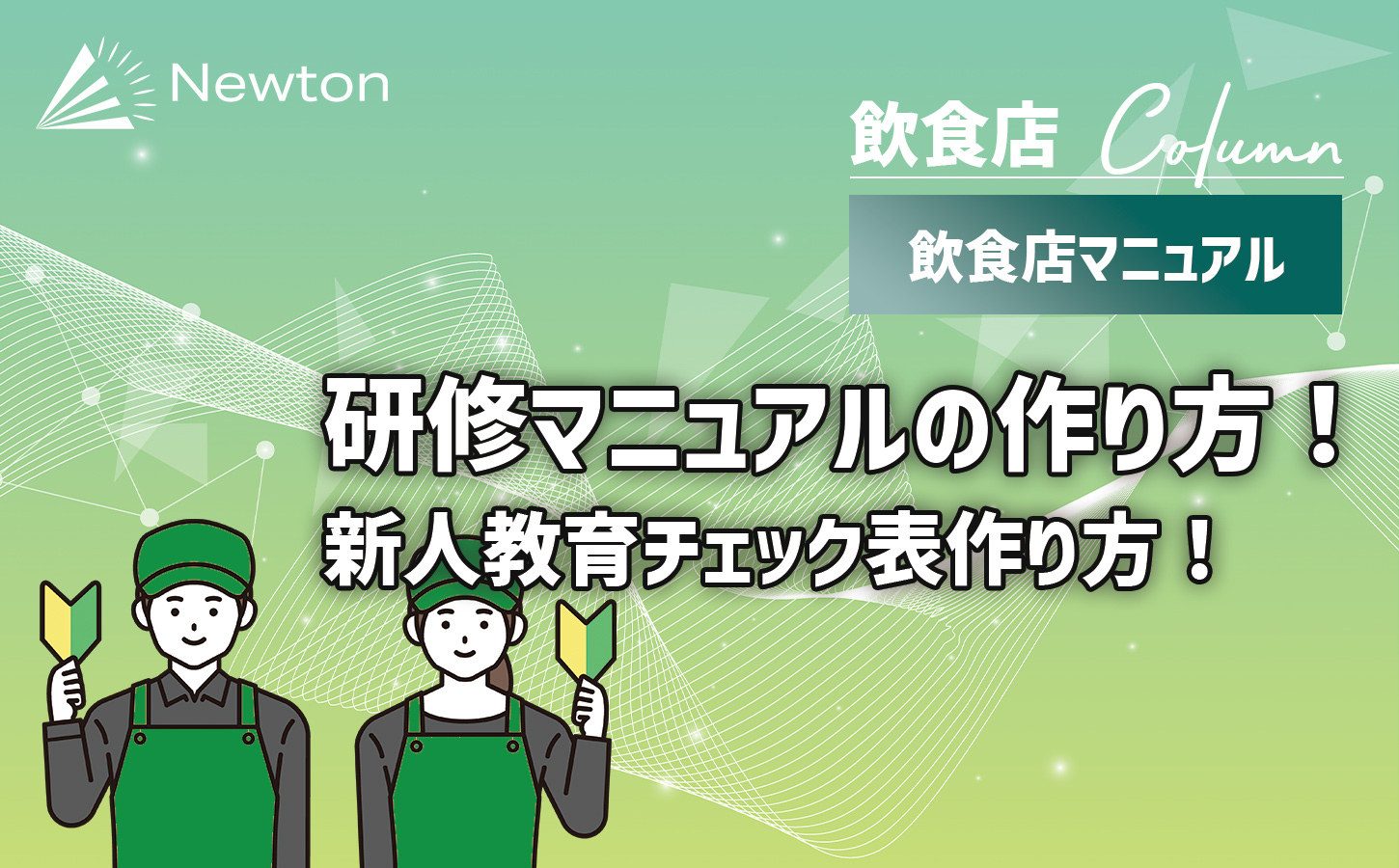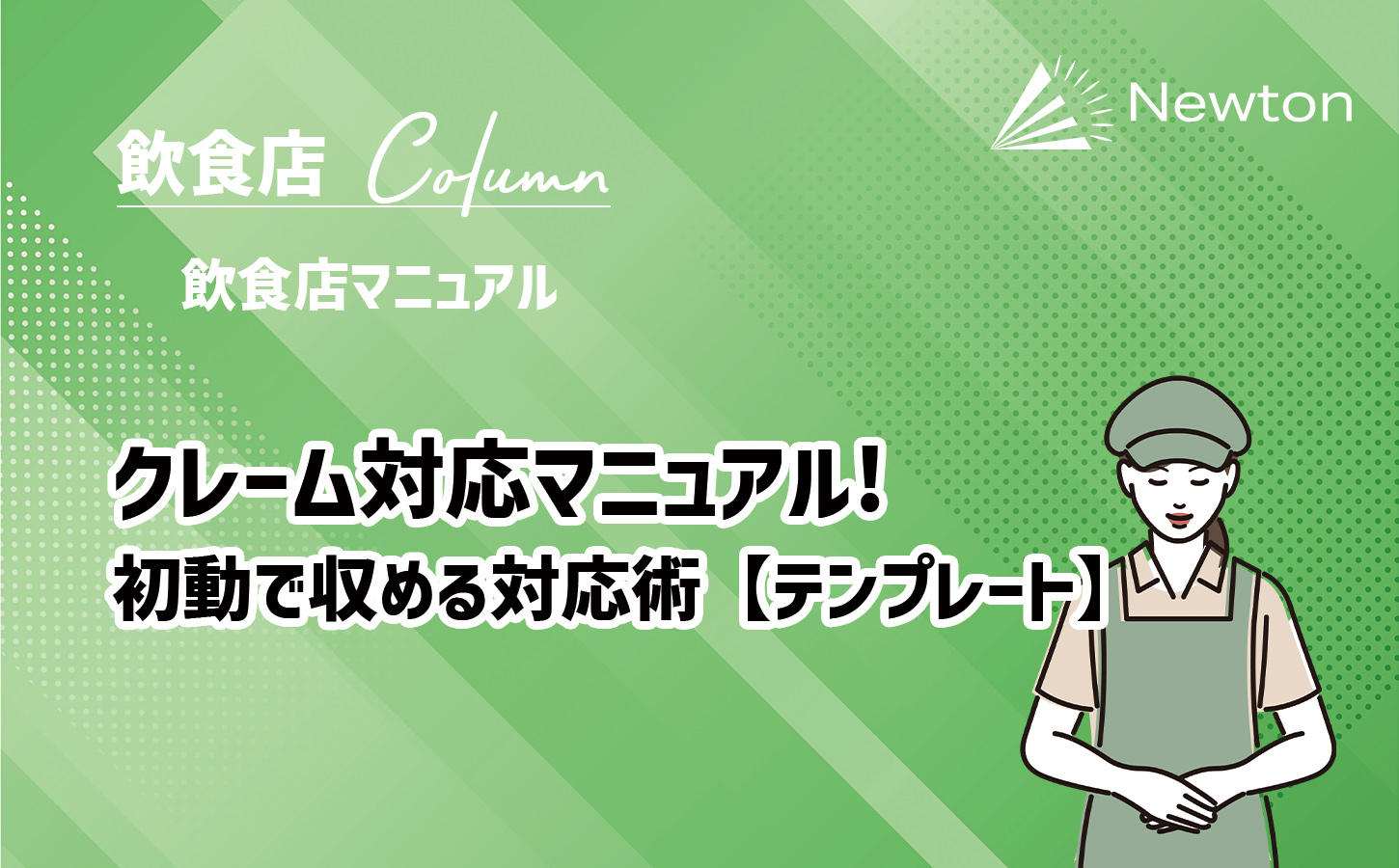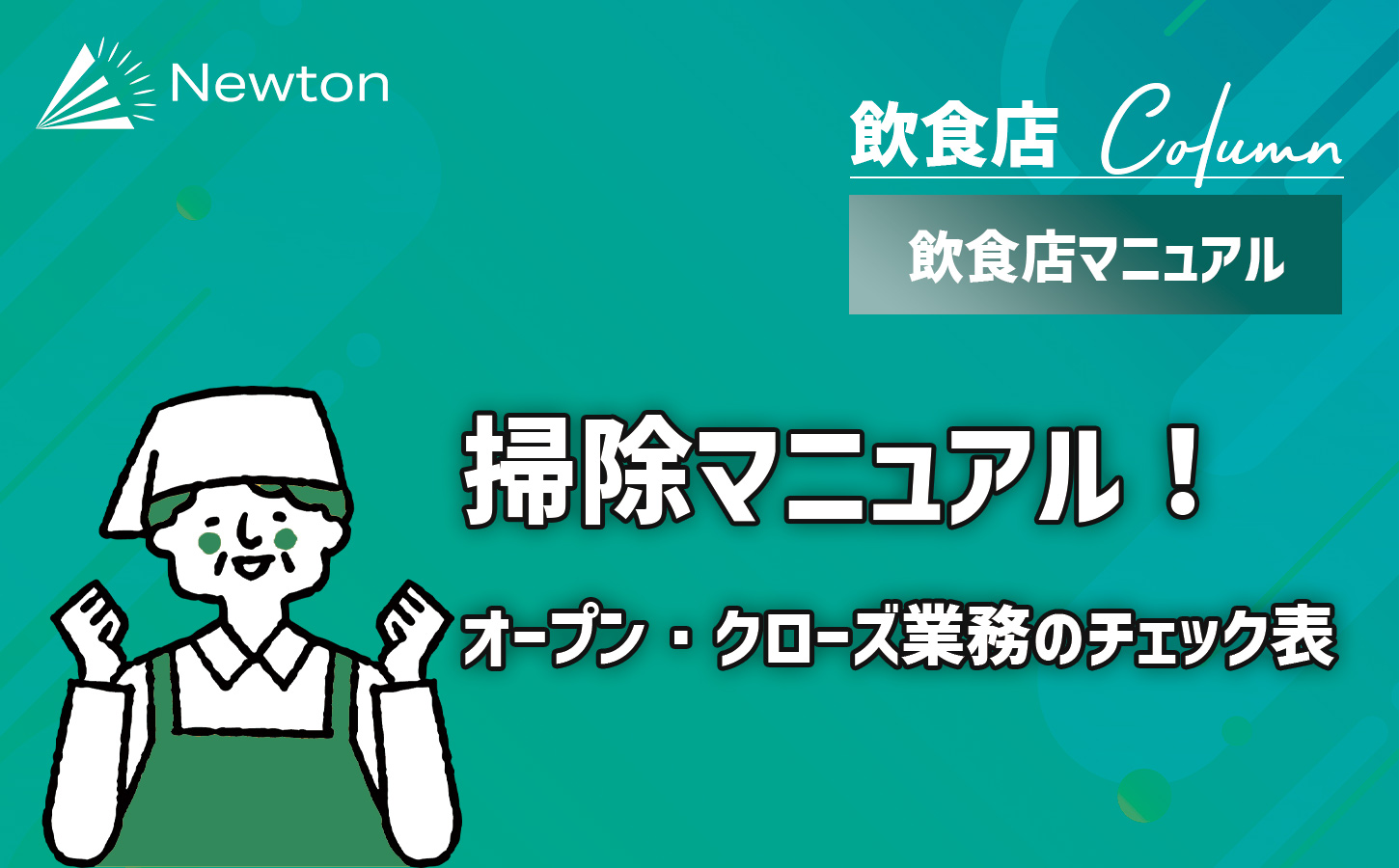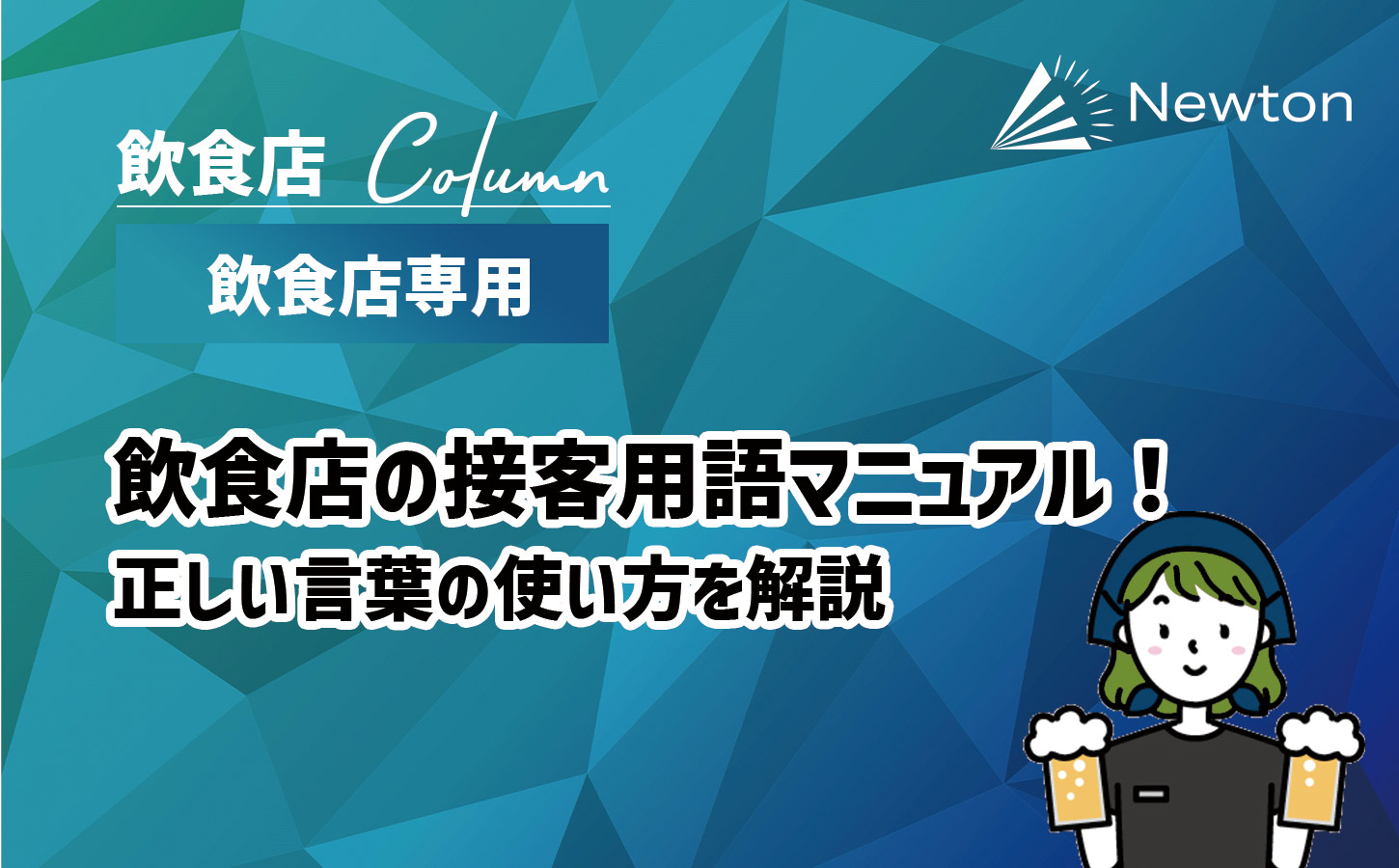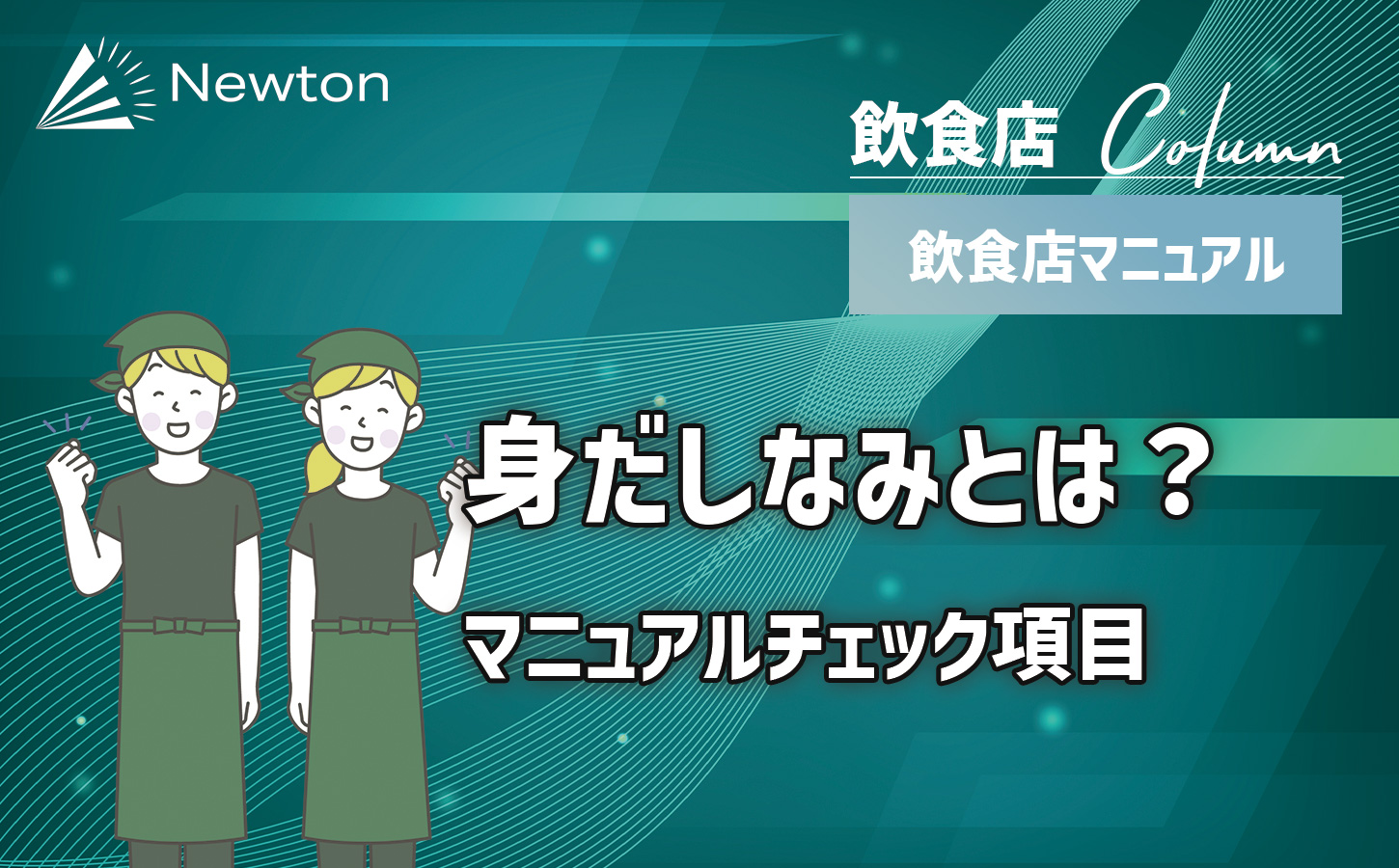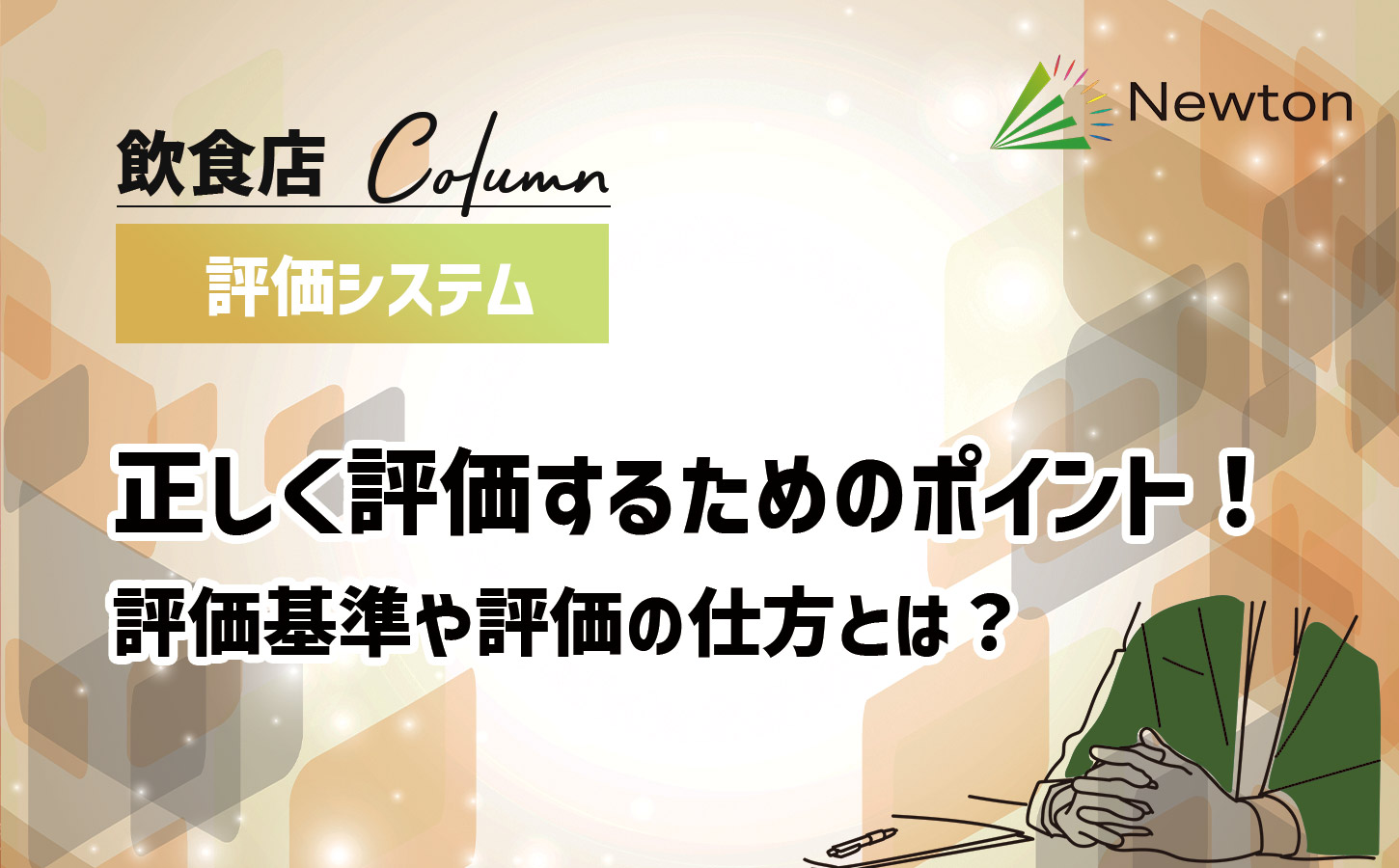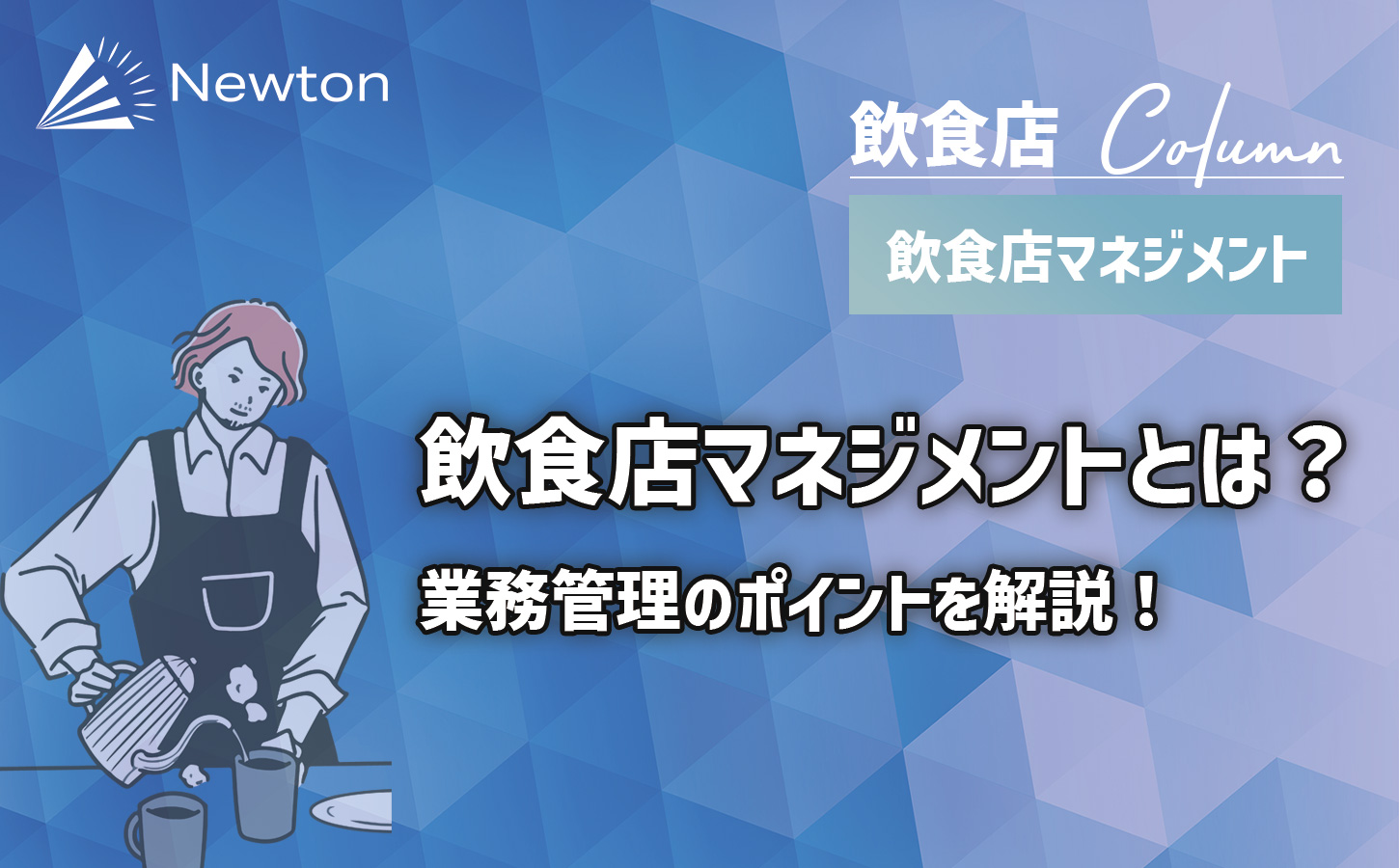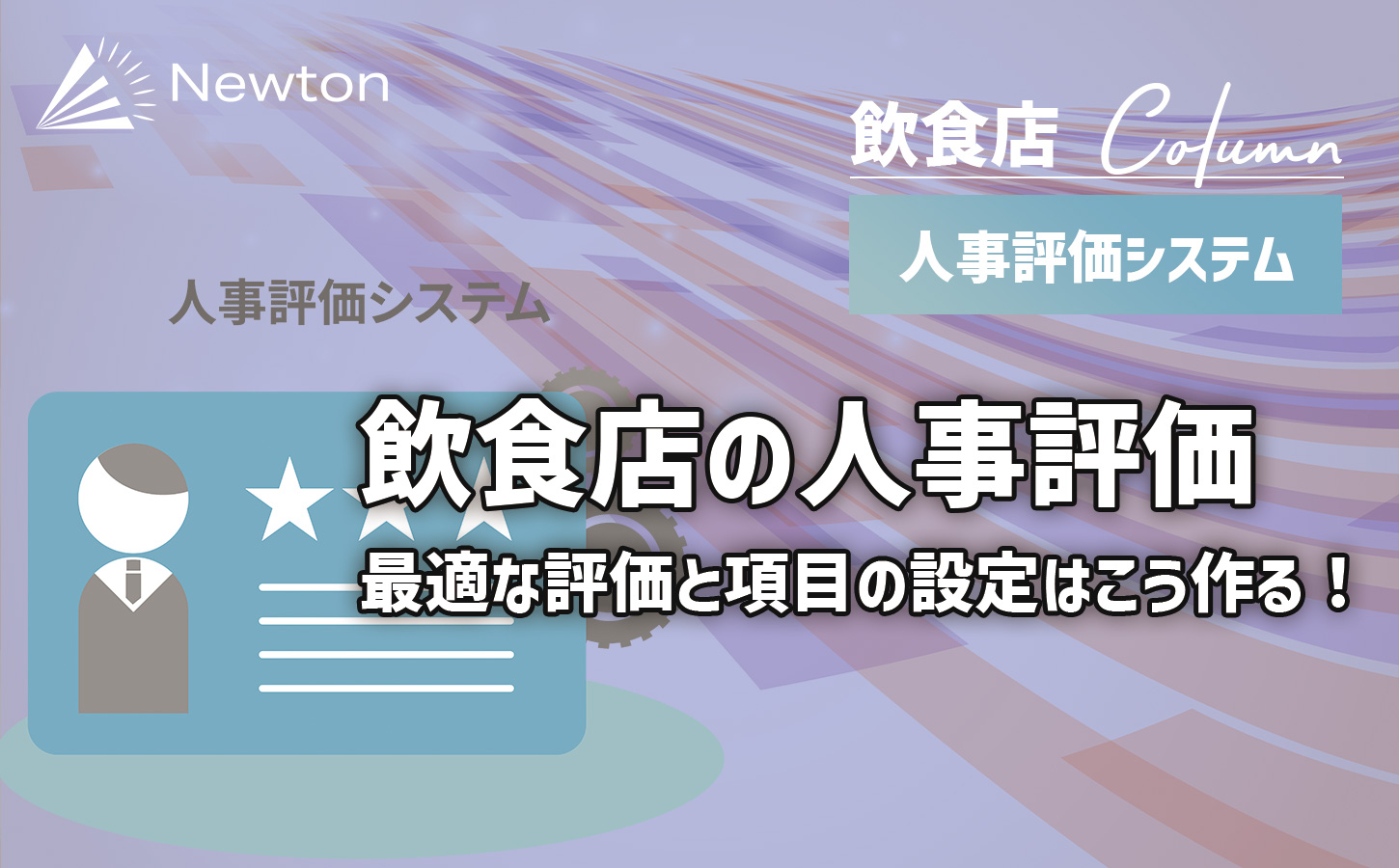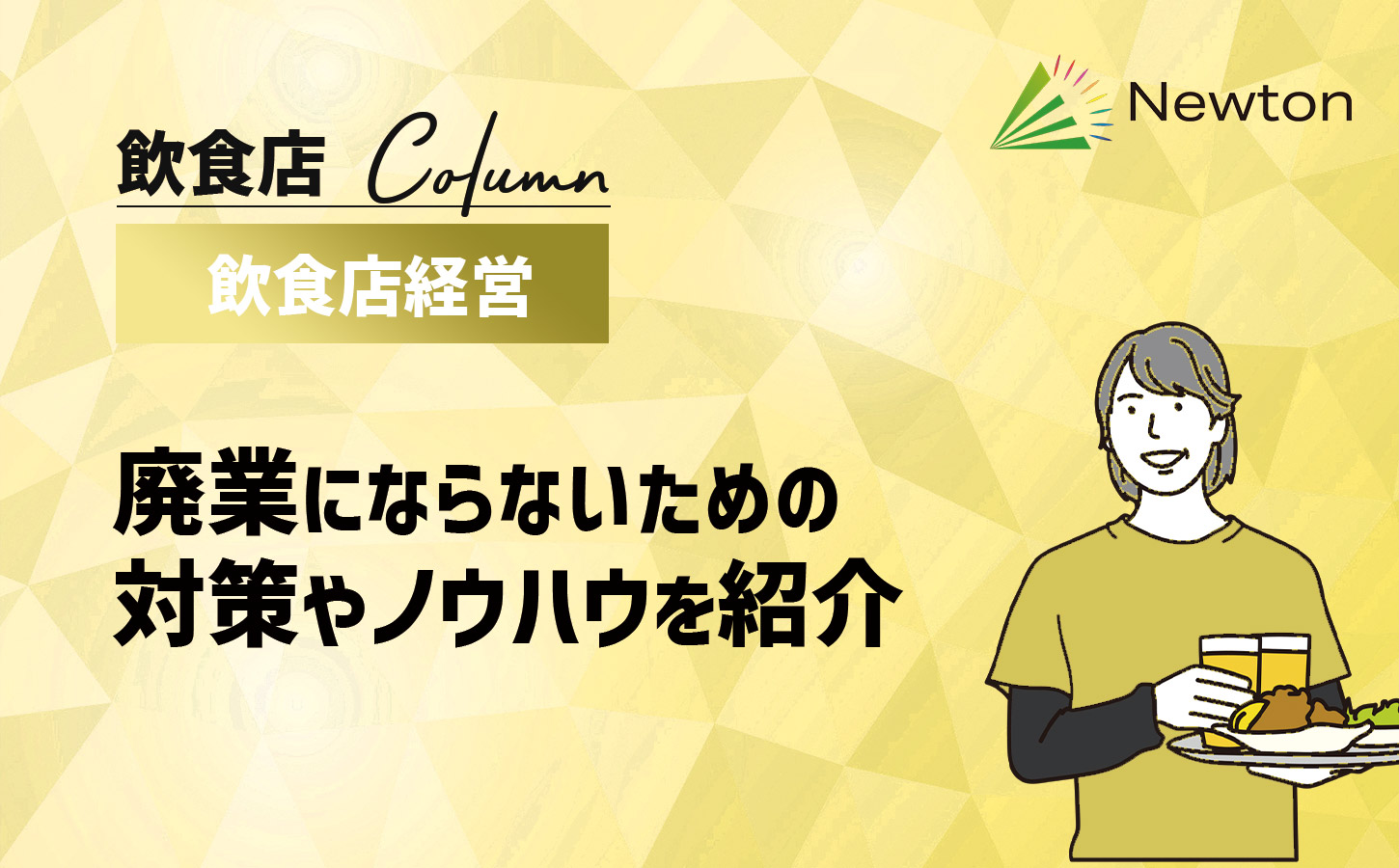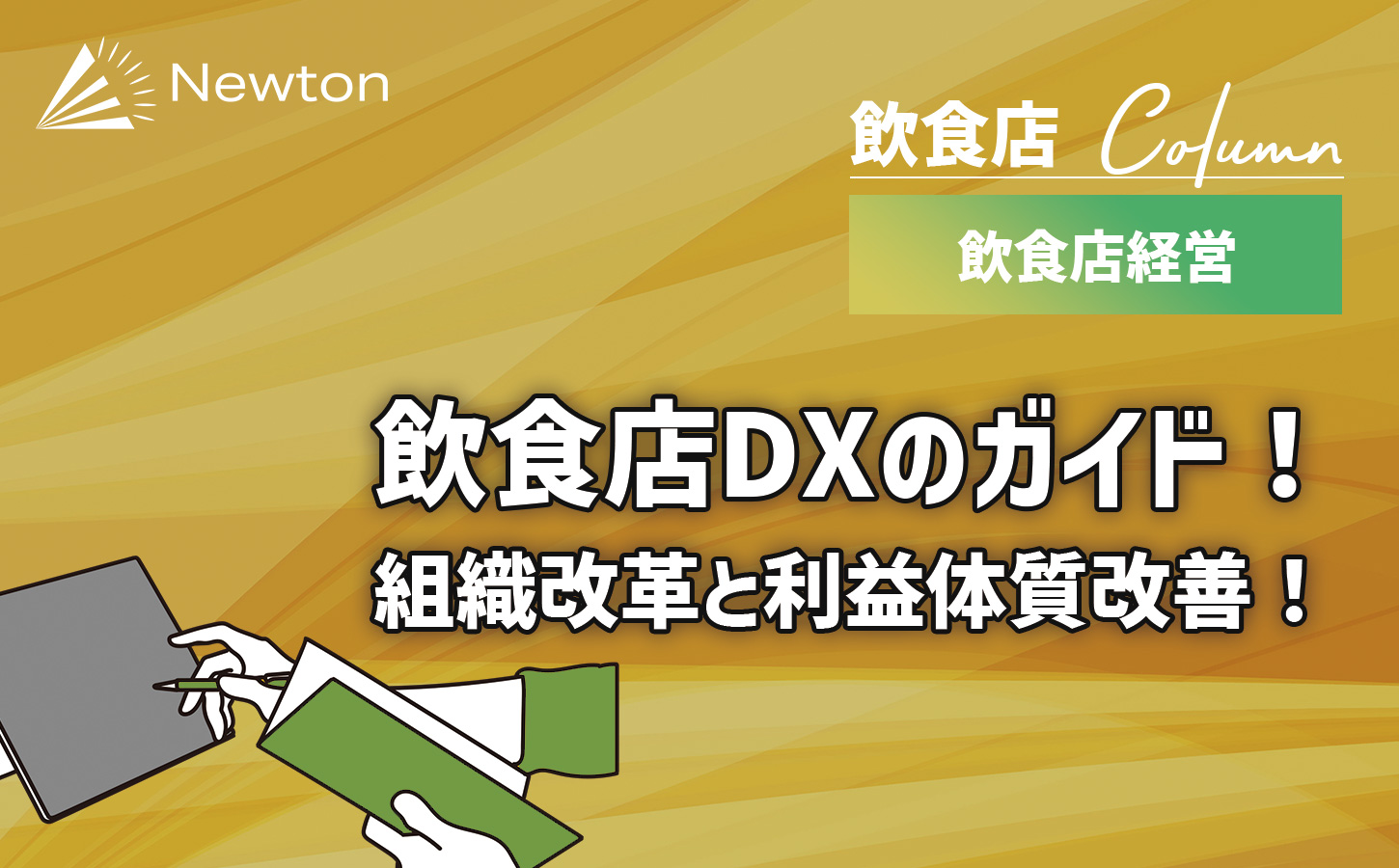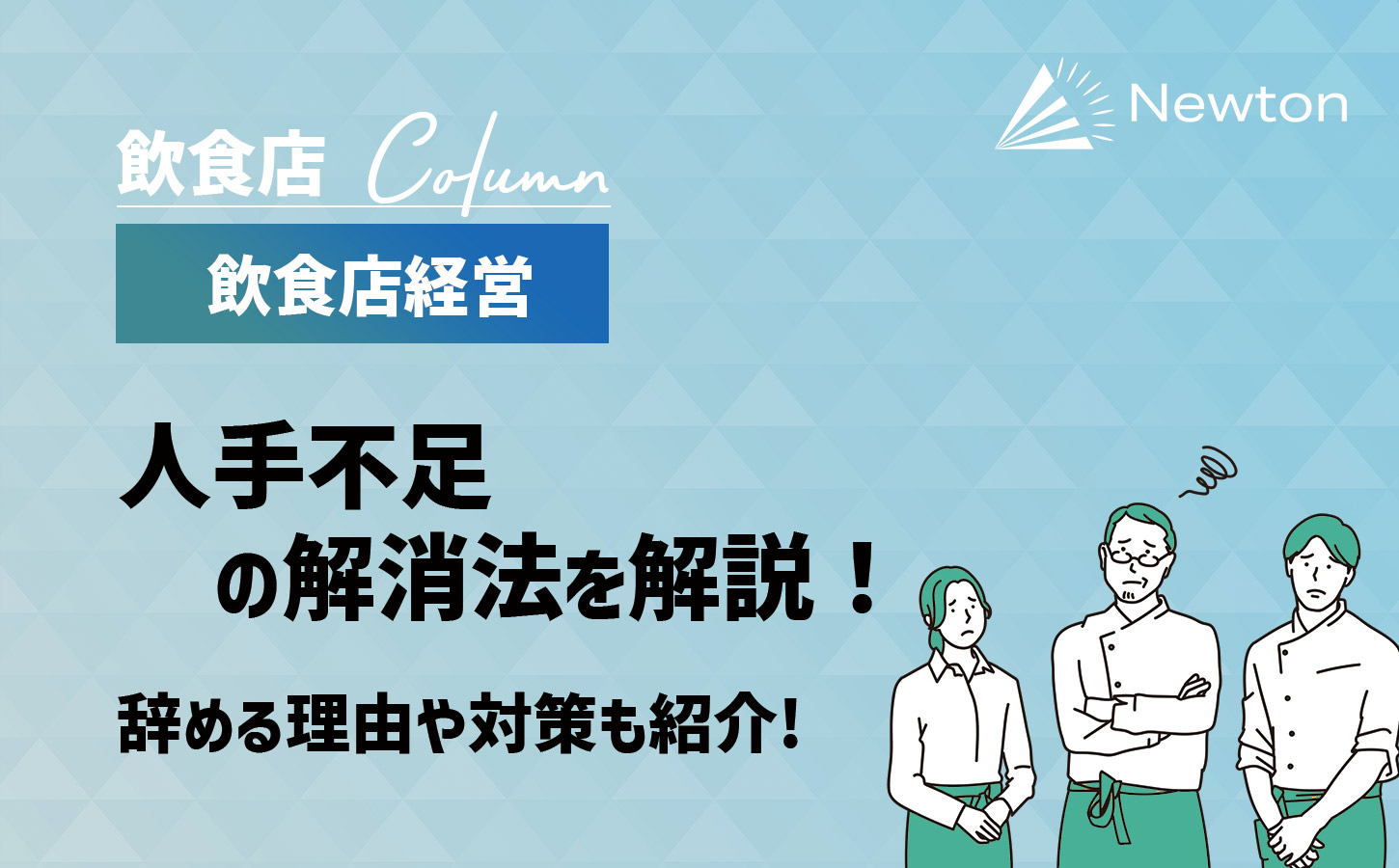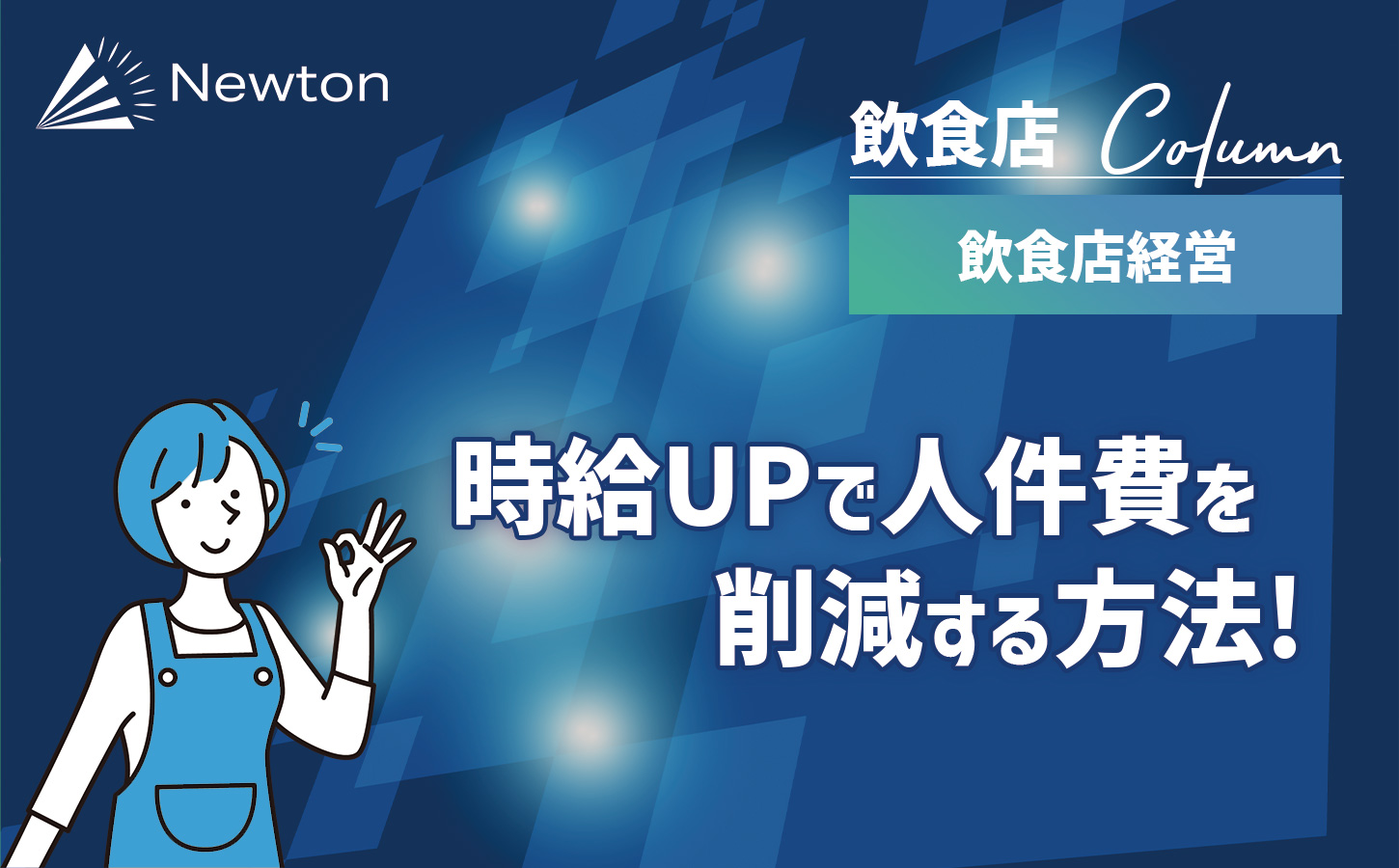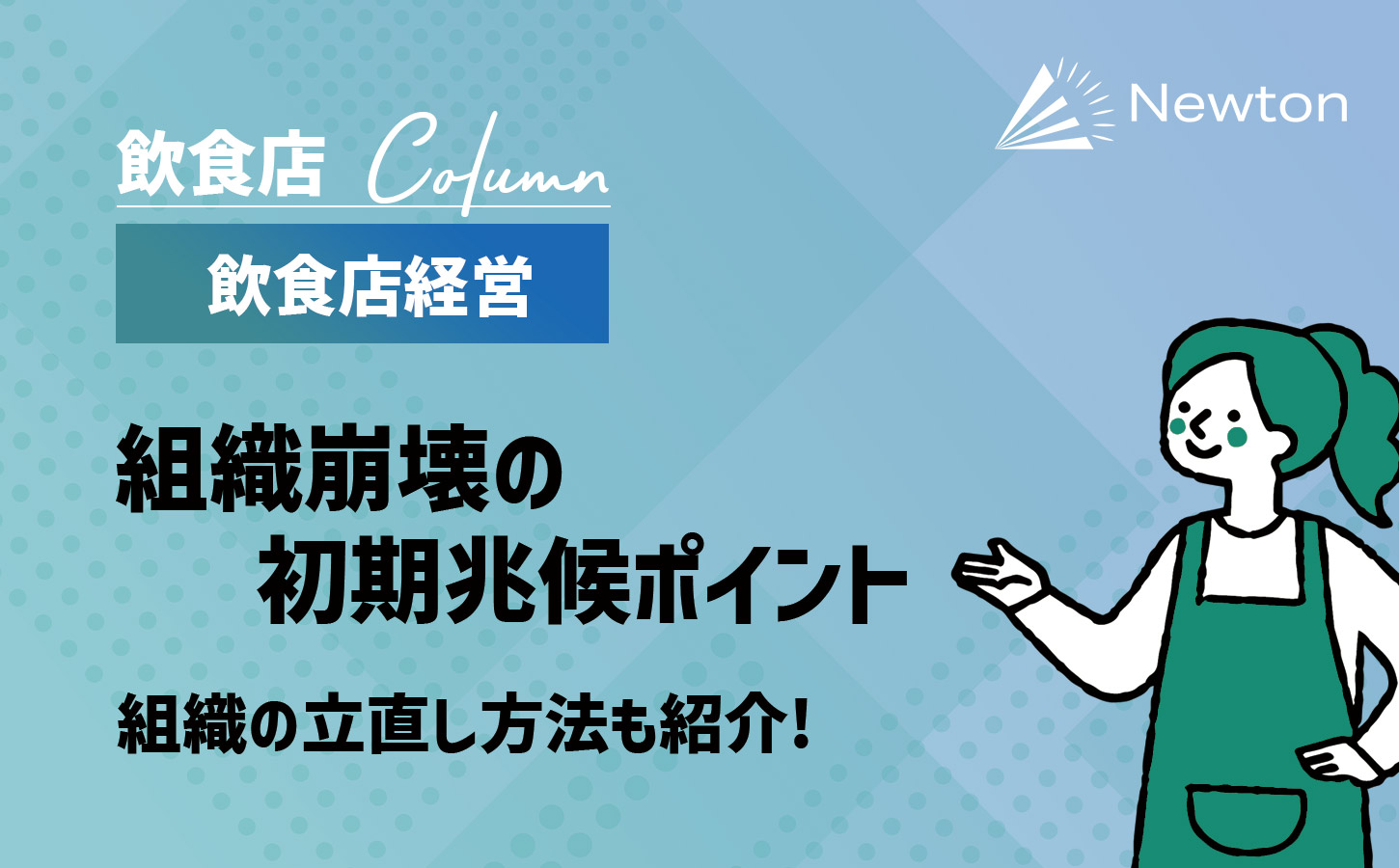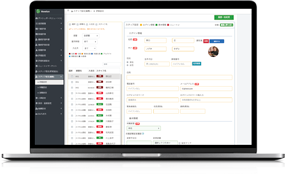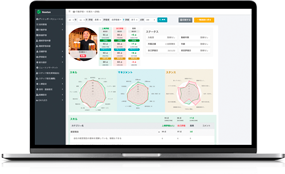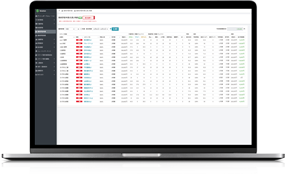人事評価に納得いかないと言われたら?不満の理由と対策を解説!
2024/06/24

多くの企業が導入している人事評価制度ですが、実施しているうちに「人事評価に納得いかない」という社員からの不満が出るケースは必ずと言っていいほど見受けられます。
本記事では、人事評価の不満の理由や見直すために意識するべきポイント、対処法や、納得度の高い評価制度について解説します。
人事評価に課題感を持つ方は、ぜひお役立てください。
「人事評価に納得いかない」と感じている人は案外多い
人事評価制度を長く見直しせずに運用していると、少なからず社員が不満を抱え、納得いかないという声は上がり始めるものです。
導入当初は成果主義で評価したいと考えていたのに、いつの間にか従来の年功序列制度のような評価制度の運用になってしまっている場合もあり、
その結果、業績低下や社員の離職、不服申し立てなどの事態にも繋がるかもしれません。
人事評価制度は社員の待遇やキャリア、昇進や昇格、報酬や給与に大きな影響を与えるため、公平かつ客観的に行う必要があります。
人事関連サービス会社のアデコが2018年に実施した「人事評価制度に関する意識調査」というアンケートでの調査結果では、
「勤務先の人事評価に満足している」と回答した人が約38%だったのに対し、「人事評価に不満を感じている」と答えた人は62%で、自社の評価制度に不満を持つ社員が多くいることがお分かりいただけるでしょう。
人事評価制度を導入する企業は増えてきていますが、まだまだ旧来の年功序列制度をそのまま運用しているところも多いことや、評価者の価値観や業務経験による評価のばらつきが、不公平感や不満が生まれる大きな要因となっています。
社員が人事評価に納得いかない主な理由

人事評価や人事考課は、従業員に納得感を持ってもらうことが非常に重要です。
- 明確な評価基準がない
- 評価者の価値観や主観による評価のばらつき
- フィードバックや説明が不十分
- 自己評価との不一致
ここでは、人事評価に納得いかないと言われる場合に考えられる主な理由をご紹介します。
明確な評価基準がない
人事評価に納得いかないといわれる場合、一番多いケースに、評価基準が不明確であることが挙げられます。
評価基準が上層部のみで共有され従業員に開示されていない場合や、そもそも評価基準が明確化されておらず曖昧な場合、また職務内容と評価基準が一致していない場合、従業員にとっては「不公平な評価」と感じてしまい人事評価への不満に繋がってしまうでしょう。
評価者の価値観や主観による評価のばらつき
人事評価を行う際、評価者の主観が入ってしまったり、なんとなくで感じている印象の影響を受けた主観で評価してしまっている場合、各評価者によって判断基準にぶれが出てしまうことがあります。
例として、目立つ印象に引きずられてしまう「ハロー効果」や、評価者が気に入っている部下を甘めに評価する「寛大化傾向」を始め、憶測で厳しく評価してしまう場合などがあります。
これによって、評価のばらつきが出てしまい、公平感が失われてしまうことが考えられ、人事評価への不満に繋がる可能性があります。
フィードバックや説明が不十分
評価結果に対し、従業員へのフィードバックが不十分だと、納得できない人事評価だと感じやすくなります。
フィードバックがあることで、従業員は自身の改善点や課題点が理解でき、今後の評価アップへの目標設定ができますが、フィードバックがなかった場合、評価結果に納得がいかず消化不良に終わり、会社自体への不信感に繋がってしまうでしょう。
自己評価との不一致
人事評価制度に不満を感じる理由として、意外と多いのが「自己評価よりも低く評価され、その理由が思い当たらない」という意見です。
自己評価が高い従業員の場合、会社からの評価を過剰に期待してしまうことがあり、「頑張りが待遇に反映されていない」と判断してしまいます。しかし、自分は頑張っていると思っていても、実際に結果が出ていなかったり、頑張る方向性がずれている場合もあります。
人事評価の評価基準
人事評価の評価基準は、一般的に「能力評価」「業績評価(成果評価)」「情意評価」で構成されます。
業務を遂行する上で求められるスキルや知識といった従業員の能力や、その能力自体がどれくらい発揮されたかを評価する「能力評価」、
一定期間における会社への貢献度を評価する「業績評価(成果評価)」、
従業員の規律性、責任感、協調性、積極性など、仕事に対する姿勢や態度を評価する「情意評価」が主な基準となっており、
各評価軸において、具体的な評価項目と評価基準を定めるようにするのが、納得度の高い人事評価におけるポイントです。
人事評価への不満がもたらす影響・デメリット

人事評価への不満を解決せずに放置してしまうと、会社にとって大きな弊害へと繋がってしまうでしょう。ここでは、人事評価への不満がもたらす影響、デメリットをまとめます。
- 社員の離職や転職
- 社員のエンゲージメント・モチベーション低下
- 業績低下
- 不服申し立てのリスク
自己評価と会社からの評価にギャップが生まれてしまうと従業員の不満に繋がってしまうため、普段からのフィードバックが重要になるでしょう。
社員の離職や転職
納得いかない人事評価における一番の悪影響は、離職率の増加です。
人事評価の結果に納得いかない従業員は、より適正な評価をしてくれて、より良い就業環境を与えてくれる会社への転職を考え始めます。特に優秀なコア人材ほど判断も早く、その傾向が見受けられます。
会社に必要な人材の離職が続くと会社の業績低下に繋がったり、プロジェクトの進捗が遅延するだけでなく、離職率が増加してしまうと新たな人材の採用や育成にもコストが必要になるため、ダメージは大きいでしょう。
社員のエンゲージメント・モチベーション低下
人事評価への不満があると、会社への不信感へ繋がってしまい、「どうせ評価されないなら成果を出しても意味がない」といった思考からモチベーションが下がってしまうことが考えられます。
納得いかない社員がいると、愚痴や文句を言い始め、周囲へも悪影響を及ぼしてしまい、チームワークが悪くなる他、会社全体の業績低下や離職にも繋がってしまうリスクがあります。
業績低下
人事評価に納得いかない社員が増えると、組織全体の業績低下も起こりうるでしょう。
納得できないことにより仕事への意欲が低下し、適当に業務を行い仕事の質が落ちていき、結果として業績低下に繋がります。
人事評価を適切に行わないと、企業としての大問題に繋がりかねないのです。
不服申し立てのリスク
人事評価に納得いかない場合、最も注意するべきリスクが不服申し立てのリスクです。
人事評価で不当に低い評価が続いたり、また広角がなされるようなケースはトラブルに発展する場合があります。
実際に過去には、当事者間で解決に至らず、訴訟になることもありました。
過去判例として、不当な人事評価や、差別的であると感じた社員の訴えが認められ、企業側が法的な制裁を受けた事例があります。
訴訟となると企業の評判に悪影響を及ぼし、法的な費用や賠償金の支払いにもつながるため、人事評価の公平性には厳密な注意が必要です。
コンプライアンスの観点でも、人事評価の不満を解消し、結果に法令違反がないか、人事権の濫用がないかといった会社側の注意をもって公正性を担保することが求められます。
人事評価への納得感を高めるために意識するポイント

人事評価への納得度を高めるためには、評価者によってばらつきがでない、信頼性・公平性の高い制度が大切になります。
ここでは、人事評価への納得感を高めるために意識するべきポイントをまとめました。
- 納得できない理由を調査する
- 評価項目を明確化する
- 評価エラーをなくす
納得できない理由を調査する
「人事評価に納得いかない」という声が上がった場合、不満が解消されない限り、評価制度への納得度が上がらないため、その納得いかない理由をしっかりと調査する必要があります。
納得できない理由の調査には、アンケートや1on1ミーティング、面談の実施を通し、互いの認識をクリアにするのが有効です。
評価項目を明確化する
人事評価が低い社員は不満を持ちやすいため、納得感を持ってもらうためにも、評価項目や企業理念を明確化することが大切です。
事前に数字やレベルなどの具体的な指標を用いて評価軸を定め、共有しておくことで、社員自身も目標設定がしやすく、仕事へのモチベーションが高まり、目標達成に向けて意識的に取り組むことができるでしょう。
主に活用される評価項目としては、上述の「人事評価の評価基準」を参考にしてください。
評価エラーをなくす
人事評価における評価の誤りや認識のずれを「評価エラー」と呼びます。
評価者の偏見や先入観といった心理的作用により評定誤差が生じてしまうことですが、この評価エラーは無意識のうちに発生してしまい、人が人を評価する以上どうしても仕方のないことです。
こうした評価エラーを避けるためには、起こりうる人事評価エラーを事前に把握しておくことや、評価基準を明確にし、公平さを保つことが大切になるでしょう。
人事評価の不満への具体策
人事評価制度にもさまざまな手法がありますが、その制度内容を見直し、自社に合ったものにすることも有効です。
- 目標管理制度(MBO)
- コンピテンシー評価
- 360度評価
- ノーレイティング
評価制度の種類や特徴を改めて確認しましょう。
目標管理制度(MBO)
MBOとはManagement by Objectivesの略で、直訳すると「目標管理制度」となります。1954年にP.F.ドラッカーが著書「現代の経営」で提唱した組織マネジメントの理論で、経営目標や部門目標を踏まえて個人目標を設定し、目標の達成度を評価する手法です。
従業員それぞれが個人目標を設定し、その進捗や達成度合いに応じて人事評価を決める手法で、会社の経営目標や部門目標と連動した個人目標を立てるため、個人と組織の成長を同時に達成させ、相互に納得感を高める効果があります。
コンピテンシー評価
コンピテンシーは、「業務を遂行する能力や行動特性」を指します。
コンピテンシー評価とは、パフォーマンスの高い従業員に共通するコンピテンシー(行動特性)をモデルとして評価基準に落とし込み、従業員の評価基準を作成する人事評価制度の手法で、従業員はその人物の業績に近づくために、設定された行動目標を目指し、上司や同僚からの評価を受けながら行動改善を目指す人事評価制度です。
コンピテンシー評価は「行動特性」を評価するのが特徴なため、公平性の高い評価制度として導入する企業が増加しています。
360度評価
360度評価とは、上司・部下・同僚など、社員に関係するさまざまな立場から多画的に評価を行う手法です。
一般的な評価制度では上司のみが評価者となりますが、360度評価ではさまざまな関係者から評価してもらうため「多面評価」とも呼ばれ、多角的に意見を吸い上げ反映させることで、客観的な評価が可能となります。
そのため一方的な評価に比べて客観性を保ちやすく、被評価者が納得しやすいのが特徴です。
ノーレイティング
ノーレイティングとは、ランクづけをしない人事評価制度の手法です。
頻繁なフィードバックにより評価を都度積み上げ、目標達成までの軌道修正を重ねる人事評価制度で、相互のコミュニケーションが活性化します。
一般的な人事評価制度では、一定期間で上司がフィードバックを行う手法になりますが、対してノーレイティングはリアルタイムで人事評価をするのが大きな違いで、常に認識をすり合わせているため、互いに納得のいく評価ができ、信頼関係が構築できるのが特徴です。
人事評価の運用を効率的に進めるなら「ニュートン」
人事評価制度に納得いかない社員を抱えていると、さまざまなデメリットがあるのがお分かりいただけたでしょうか。
不満に繋がる理由を調査し、しっかりと対策を進めていくことが重要です。
とはいえ、管理や運用は簡単なものではないため、あらかじめ仕組み化されている人事評価ツールの活用が有効でしょう。
納得度の高い人事評価制度により組織の成長に繋がる人材育成を目指したいなら、タレントマネジメントや人材育成に特化した特許取得済のツール「ニュートン」がおすすめです。
この記事を書いたライター

Newton編集部
飲食店の人事に役立つ情報を発信していきます。人材から人材へ、人が育つ人事評価システムNewtonとは、飲食店に特化したタレントマネジメント+人事評価システムです。
管理者の人事管理のパフォーマンスを上げるだけでなく、スタッフのモチベーションアップや、離職率の低下、企業にとっての人材を守るシステムです。詳しくはこちら