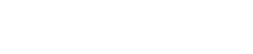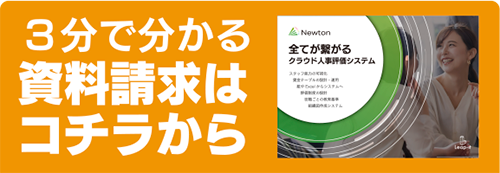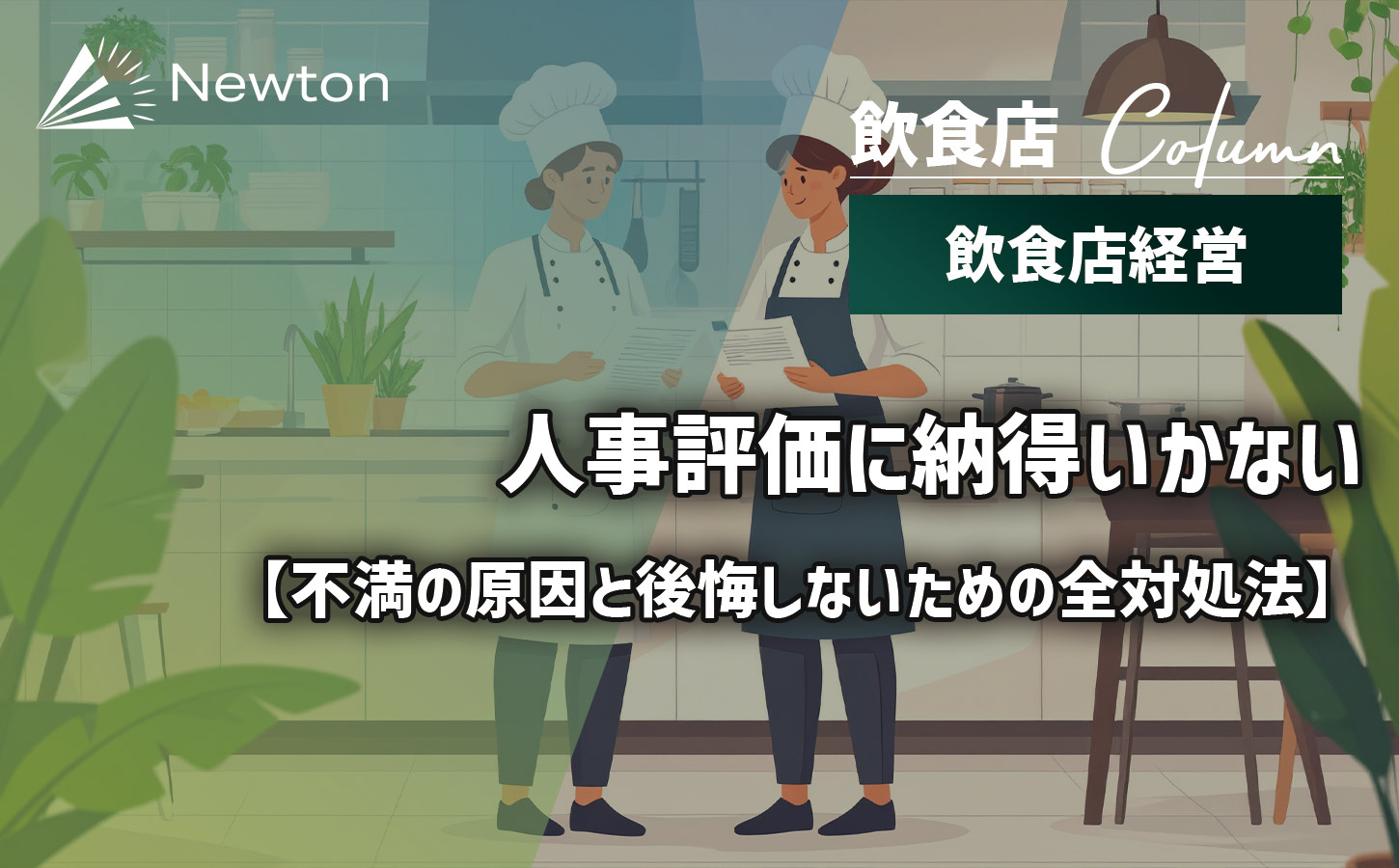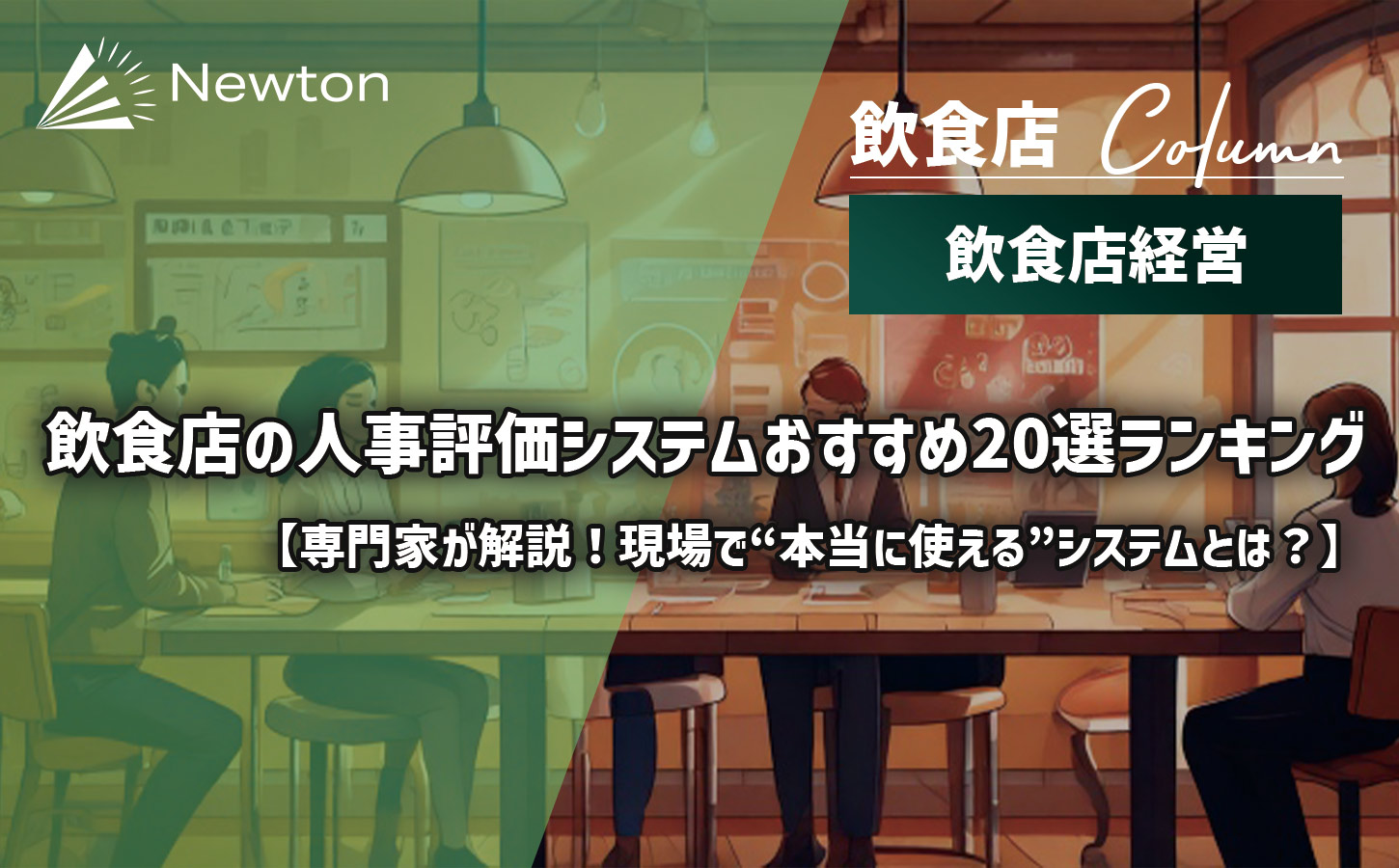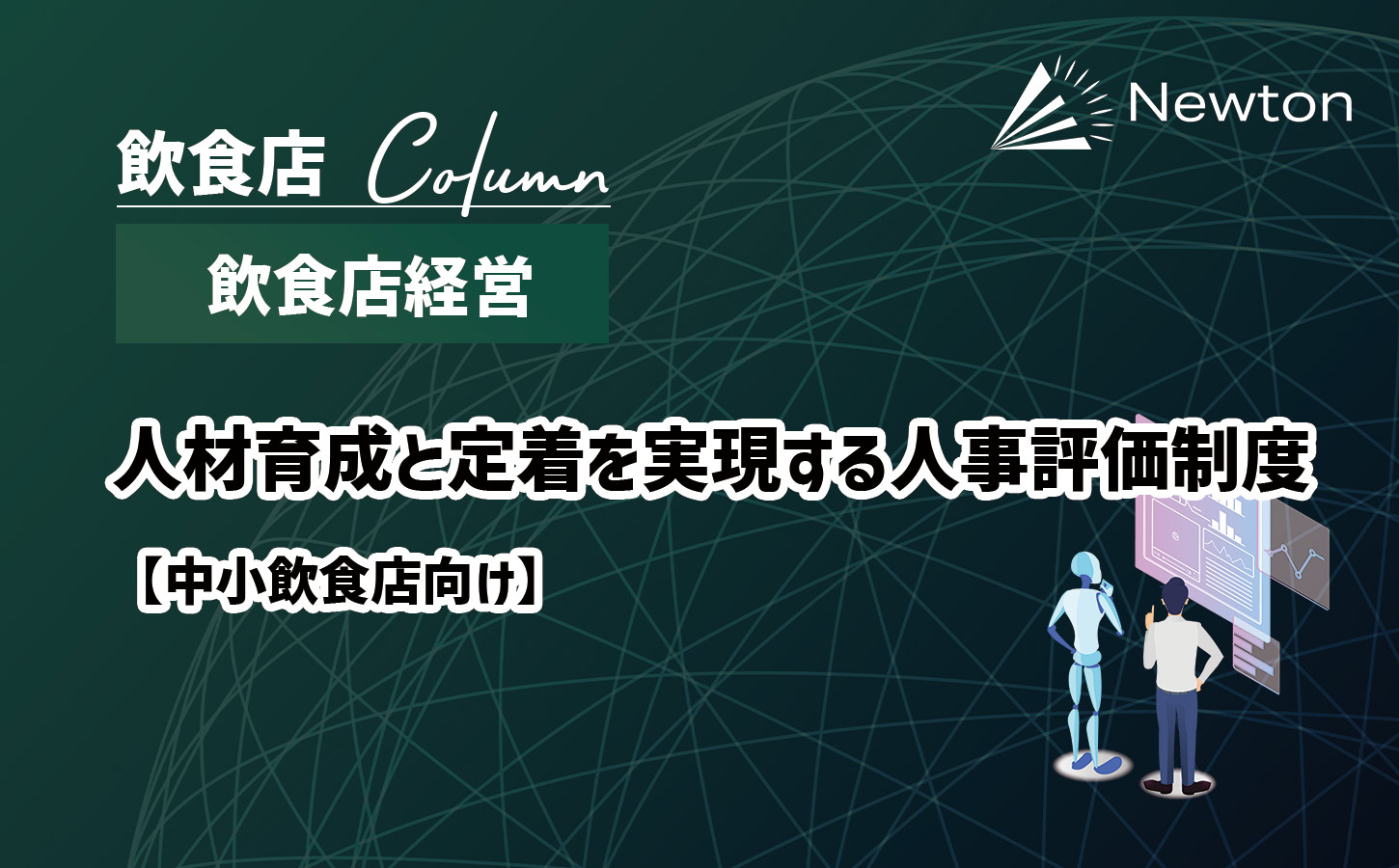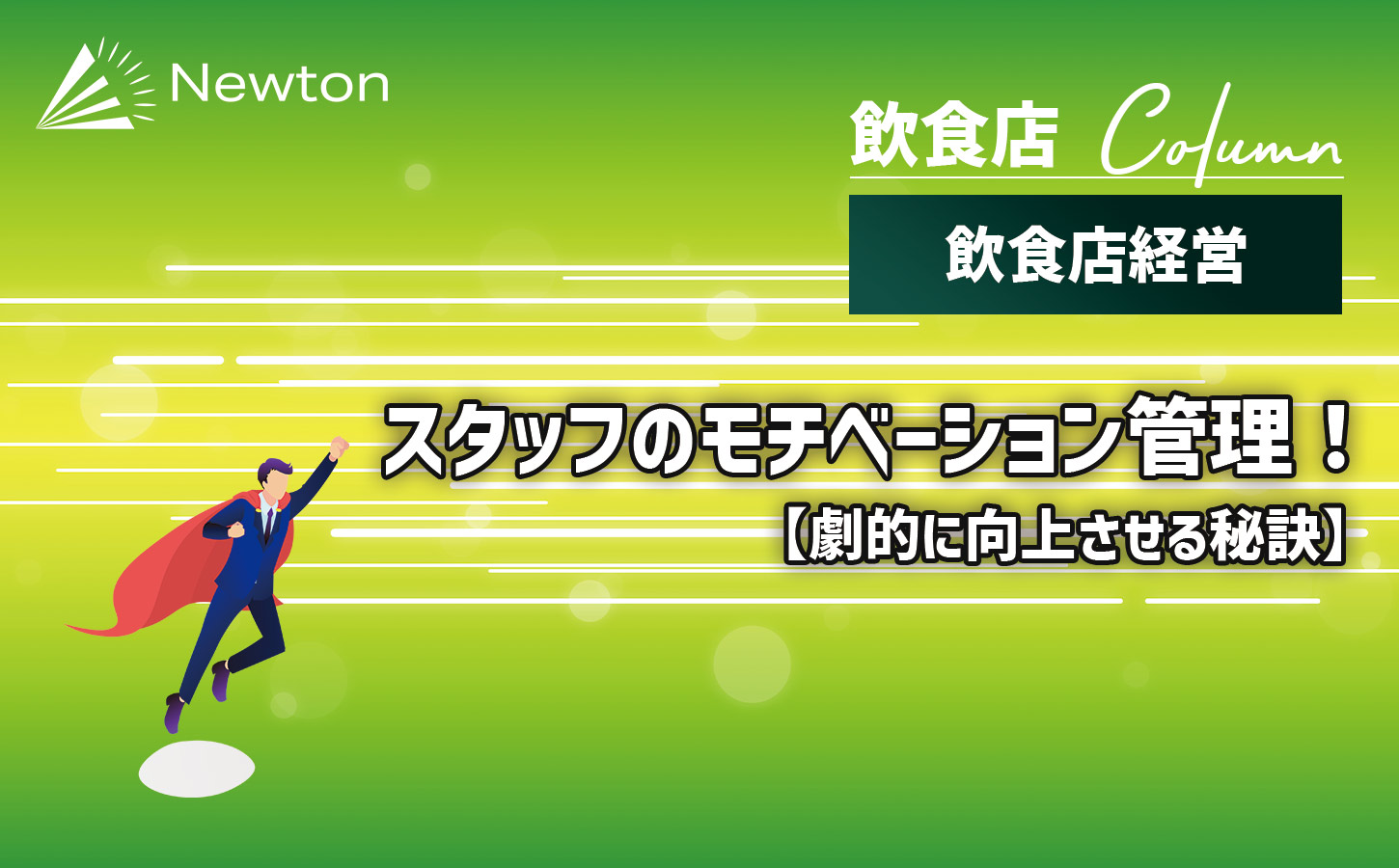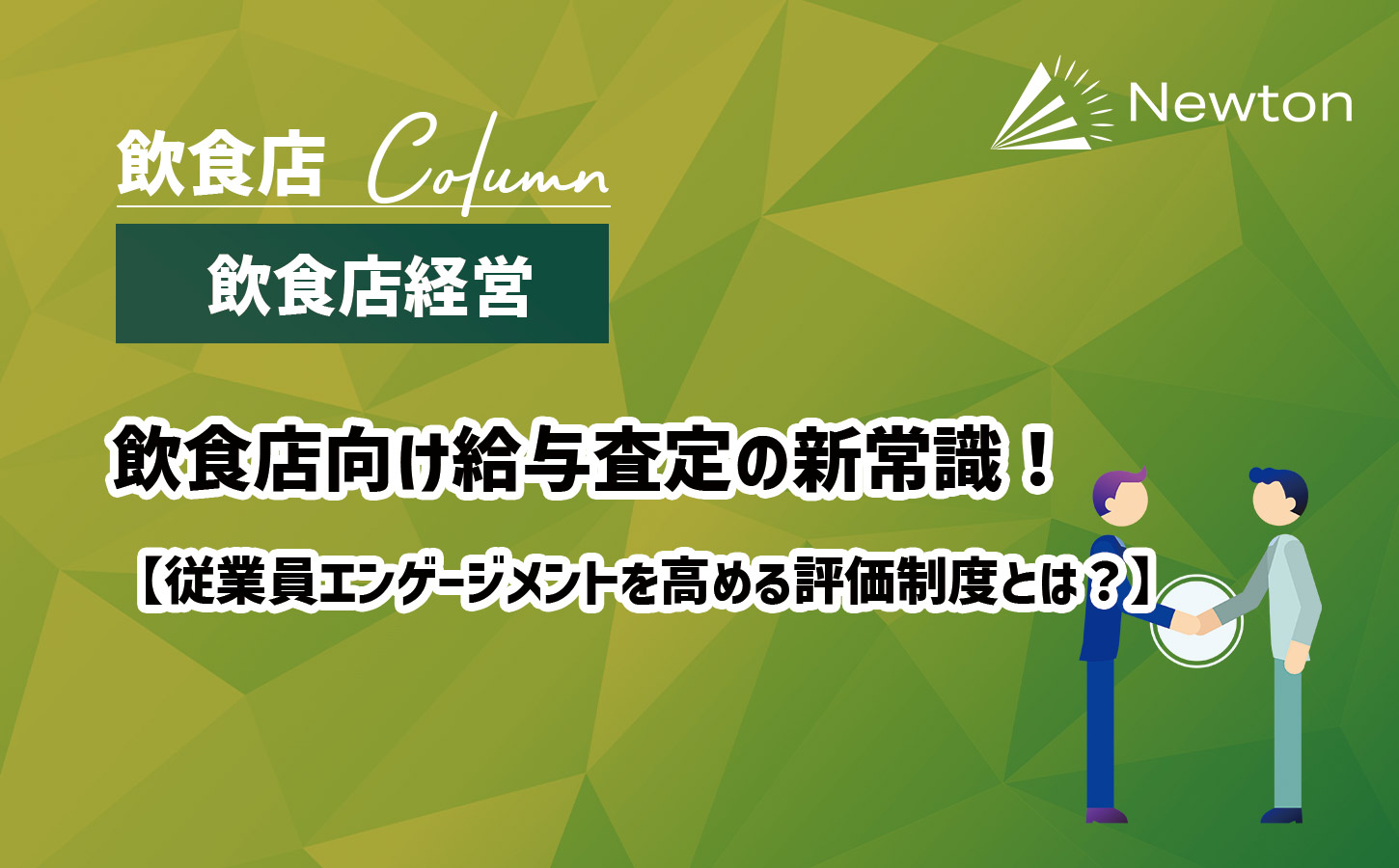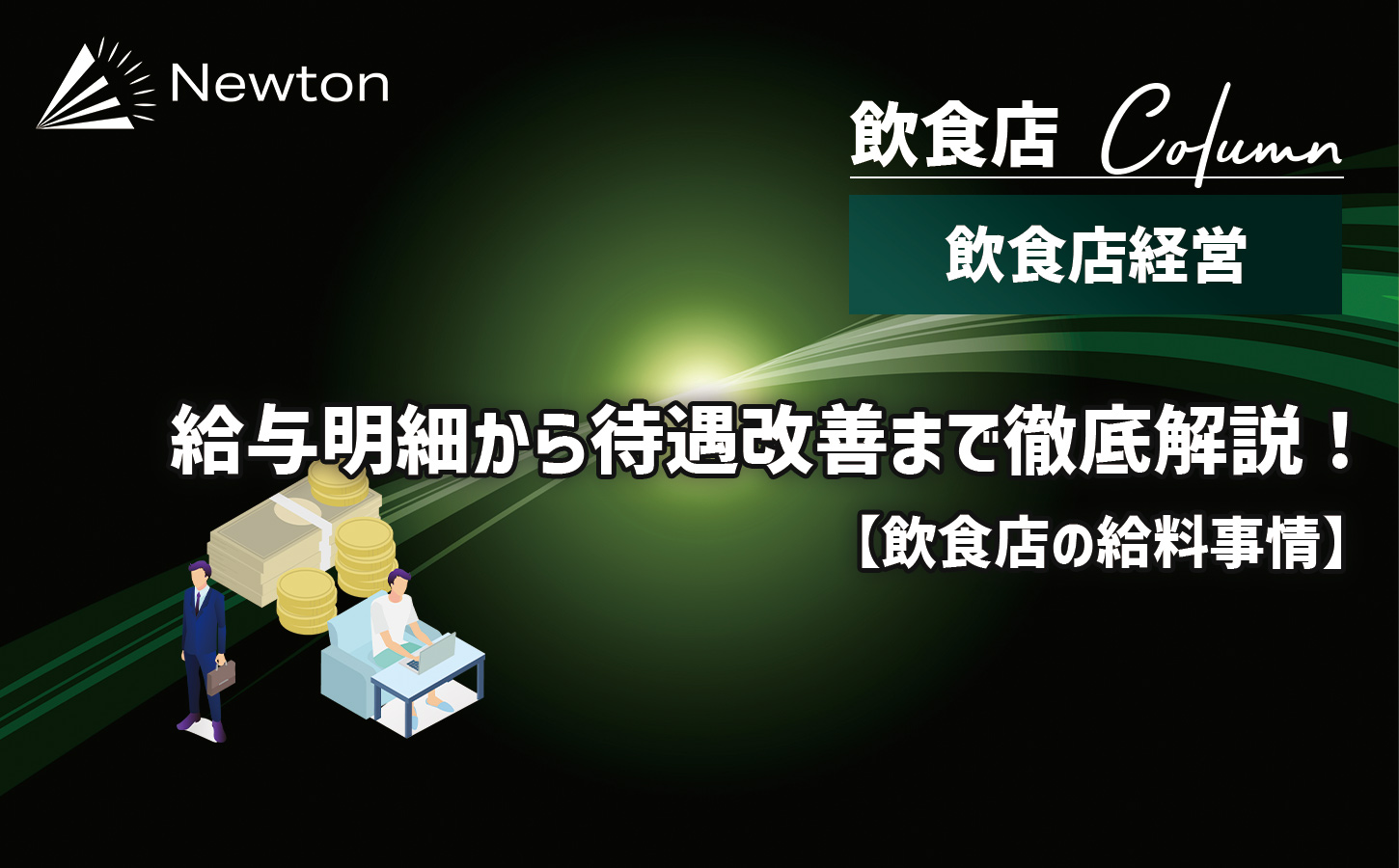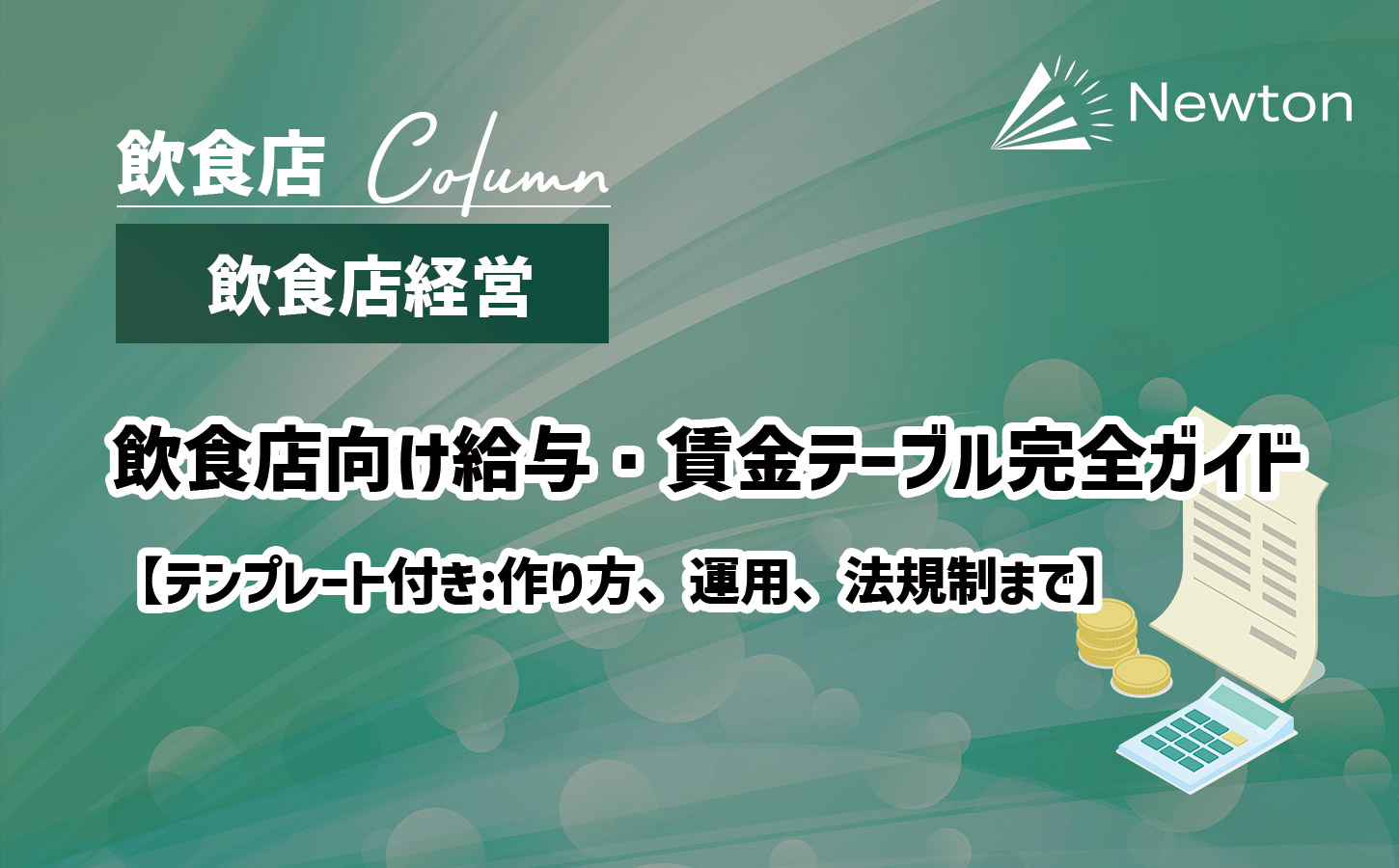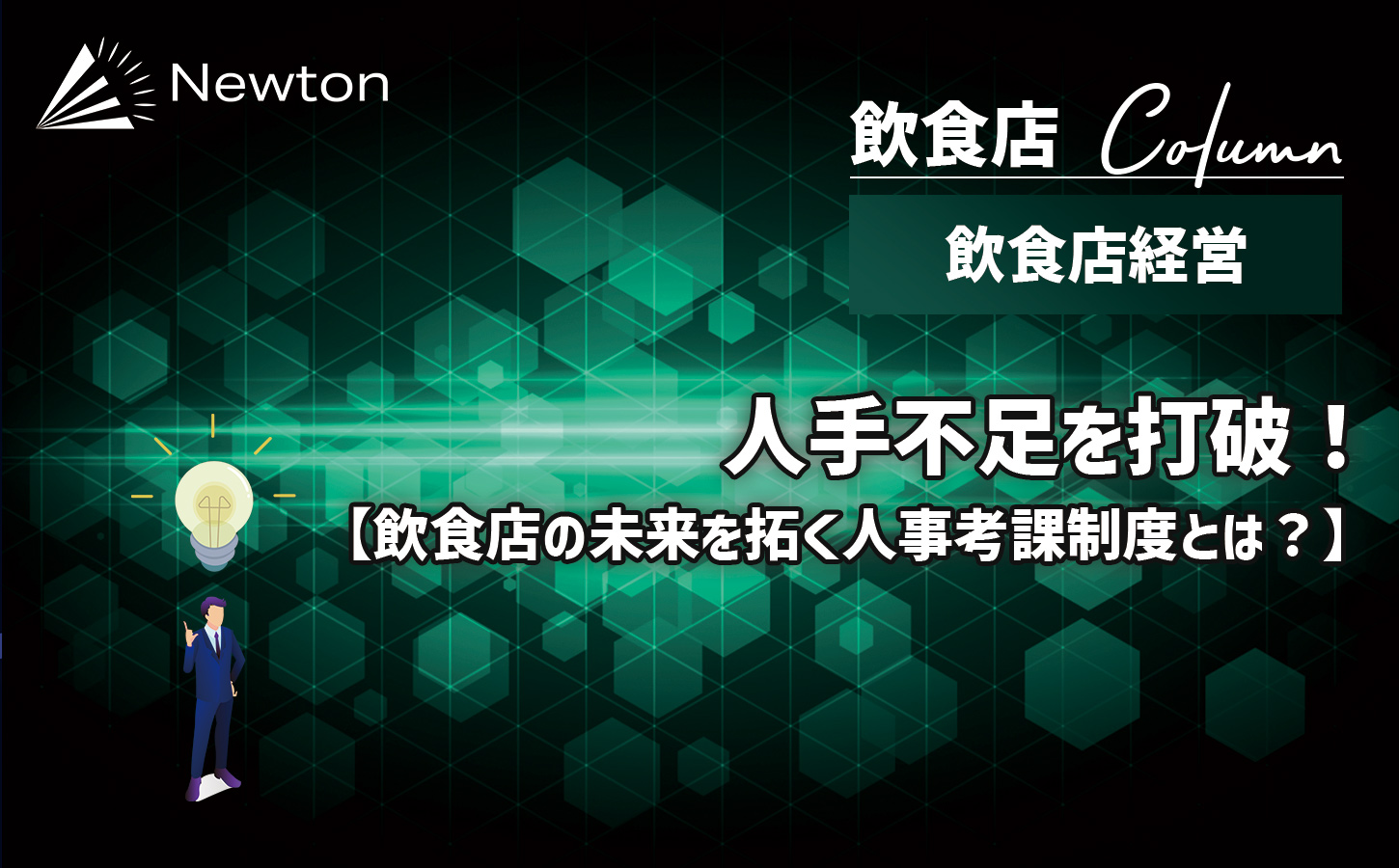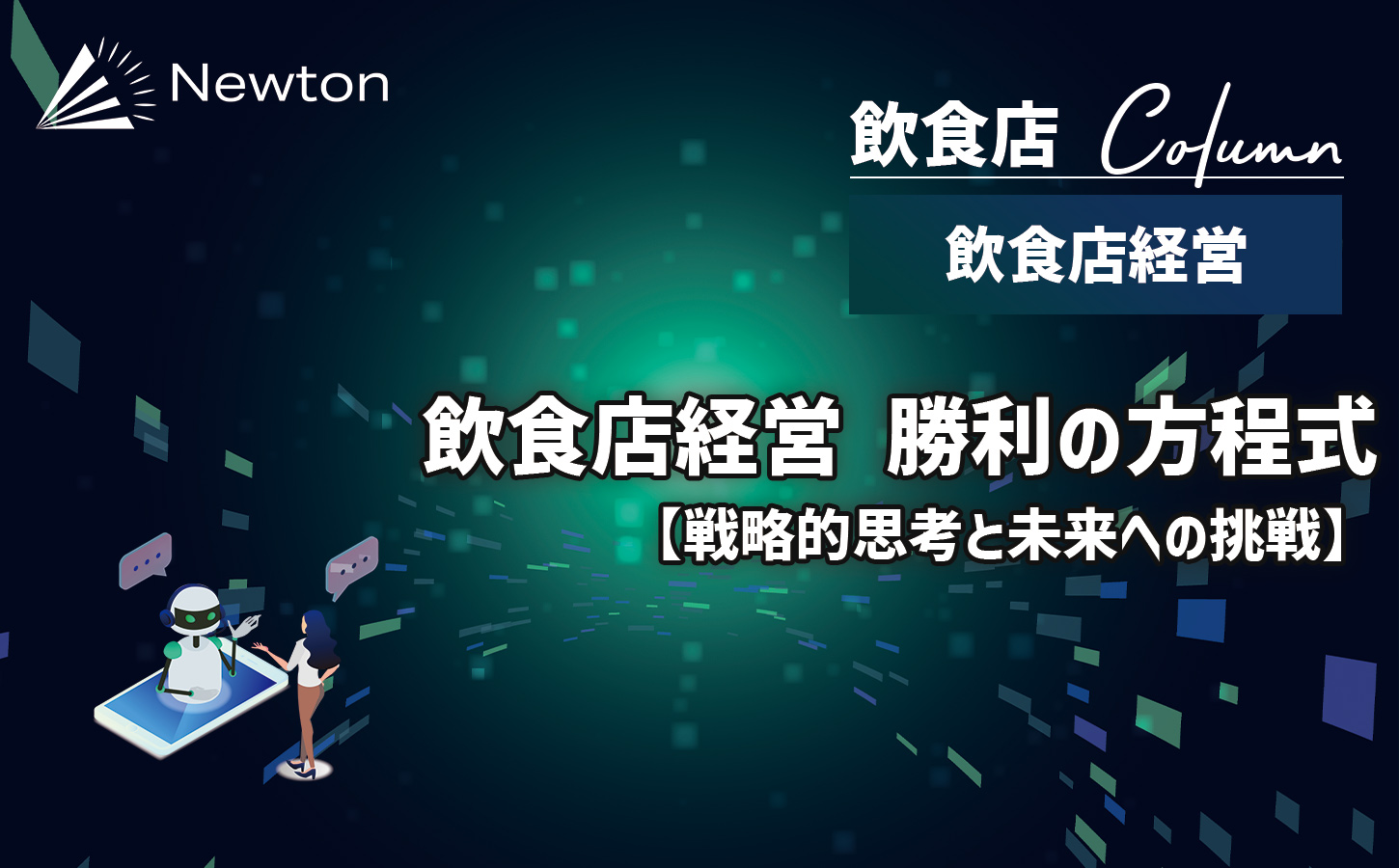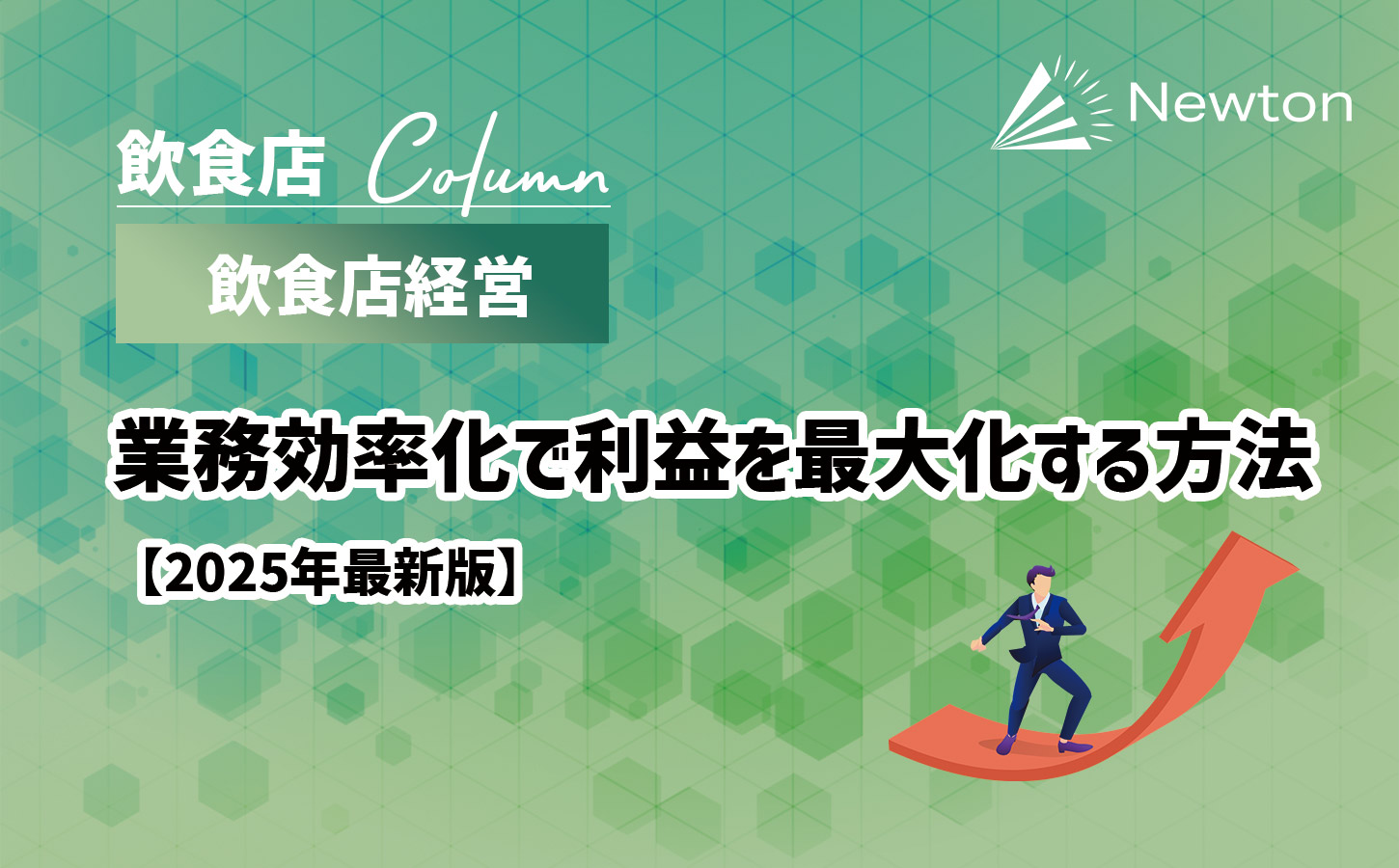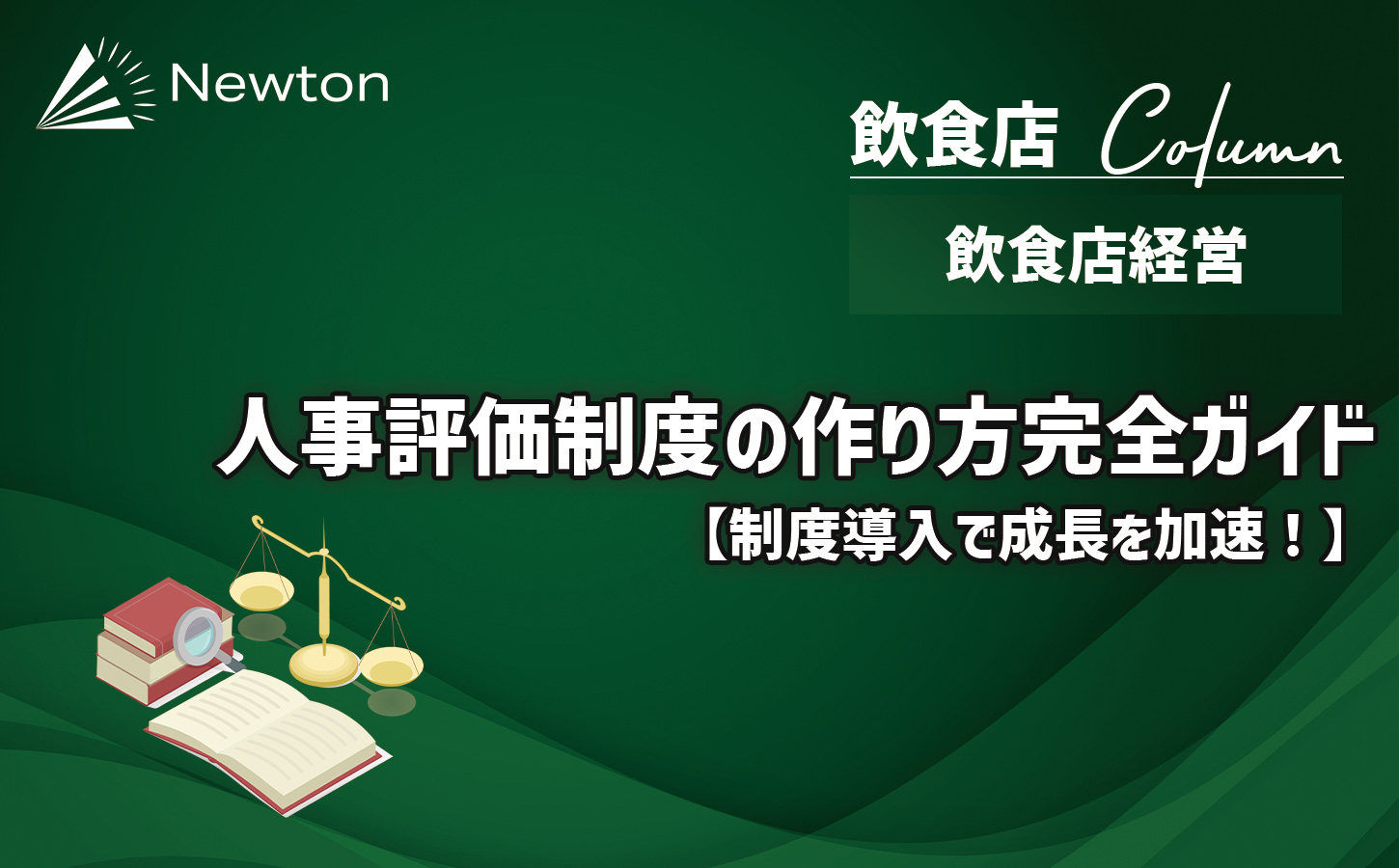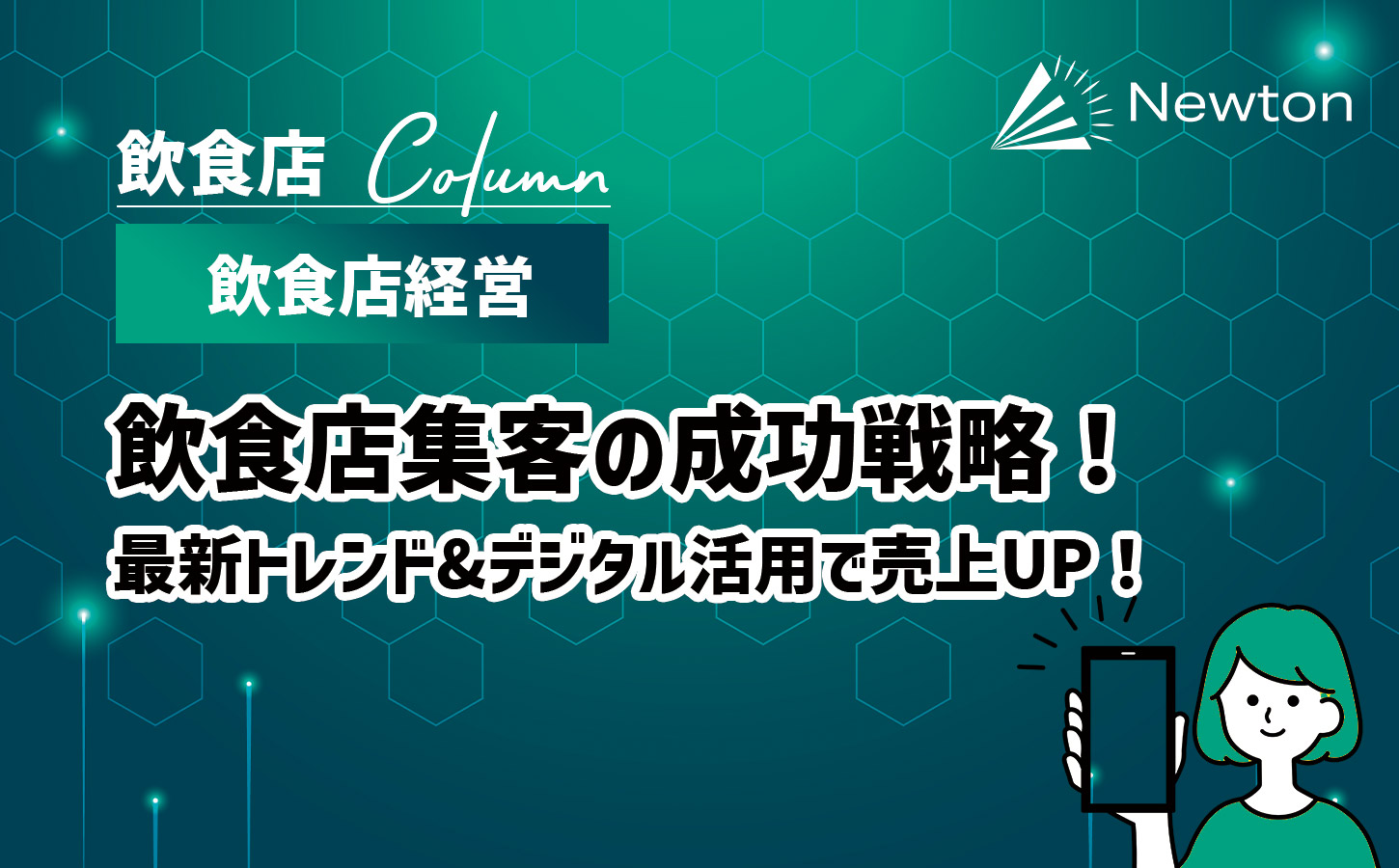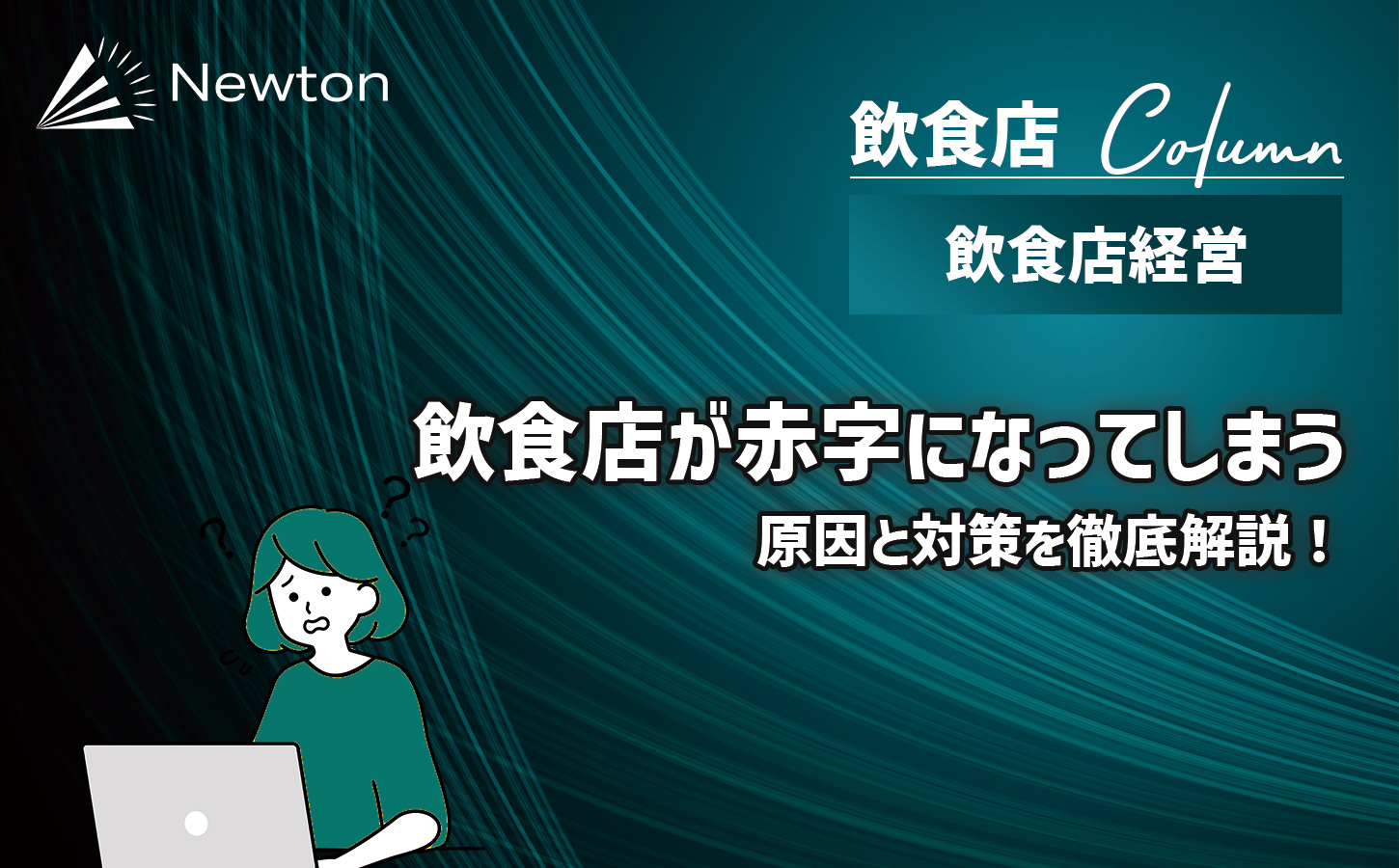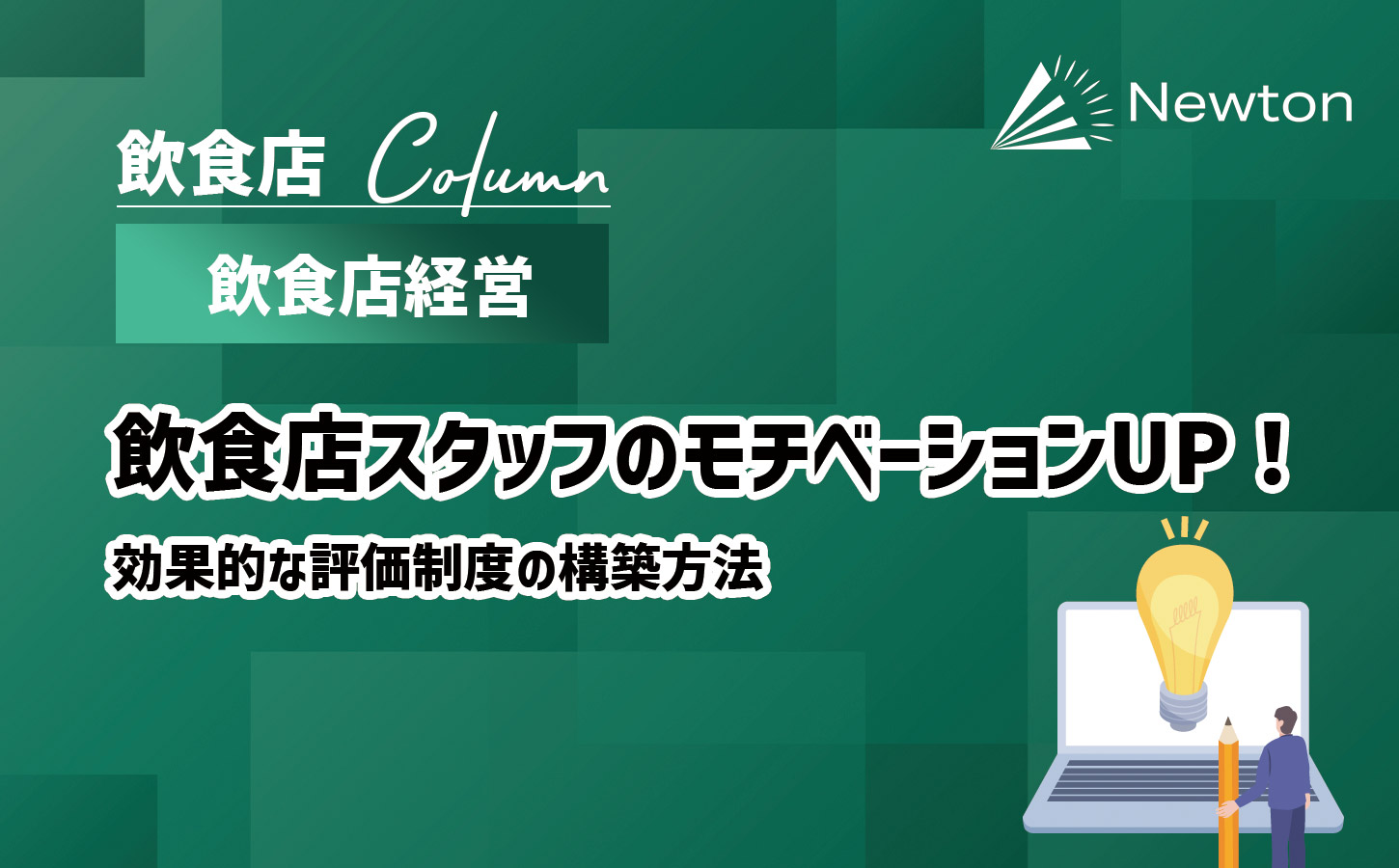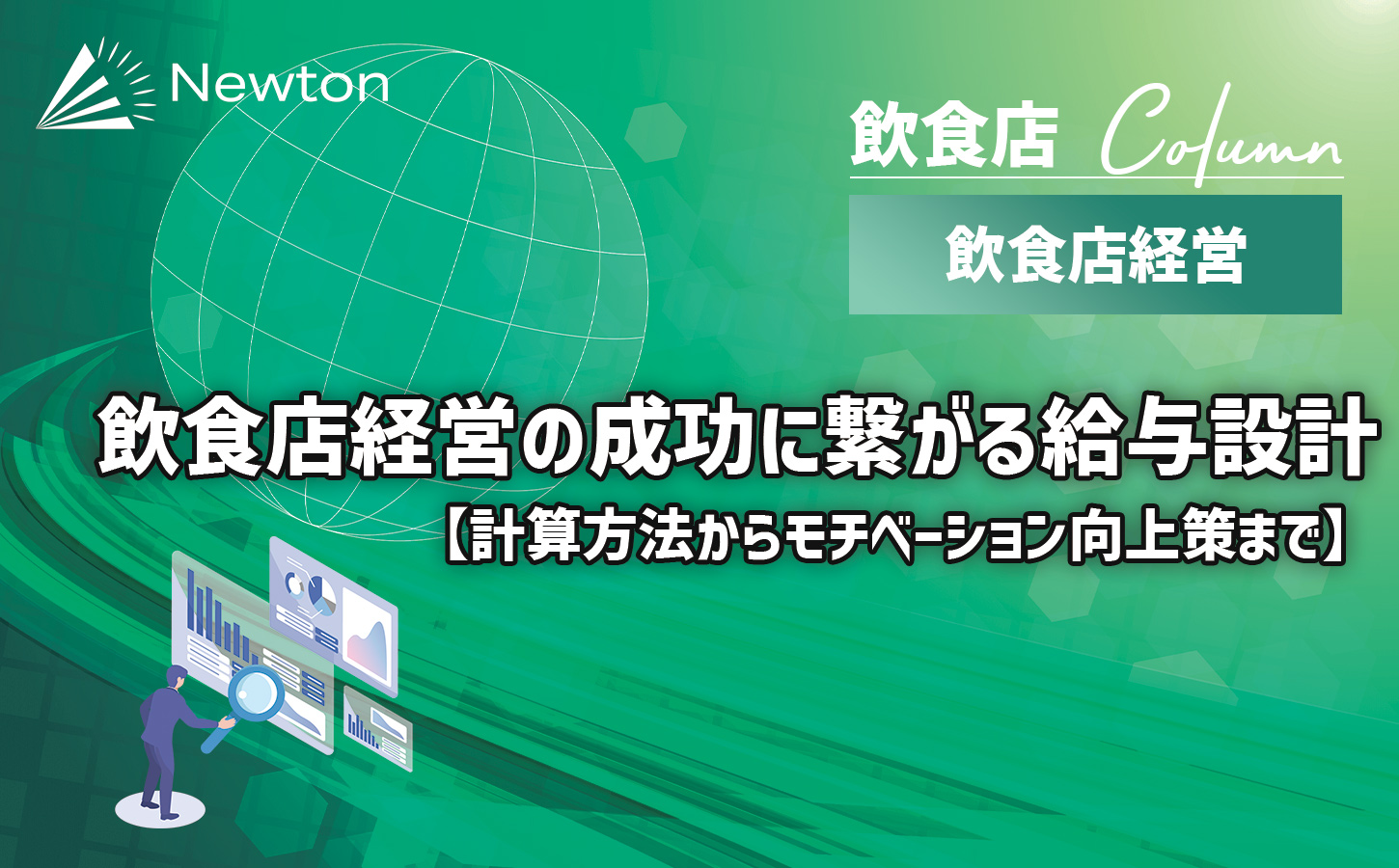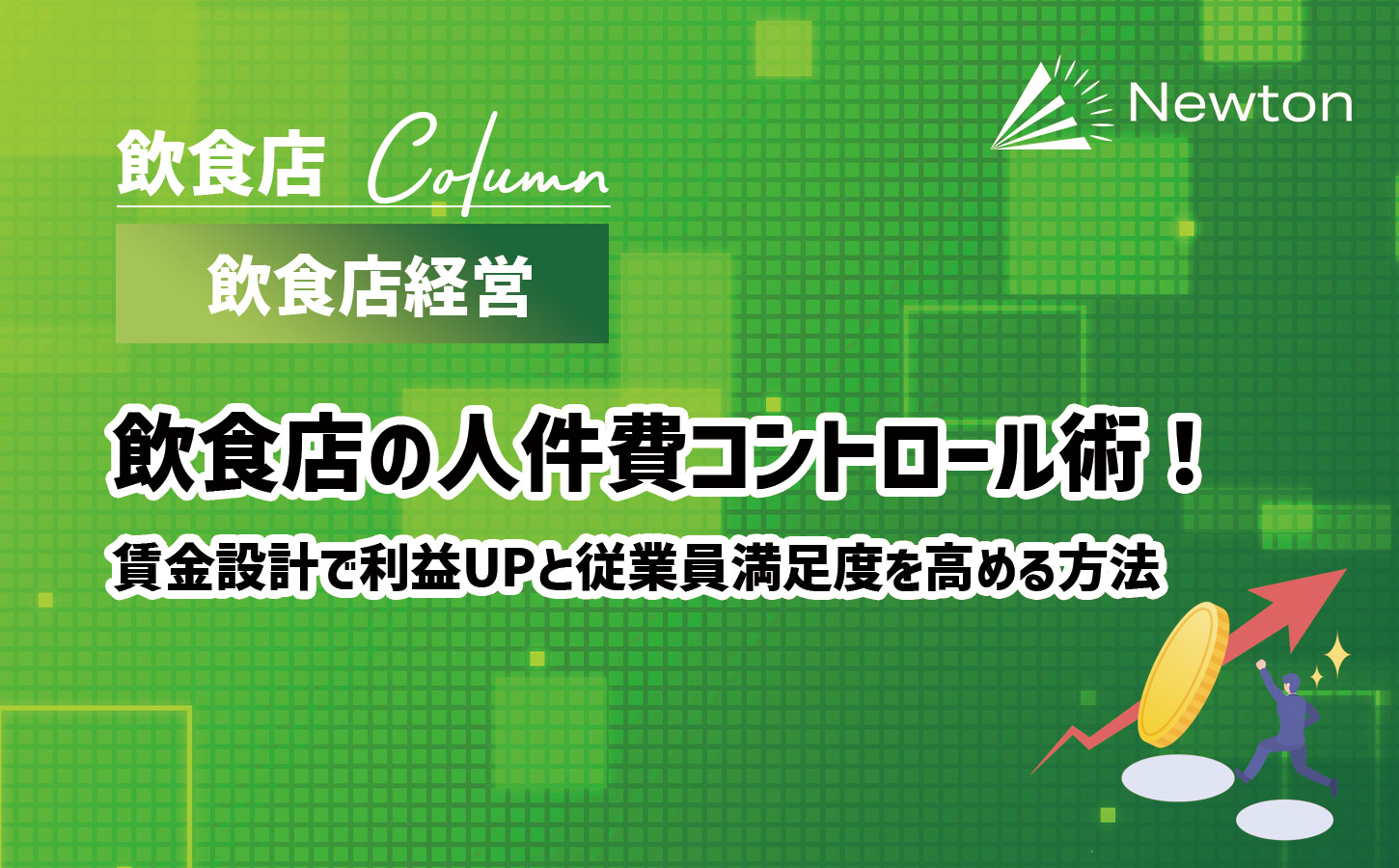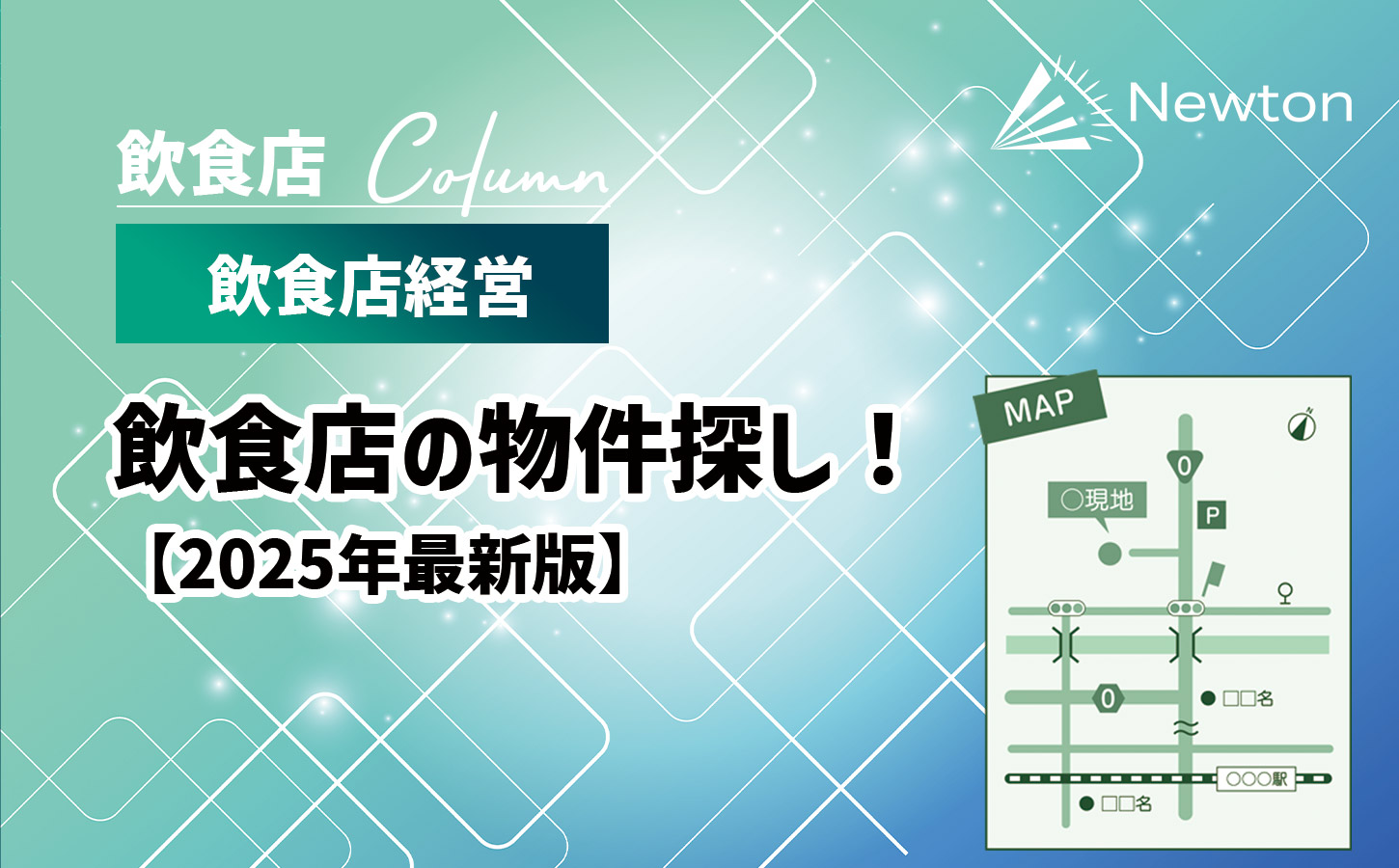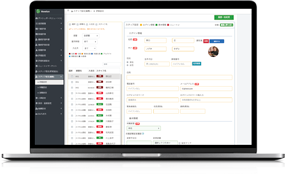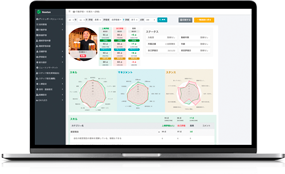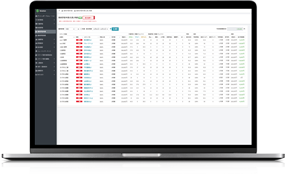人事評価コメントの書き方と注意点を解説!職種別の上司コメントの例文もご紹介!
2024/09/30

人事評価のコメント作成、毎年頭を悩ませていませんか。
部下の日々の頑張りを認め、成果を的確に言葉にするのは、簡単なことではありません。
「もっと気の利いた、的確な表現はないか」
「改善点を伝えるときに、相手のモチベーションを下げてしまったらどうしよう」
PCの前でうんうん唸りながら、多くの管理職が同じ悩みを抱えています。
この記事では、そんなあなたのために、人事評価の上司コメントに関するあらゆる悩みを解決します。
コピペしてすぐに使える職種別の豊富な例文から、部下のやる気を引き出し、成長を促すための具体的な書き方のコツまで、網羅的に解説します。
この記事のポイント
- 【コピペで使える】人事評価の上司コメント例文集
- 部下の信頼を得て成長を後押しする!コメント作成5つの基本原則
- 絶対NG!部下のモチベーションを奪う上司コメント4つの特徴
- 【独自ノウハウ】評価業務を効率化し、質を高めるタレントマネジメントシステムの活用
- まとめ:的確な上司コメントは、部下と組織を育てる最強のツール
この記事を読めば、評価コメントの作成時間を大幅に短縮できるだけでなく、部下一人ひとりに寄り添ったフィードバックが可能になります。
結果として、部下からの信頼を高め、「良い上司」としてチームのパフォーマンスを最大限に引き出すことができるでしょう。
【コピペで使える】人事評価の上司コメント例文集

まずは、すぐに使える上司コメントの例文をまとめてご紹介します。
部下の状況や自社の評価シートに合わせて、最適な例文を見つけてください。
このセクションでは、以下の3つの視点で例文を整理しています。
- 評価段階別:ポジティブな評価か、改善を促す評価か
- 職種別:営業、事務、看護師など、具体的な職種ごとの例文
- 評価項目別:成果、能力、情意など、評価基準ごとのフレーズ
これらの例文は、少し修正するだけで現場で使える実践的なものばかりです。
ぜひあなたの言葉でアレンジして、活用してみてください。
評価段階別|良い点・改善点の伝え方と例文
部下のパフォーマンスレベルに応じて、コメントの伝え方を工夫することが重要です。
単に褒める、あるいは指摘するだけでなく、どのように伝えれば相手が前向きに受け止め、次の成長に繋げられるかを考えましょう。
ここでは、「ポジティブ評価」と「標準〜改善点がある場合」の2つのシナリオに分けて、具体的な例文とポイントを解説します。
【強みを伸ばす】ポジティブ評価のコメント例文
優れた成果を出した部下には、その事実を具体的に称賛し、さらなる活躍への期待を伝えることが大切です。
本人が自身の強みを客観的に認識し、自信を持って次のステージに進めるようなコメントを心がけましょう。
| 状況 | コメント例文 |
|---|---|
| 目標を大幅に達成した | 目標達成率120%という素晴らしい成果は、〇〇さんの粘り強い顧客訪問と的確な提案力の賜物です。特に新規開拓における行動量はチーム全体の手本となっており、今後のさらなる飛躍を期待しています。 |
| チームに大きく貢献した | 〇〇さんが主導した業務改善プロジェクトにより、チームの残業時間が月平均10時間削減されました。常に全体の効率を考え、主体的に行動する姿勢を高く評価します。 |
| 新しいスキルを習得した | 未経験だった動画編集スキルを自主的に学び、社内広報用の動画を完成させた行動力に感銘を受けました。新しい挑戦を恐れない姿勢は、今後のキャリアにおいて大きな武器になるでしょう。 |
【成長を促す】標準〜改善点がある場合のコメント例文
多くの管理職が最もコメントに悩むのが、このケースではないでしょうか。
重要なのは、できていない点の指摘だけでなく、まずできている点を認めた上で、具体的な改善策と期待をセットで伝えることです。
このような「サンドイッチ型」のフィードバックは、部下が指摘を素直に受け入れ、前向きな行動変容を起こす助けとなります。
| 状況 | コメント例文 |
|---|---|
| 成果は標準だが、プロセスに課題 | 目標達成に向けた真摯な取り組みは評価しています。一方で、タスクの優先順位付けに課題が見られ、締め切り間際に業務が集中する傾向があります。来期は週次での進捗確認会を通じて、計画的な業務遂行スキルを一緒に身につけていきましょう。 |
| 特定のスキルに改善が必要 | 顧客への丁寧な対応は素晴らしく、お客様からの評判も上々です。その上で、より提案の幅を広げるために、製品Bに関する知識を深めることを期待します。来月の製品研修への参加を推奨します。 |
| 勤務態度に少し懸念がある | 日々のルーティン業務を正確にこなしてくれる点には、いつも助けられています。ありがとうございます。一方で、会議での発言が少ない点が気になります。〇〇さんの視点は貴重ですので、来期はまず一度、意見を述べることを目標にしてみませんか。 |
【職種別】そのまま使える上司コメント例文18選
ここでは、より具体的に、職種ごとの特性を踏まえたコメント例文をご紹介します。
読者の皆様が担当する部下の職種は多岐にわたるため、幅広いケースを想定しました。
各職種で特に評価されるポイントに焦点を当てていますので、部下の顔を思い浮かべながらご覧ください。
営業職
営業職では、売上などの数値目標(定量評価)と、顧客との関係構築や行動プロセス(定性評価)の両面から評価することが重要です。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 目標達成度 | 上半期目標であった新規契約数10件に対し、15件という素晴らしい結果を残しました。特に、競合とのコンペでA社から大型契約を獲得できたのは、〇〇さんの粘り強い交渉と緻密な情報分析の成果です。 |
| プロセス・行動 | 安定して高い成果を出し続けているのは、日々の行動計画と徹底した顧客管理の賜物です。〇〇さんが作成しているアプローチリストは非常に質が高く、ぜひチーム全体で共有してほしいと思います。 |
| 改善点 | 既存顧客との関係構築力は高い評価に値します。今後はその強みを活かしつつ、新規顧客の開拓にもより一層力を入れることで、営業としての幅がさらに広がると期待しています。 |
事務職
事務職の貢献は、数字に表れにくい場合も多いため、業務の正確性や効率化への貢献、他部署との連携といった点を具体的に言語化することが大切です。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 正確性・迅速性 | 請求書処理において、この半年間ミスが一度もありませんでした。〇〇さんの正確かつ迅速な業務遂行能力のおかげで、部署全体の業務が非常にスムーズに進んでいます。 |
| 業務改善 | 従来のアナログなファイリング方法を見直し、クラウドストレージを活用した管理方法を提案・実行してくれました。これにより、資料検索時間が大幅に短縮され、部署全体の生産性向上に大きく貢献しました。 |
| 協調性・サポート | 常に周りに気を配り、多忙なメンバーの業務を率先して手伝う姿勢は、チームの潤滑油のような存在です。〇〇さんのサポートのおかげで、チームの雰囲気が非常に良くなりました。 |
看護師・介護士
医療・福祉の現場では、専門知識や技術はもちろん、患者・利用者への対応やチームでの連携が極めて重要になります。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 患者・利用者対応 | 常に患者様の立場に立った丁寧なケアを実践しており、ご家族からの信頼も厚いです。特に、認知症のA様に対して根気強くコミュニケーションを取り、笑顔を引き出していた場面は印象的でした。 |
| チーム連携 | 医師やリハビリスタッフとの情報共有を密に行い、常に最適なケアを提供しようとする姿勢は素晴らしいです。カンファレンスでの的確な報告は、チーム医療の質向上に不可欠なものとなっています。 |
| 改善点 | 高い専門知識を持っていますが、時にご自身の判断で業務を進めてしまう傾向が見られます。安全な医療・ケアを提供するためにも、必ずチームで報告・連絡・相談を徹底するようお願いします。 |
保育士
保育士の評価では、子どもたちの安全を守り、健やかな発達を支えるという基本に加え、保護者との信頼関係構築も重要なポイントです。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 園児への対応 | 一人ひとりの子どもの発達段階や個性を深く理解し、それぞれに合った声かけや関わり方ができています。〇〇先生のクラスの子どもたちが、のびのびと安心して過ごしている様子が何よりの証拠です。 |
| 保護者との連携 | 保護者への連絡ノートの記述が非常に丁寧で、日々の園での子どもの様子が目に浮かぶようだと好評です。懇談会での誠実な対応は、園と家庭との信頼関係構築に大きく貢献しています。 |
| 企画・実行力 | 運動会の企画では、子どもたちの自主性を引き出す新しいプログラムを提案・実行してくれました。準備段階から子どもたちを巻き込む工夫は、他の職員の参考にもなりました。 |
公務員
公務員の評価では、法令遵守や公正性といった基本姿勢に加え、住民サービス向上への貢献や、前例踏襲にとらわれない業務改善への意欲などが評価されます。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 住民対応 | 窓口業務において、常に丁寧で分かりやすい説明を心がけており、住民の方から感謝の声が届いています。複雑な手続きについても、相手の立場に立って根気強く対応する姿勢は、全体の模範です。 |
| 業務改善 | 〇〇申請手続きのオンライン化を提案し、関係各所との調整を粘り強く進めてくれました。これにより、住民の利便性向上と職員の業務効率化の両方を実現できた点は、高く評価します。 |
| 法令・知識 | 担当分野の関連法規について深い知識を有しており、法改正にも迅速に対応しています。他の職員からの問い合わせにも的確に回答しており、部署の知識レベル向上に貢献しています。 |
製造・技術職(エンジニア)
製造・技術職では、専門的なスキルや知識はもちろん、品質や生産性の向上、安全への意識、そしてチームでの協力体制が評価のポイントとなります。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 品質・生産性向上 | 製造ラインの工程を見直し、新たな治具を導入したことで、不良品率を5%改善し、生産性を10%向上させました。データに基づいた的確な分析と実行力を高く評価します。 |
| 技術力・問題解決 | 〇〇の不具合が発生した際、原因を迅速に特定し、再発防止策まで策定してくれました。その深い技術的知見と冷静な問題解決能力は、チームにとって不可欠です。 |
| チームワーク・指導 | 自身の技術や知識を惜しみなく後輩に伝え、チーム全体の技術力向上に貢献しています。〇〇さんの丁寧な指導のおかげで、若手メンバーの成長が著しいです。 |
【評価項目別】表現の幅が広がるコメントフレーズ集
自社の評価シートの項目に合わせて、表現のバリエーションを増やせるように、一般的な評価項目別のフレーズ集を用意しました。
これらのフレーズを組み合わせることで、より具体的で説得力のあるコメントが作成できます。
① 成果・業績評価(目標達成度)のフレーズ
結果だけでなく、そのプロセスや組織への貢献度も評価することが重要です。
| 評価の方向性 | フレーズ例 |
|---|---|
| 目標達成 | – 目標であった売上〇〇円を120%達成した点は、素晴らしい成果です。 – 〇〇という行動が、新規契約数〇件という結果に繋がりました。 – 常に高い成果を出し続けており、安定してチームの業績に貢献しています。 |
| 目標未達成 | – 目標には一歩届きませんでしたが、〇〇という新しい試みに挑戦した点は評価できます。 – 結果は伴いませんでしたが、目標達成に向けたプロセスには見るべきものがありました。 |
| 貢献度 | – 個人目標の達成のみならず、チーム全体の目標達成にも大きく貢献しました。 – 〇〇さんの上げた成果は、部署全体の士気を高める良い影響を与えました。 |
② 能力評価(スキル・専門性)のフレーズ
保有スキルが業務でどのように発揮され、成果に繋がったのかを具体的に示しましょう。
| スキルの種類 | フレーズ例 |
|---|---|
| 企画・立案力 | – 課題の本質を捉えた的確な企画を立案し、プロジェクトを成功に導きました。 – 斬新な視点からの提案は、議論を活性化させるきっかけとなりました。 |
| 実行・遂行力 | – 計画を着実に実行に移し、困難な状況でも最後までやり遂げる責任感があります。 – 関係各所との調整を粘り強く行い、計画を円滑に推進しました。 |
| 専門知識 | – 〇〇分野に関する深い専門知識は、部署内でも随一です。 – 新しい技術の習得に意欲的で、その知識をチームに還元してくれています。 |
③ 情意評価(勤務態度・意欲)のフレーズ
主観的になりがちな項目だからこそ、具体的な行動事実に基づいて評価することが納得感を高める鍵です。
| 評価項目 | フレーズ例 |
|---|---|
| 積極性 | – 常に現状に満足せず、より良い方法を模索する姿勢が見られます。 – 誰も手を挙げたがらない業務にも、自ら率先して取り組んでくれました。 |
| 協調性 | – チームの目標達成のために、自分の役割を理解し、他メンバーと効果的に連携しています。 – 意見が対立する場面でも、冷静に双方の意見を聞き、合意形成に努めていました。 |
| 責任感 | – 自身の担当業務に対して強い責任感を持ち、最後までやり遂げる姿勢は高く評価できます。 – ミスが発生した際も、隠さず迅速に報告し、誠実に対応していました。 |
部下の信頼を得て成長を後押しする!コメント作成5つの基本原則

優れた例文を知ることも大切ですが、応用力を身につけるためには、コメント作成の根底にある「考え方」を理解することが不可欠です。
ここでは、部下のモチベーションを高め、上司としての信頼を得るための5つの基本原則を解説します。
これらの原則を意識すれば、あなたのコメントは単なる評価ではなく、部下の成長を力強く後押しするメッセージへと変わるはずです。
原則1:具体的・客観的な事実(行動・数字)を元に書く
評価コメントで最も重要なのは、「具体性」と「客観性」です。
なぜなら、根拠が曖昧な評価は部下の納得を得られず、不信感に繋がるからです。
日頃の行動や成果を、具体的なエピソードや数値を交えて記述しましょう。
| 比較 | コメント例 |
|---|---|
| 悪い例(抽象的) | 今期もよく頑張ってくれた。積極性もあって素晴らしい。 |
| 良い例(具体的) | 担当したA案件で、自ら追加提案を行い、結果として前年比150%の売上を達成した点は高く評価します。 |
原則2:未来志向で、次のアクションに繋げる
人事評価は、過去の成績を裁く場ではありません。
その目的は、評価を通じて部下の未来の成長を促すことにあります。
コメントの最後は、必ず次期の目標や期待する行動を示す、前向きな言葉で締めくくりましょう。
「今回の成果を活かして、来期はリーダーとして後輩指導にも挑戦してほしい」のように、具体的な期待を伝えることが重要です。[^3]
原則3:強みと改善点をバランス良く伝える
良い点だけではお説教になり、悪い点だけでは部下を追い詰めてしまいます。
部下がフィードバックを素直に受け入れるためには、強みと改善点の両方をバランス良く伝えることが効果的です。
特に改善点を伝える際は、まずポジティブな点を認めてから本題に入る「ポジティブ・サンドイッチ」の手法が有効です。
これにより、部下は心理的な抵抗なく、自身の課題と向き合うことができます。
原則4:部下の自己評価を尊重し、ギャップを埋める
評価は上司からの一方的な押し付けであってはなりません。
コメントを作成する前に、必ず部下が提出した自己評価に目を通しましょう。
もし、上司の評価と部下の自己評価にギャE.T.ップがある場合は、その差がどこから生まれているのかを考え、面談での対話を通じてすり合わせる準備が必要です。
「自分ではこう評価しているが、あなたはどう思う?」と問いかける姿勢が、部下の納得感を引き出します。
原則5:普段からの1on1や記録が質の高いコメントを生む
質の高い評価コメントは、一朝一夕には書けません。
評価期間の終わりに慌てて思い出そうとしても、直近の出来事ばかりが印象に残ってしまう「期末効果」に陥りがちです。
日頃から1on1ミーティングなどで部下と対話し、気になった行動や成果をメモしておく習慣が、最終的に客観的で説得力のあるコメント作成に繋がります。
絶対NG!部下のモチベーションを奪う上司コメント4つの特徴

良かれと思って書いたコメントが、実は部下のやる気を削いでいるとしたら、それは非常にもったいないことです。
ここでは、管理職が陥りがちな、絶対に避けるべきNGコメントの4つの特徴を解説します。
無意識のうちに部下を傷つけ、信頼関係を損なわないためにも、ぜひチェックしてください。
| NGな特徴 | 具体的なNG例文 | なぜNGか? |
|---|---|---|
| 人格・性格の否定 | 「君は慎重な性格だから、決断が遅い」 | 変えられない人格を指摘されると、部下は改善のしようがなく、自己否定に陥ってしまう。評価すべきは「行動」。 |
| 他者との比較 | 「同期の〇〇君は、もう新規契約を5件も取っているぞ」 | 他者比較は、不公平感や劣等感を生むだけ。評価はあくまで本人の過去との成長度で測るべき。 |
| 根拠のない主観 | 「なんとなく、今回の成果には物足りなさを感じる」 | 具体的な事実に基づかないコメントは、部下にとって「上司の好き嫌い」としか受け取れず、不信感に繋がる。 |
| 曖昧な指示 | 「もっと主体性を発揮してほしい」 | どうすれば「主体的」と評価されるのかが分からず、部下は次の行動に移せない。 |
1. 人格や性格を否定するコメント
「〇〇さんは心配性だから、行動が遅い」
「もう少し明るい性格だったら、チームも活性化するのに」
これらは、評価ではなく人格攻撃です。
評価の対象は、あくまでも客観的に観察できる「行動」と、その「結果」でなければなりません。
2. 他の社員と比較するコメント
「同期のAさんはもうリーダーを任されているのに、君は…」
このような他者との比較は、部下の間に無用な競争心や劣等感を生み出し、チームワークを阻害します。
比較対象は、常に「過去の本人」あるいは「設定した目標」であるべきです。
3. 根拠のない主観的なコメント
「君には期待しているんだけど、どうも物足りないんだよな」
具体的な事実に基づかない、上司の「印象」や「感覚」で語られたコメントは、部下を混乱させるだけです。
なぜそう感じるのか、具体的なエピソードやデータを添えて説明できなければ、それは単なる個人的な感想に過ぎません。
4. 曖昧で、どうすれば良いか分からないコメント
「来期はもっとリーダーシップを発揮してほしい」
このコメントを受け取った部下は、「具体的に何をすれば良いのか」が分からず、行動に移せません。
「来期は、週次の定例ミーティングで進行役を務めることから始めてみよう」のように、次のアクションに繋がる具体的な指示や提案をすることが不可欠です。
【独自ノウハウ】評価業務を効率化し、質を高めるタレントマネジメントシステムの活用

毎年繰り返される人事評価。
そのコメント作成に多くの時間を費やし、精神的な負担を感じている方も多いのではないでしょうか。
その悩みを根本的に解決する手段として、近年注目されているのが「タレントマネジメントシステム」の活用です。
ここでは、評価業務を効率化し、かつコメントの質をも高めるシステムの可能性について、具体的な事例を交えて解説します。
なぜ今、人事評価にシステム活用が求められるのか?
人事評価システムの導入は、単なる業務効率化に留まらない多くのメリットをもたらします。
- 評価の客観性・公平性の担保:日々の実績や行動データを自動で蓄積し、客観的な根拠に基づいた評価が可能になる。
- 業務負担の軽減:評価シートの配布・回収・集計といった作業が自動化され、管理者はより本質的な業務に集中できる。
- 評価と育成の連動:評価結果と研修履歴などを一元管理し、個々の課題に合わせた育成プランを立てやすくなる。
- 評価プロセスの透明化:誰がいつ何を評価したのかが可視化され、従業員の評価制度に対する納得感が高まる。
事例:飲食店向けシステム「ニュートン」に学ぶ、データに基づく評価と育成
ここでは、より具体的なイメージを持っていただくために、当サイトの関連サービスである飲食店向けタレントマネジメントシステム「ニュートン」の事例をご紹介します。
飲食業界特有の課題解決ノウハウが詰まっていますが、その考え方は多くの職場で応用可能です。
強み①:客観データで評価の公平性と納得感を高める
「ニュートン」は、従業員のスキルレベルや勤務態度、実績などのデータを日々収集・蓄積します。
これにより、上司は「〇〇さんは今月、接客スキル評価項目で平均点を5点上回った」といった客観的な事実に基づいてコメントを作成できます。
上司の主観や記憶だけに頼らない評価は、従業員の納得感を飛躍的に高めます。
強み②:教育と評価の連動で、個人の成長を自動でサポート
「ニュートン」の大きな特徴は、評価と教育がシステム上で連動している点です。
例えば、評価面談で「新メニューの提案力が課題」という結果が出た場合、システムが自動で関連する調理マニュアルや提案方法の研修動画を本人に提示します。
これにより、評価が「やりっぱなし」にならず、具体的な成長アクションへとスムーズに繋がるのです。
強み③:評価業務40%削減で、部下との対話時間を創出
「ニュートン」を導入した企業では、評価業務にかかる時間が平均で40%削減されたというデータがあります。
評価シートの作成や集計といった作業から解放されることで、管理者は本来最も時間をかけるべき「部下との1on1ミーティング」などの対話に時間を使えるようになります。
システムはあくまでツールであり、それによって生まれた時間を、人と人とのコミュニケーションに投資することが、最終的にチームの成長を加速させます。
まとめ:的確な上司コメントは、部下と組織を育てる最強のツール

この記事では、人事評価における上司コメントの具体的な例文から、部下の成長を促すための基本原則、そして避けるべきNG例まで、幅広く解説しました。
改めて、重要なポイントを振り返ります。
- 具体的・客観的な事実に基づいて書く
- 未来志向で、次のアクションに繋げる
- 強みと改善点をバランス良く伝える
- 人格否定や他者比較は絶対にしない
人事評価のコメント作成は、決して簡単な仕事ではありません。
しかし、それは同時に、部下のキャリアに深く関わり、その成長を直接支援できる、非常にやりがいのある役割でもあります。
今回ご紹介した例文やポイントが、あなたの評価業務の負担を少しでも軽くし、部下とのより良い関係を築く一助となれば幸いです。
的確なフィードバックは、部下一人ひとりを、そしてチーム全体を力強く育てる最強のツールなのです。
人事評価を効率的に進めるなら「ニュートン」

人事評価のコメントは、従業員の成長やモチベーションアップにつながるように書くことが重要です。
人事評価コメントの根拠となる社員のスキルや経歴、評価実績や目標に対する進捗などのデータは【システム化】することで、人材育成の戦略人事に効率よく展開できるでしょう。納得度の高い人事評価制度により組織の成長に繋がる人材育成を目指したいなら、タレントマネジメントや人材育成に特化した特許取得済のツール「ニュートン」がおすすめです。
工数のかかる「人事評価」業務を「人事評価ツールNewton(ニュートン)」でシンプルに効率化してみてはいかがでしょうか。
この記事を書いたライター

Newton編集部
飲食店の人事に役立つ情報を発信していきます。人材から人材へ、人が育つ人事評価システムNewtonとは、飲食店に特化したタレントマネジメント+人事評価システムです。
管理者の人事管理のパフォーマンスを上げるだけでなく、スタッフのモチベーションアップや、離職率の低下、企業にとっての人材を守るシステムです。詳しくはこちら