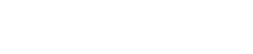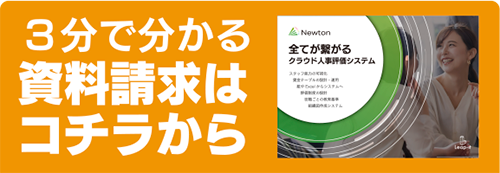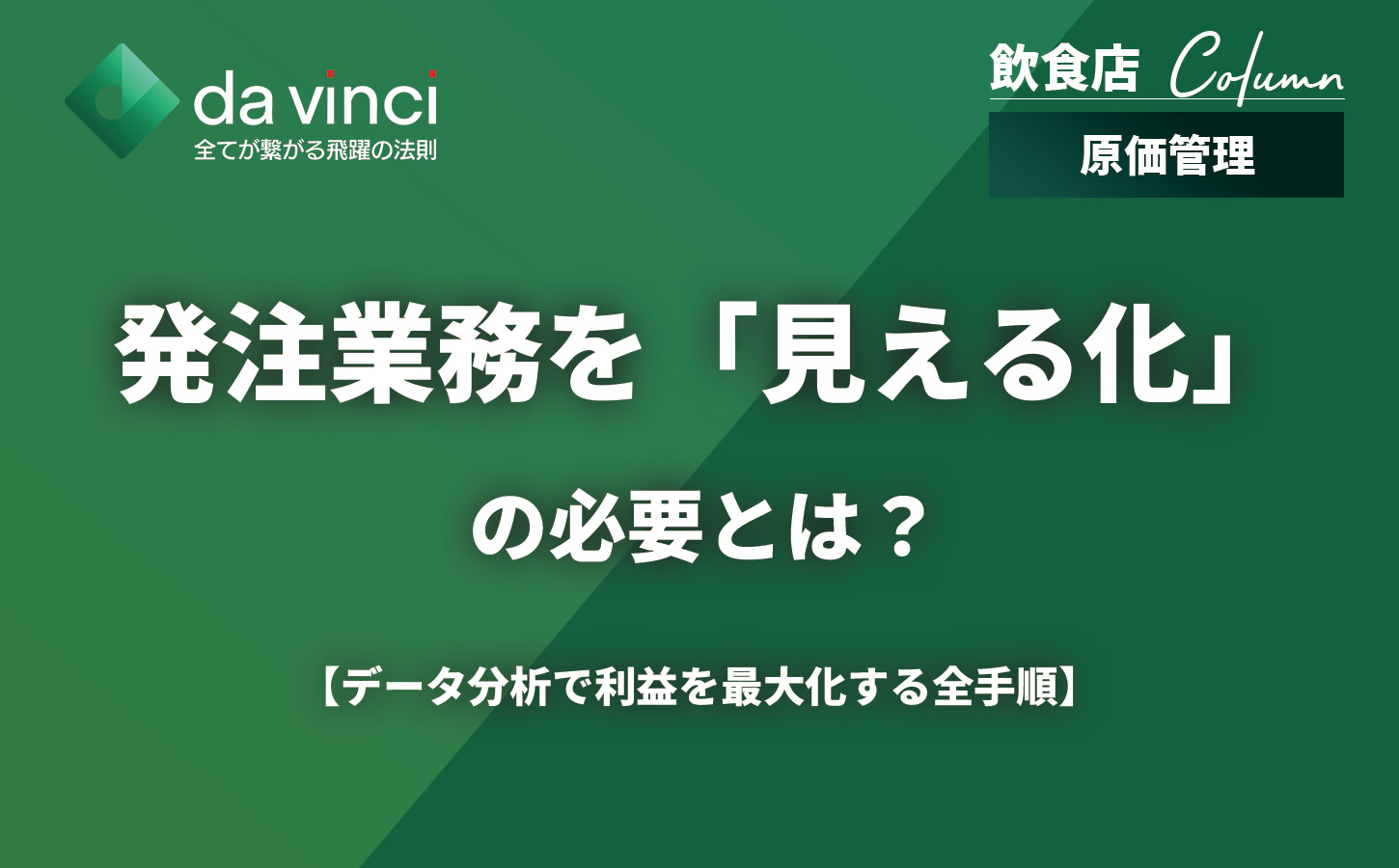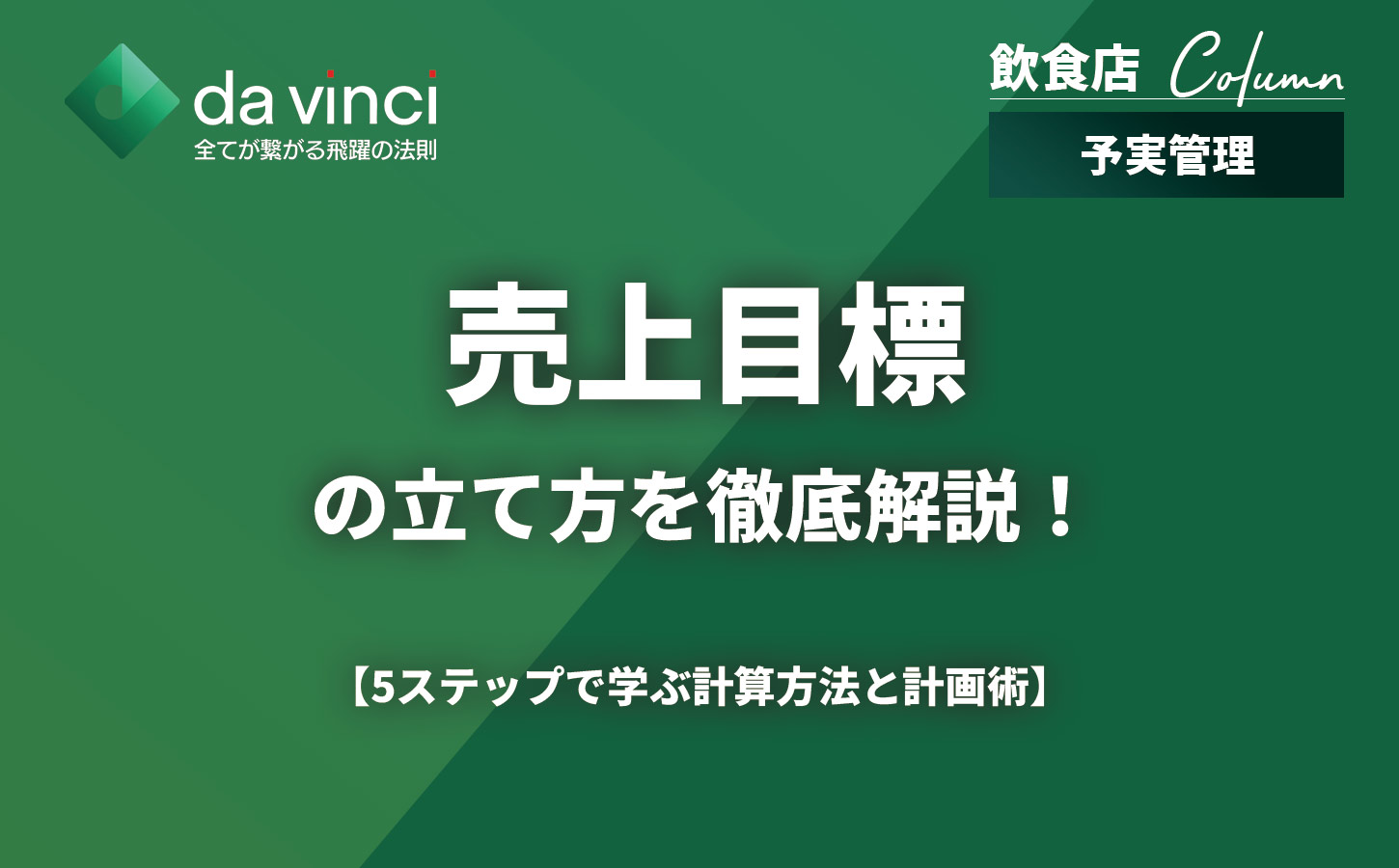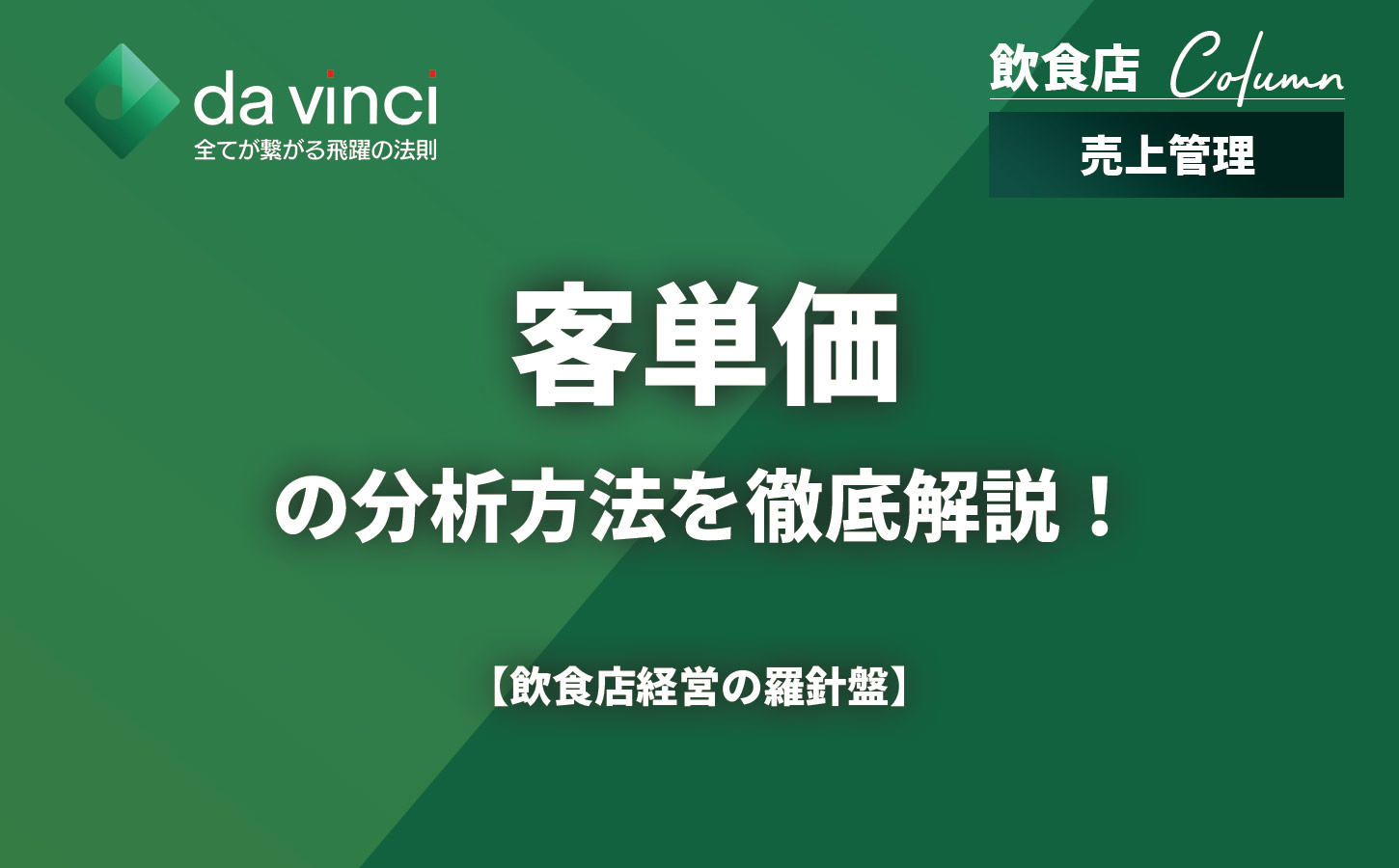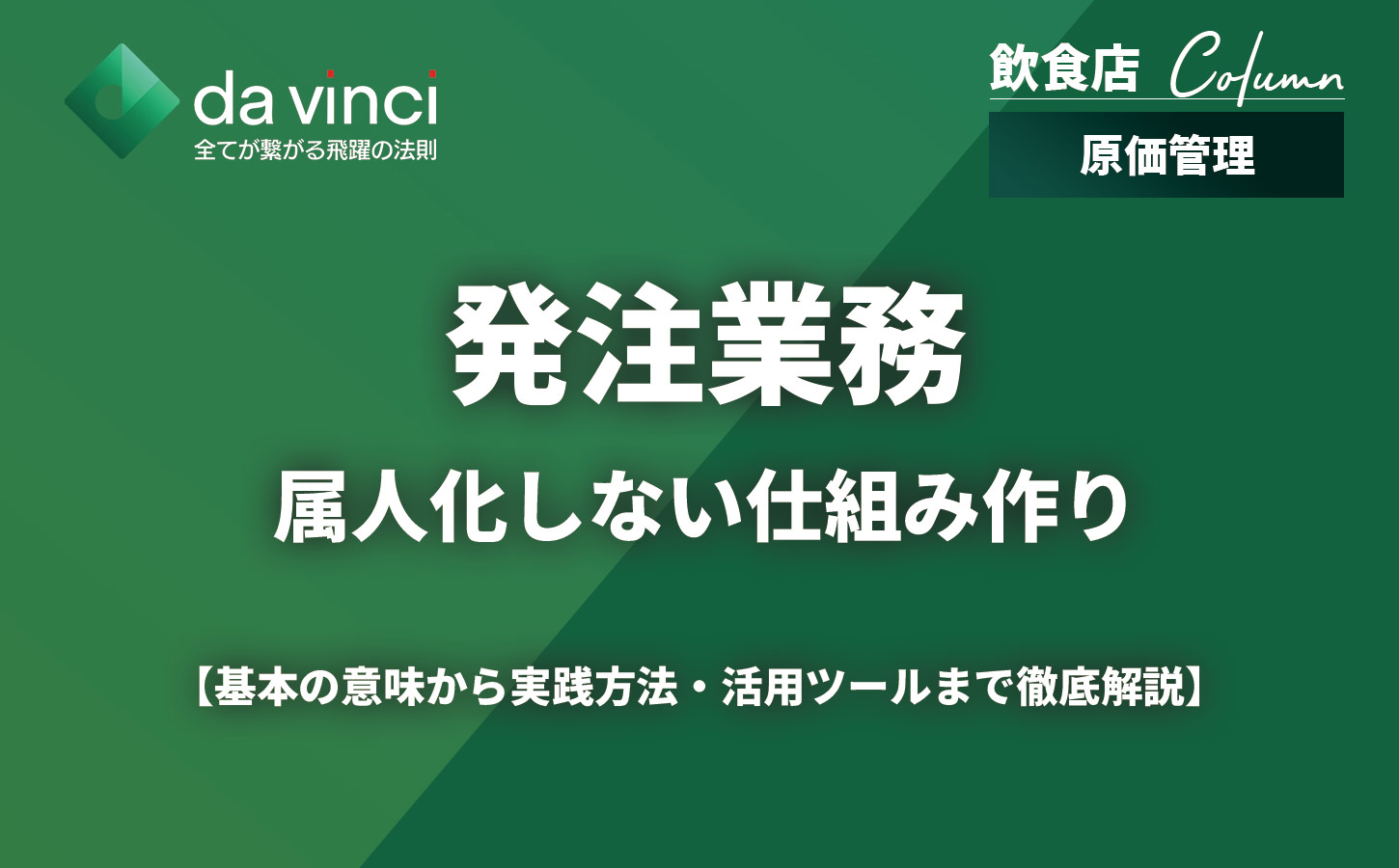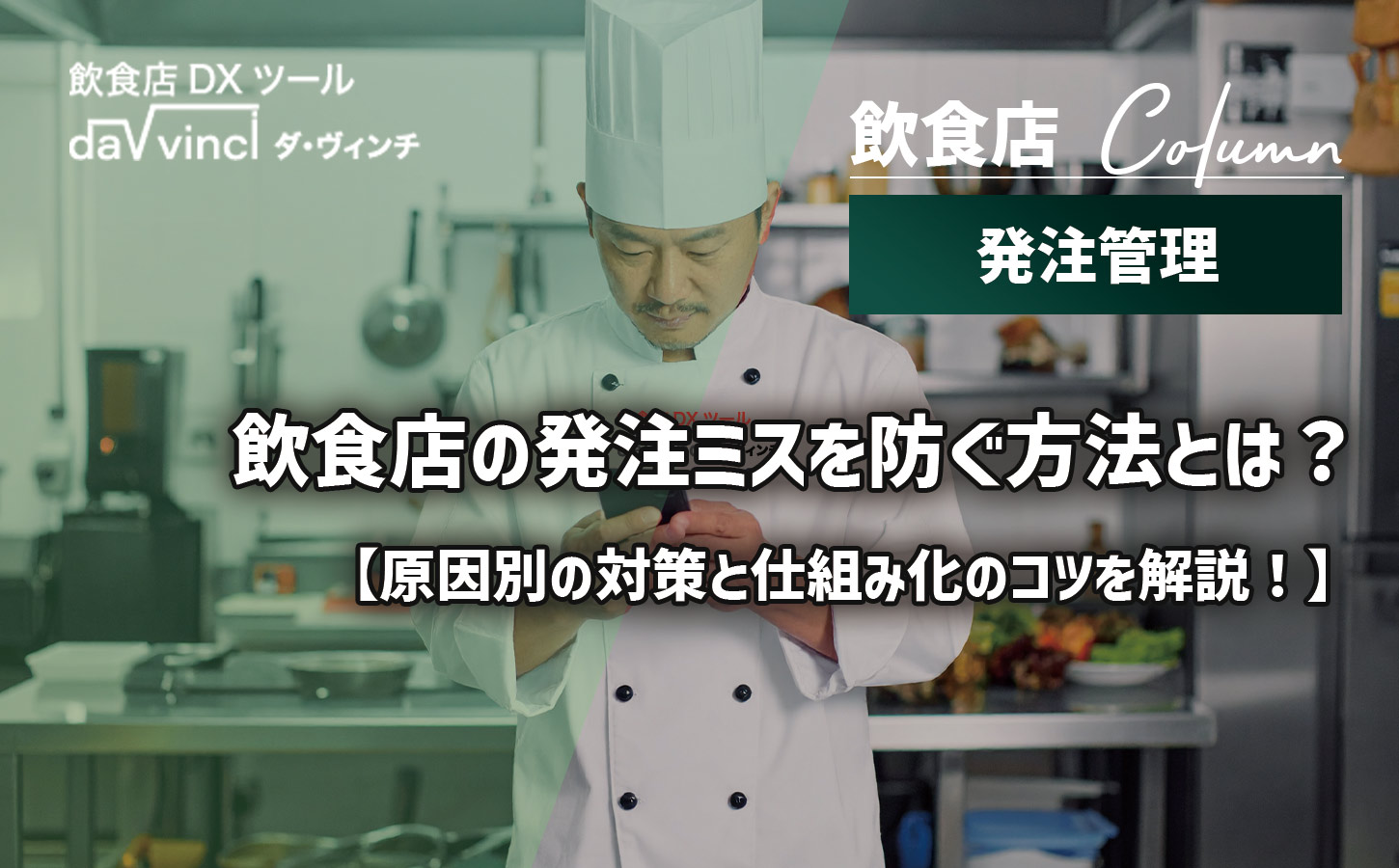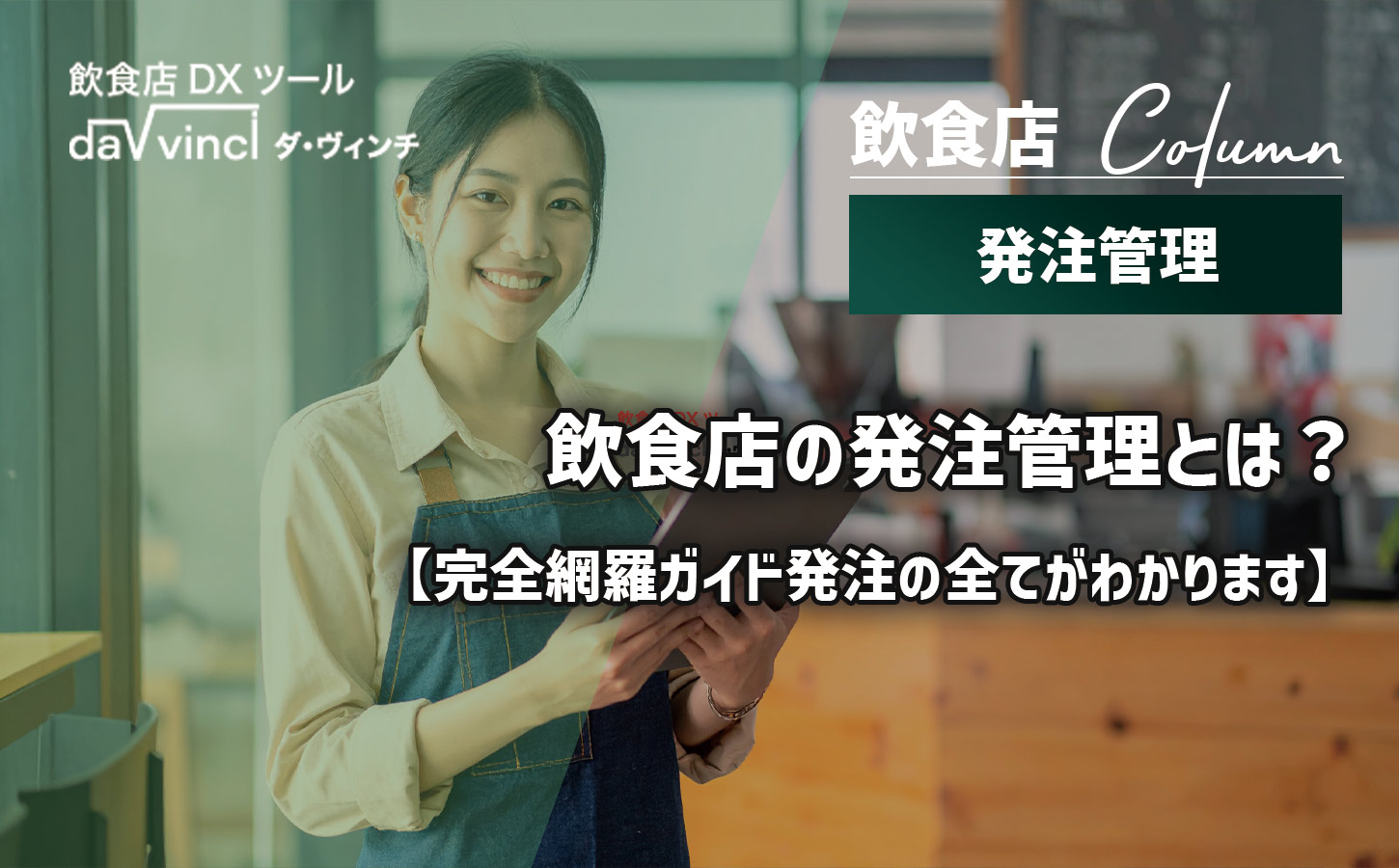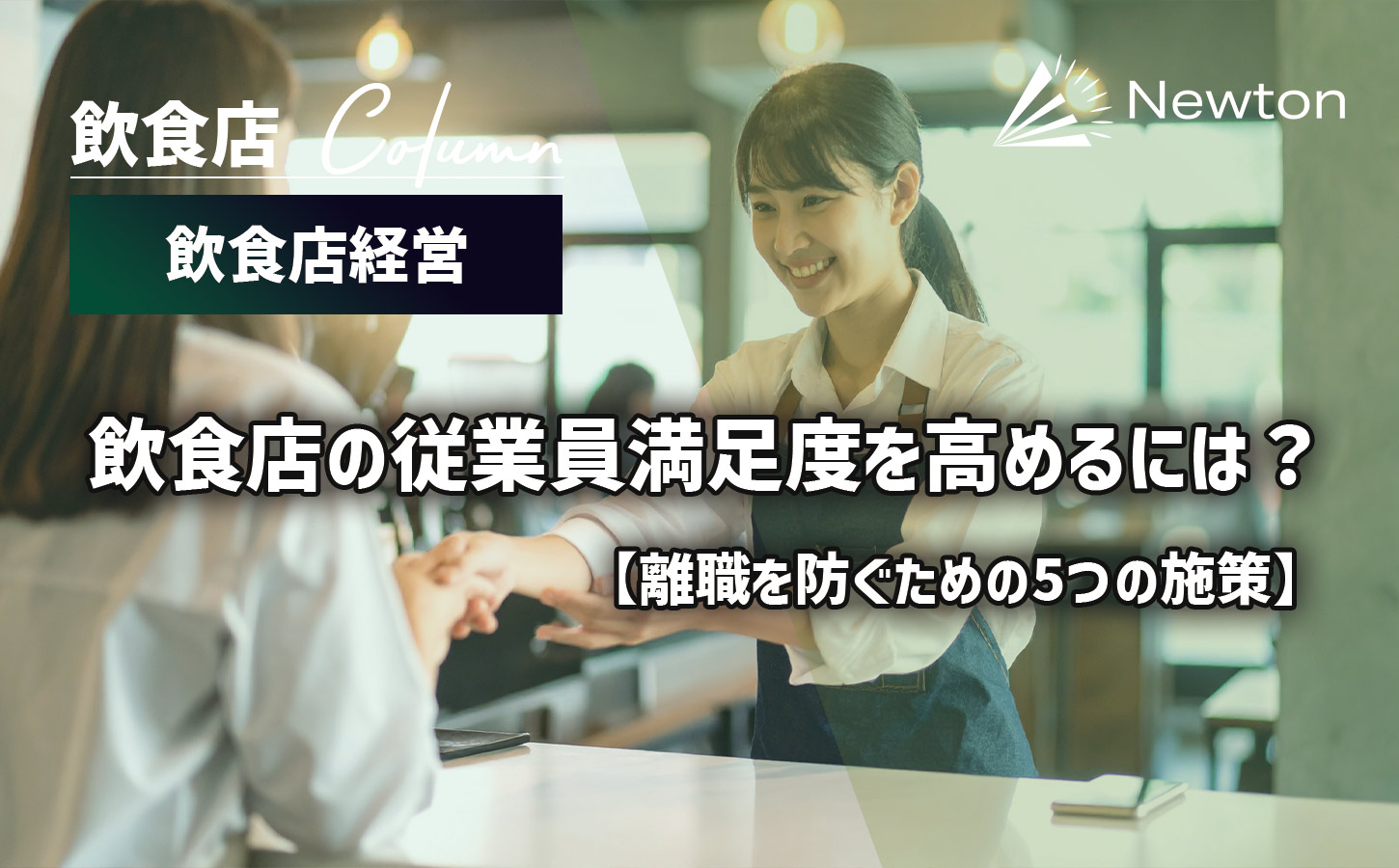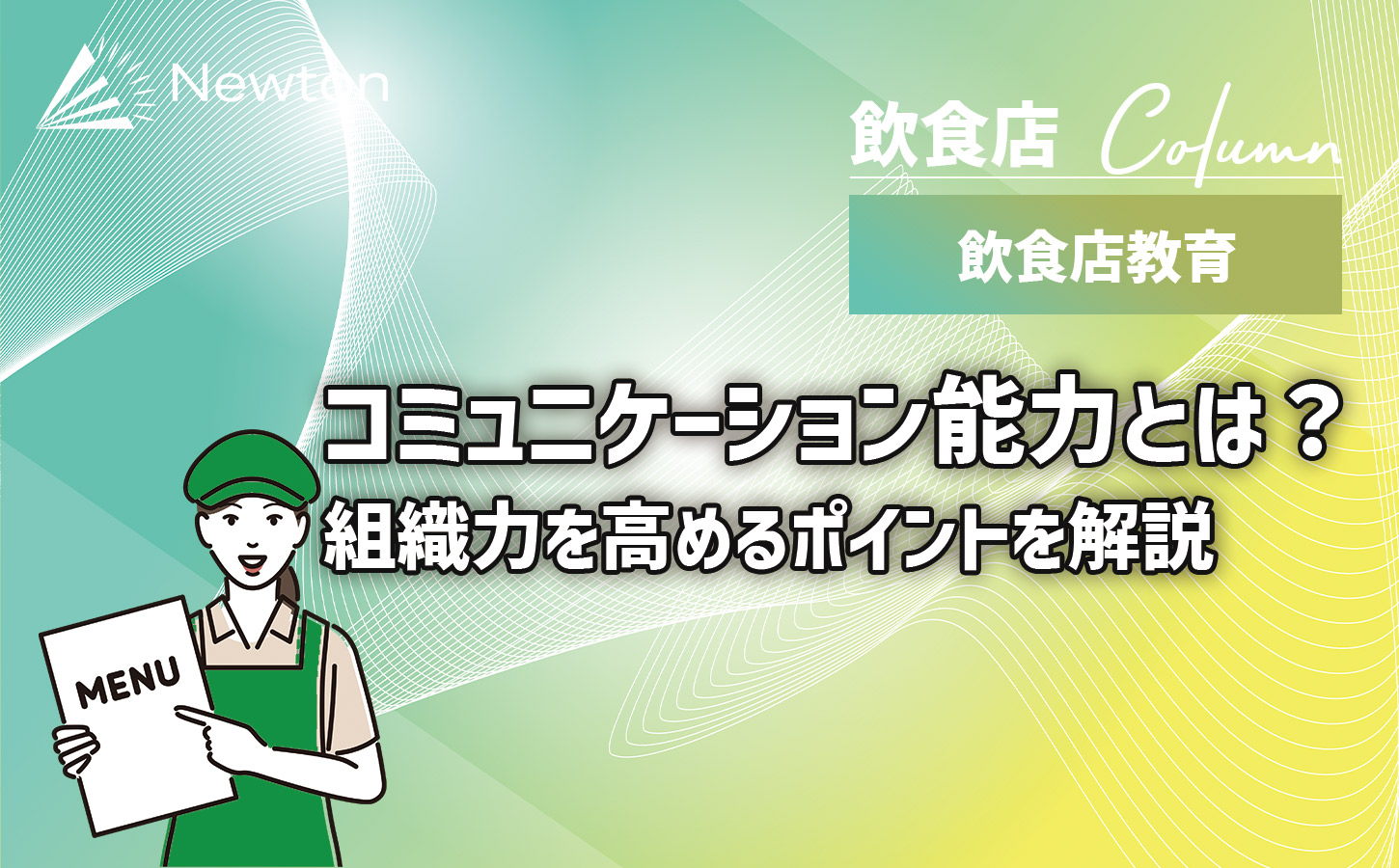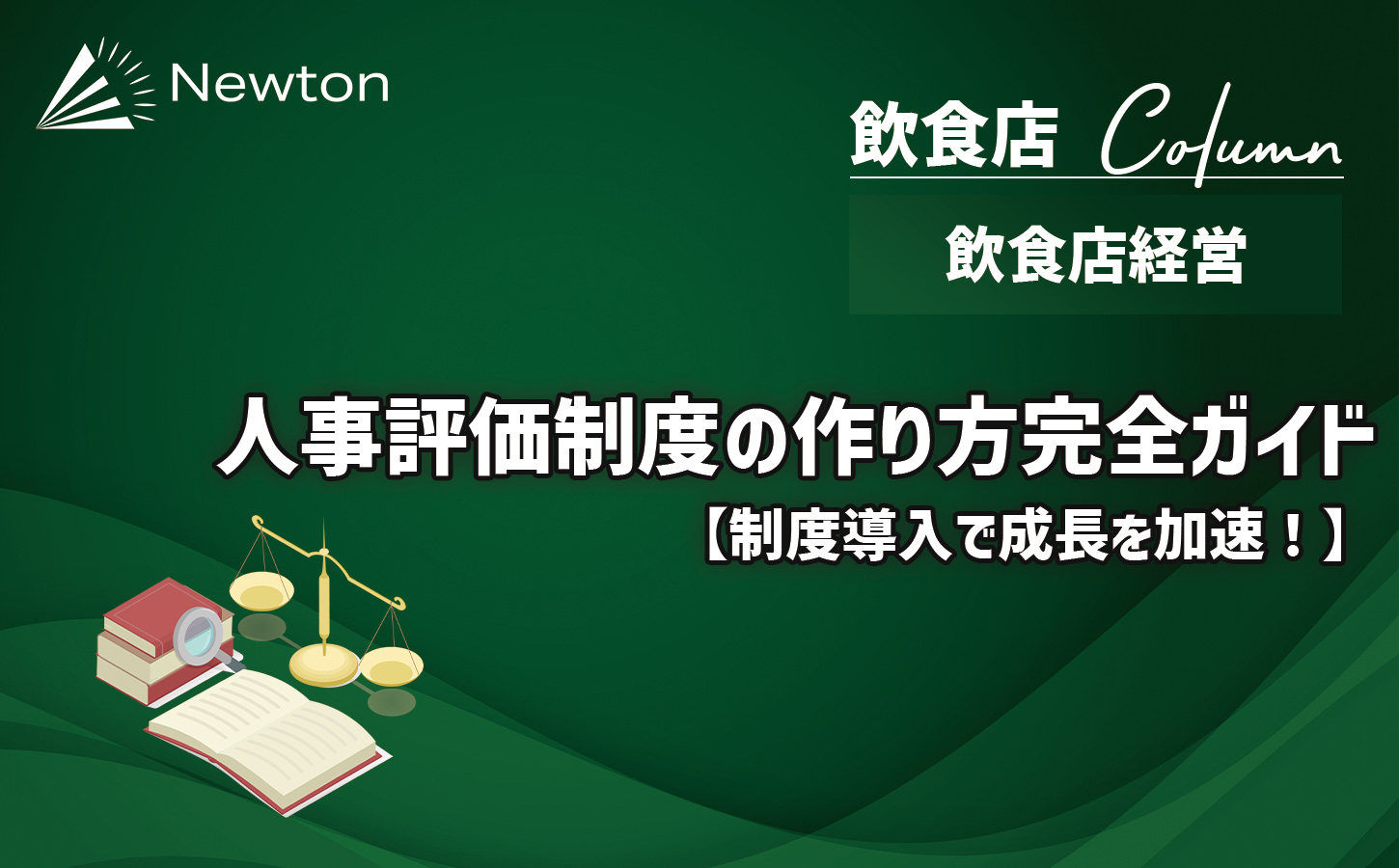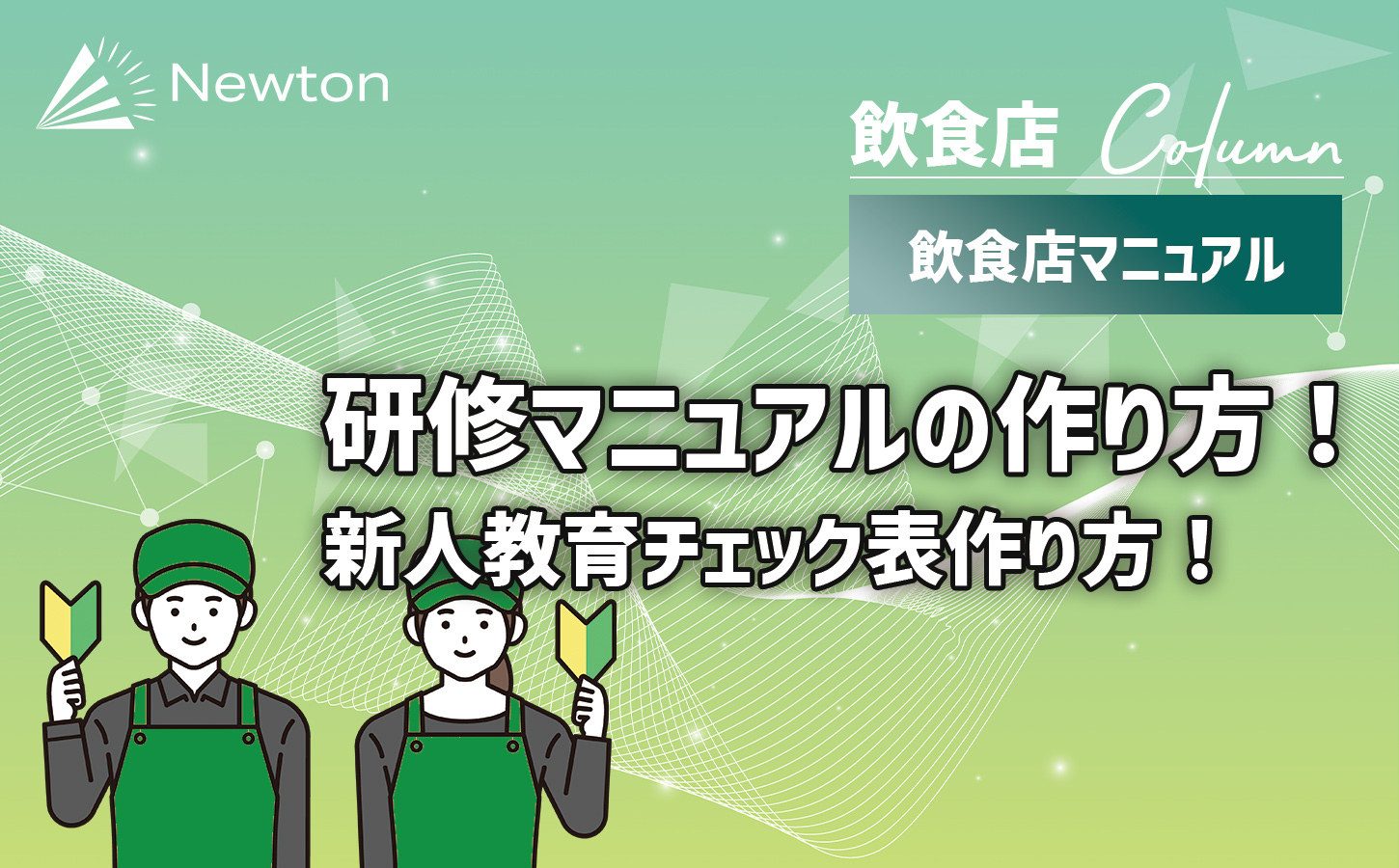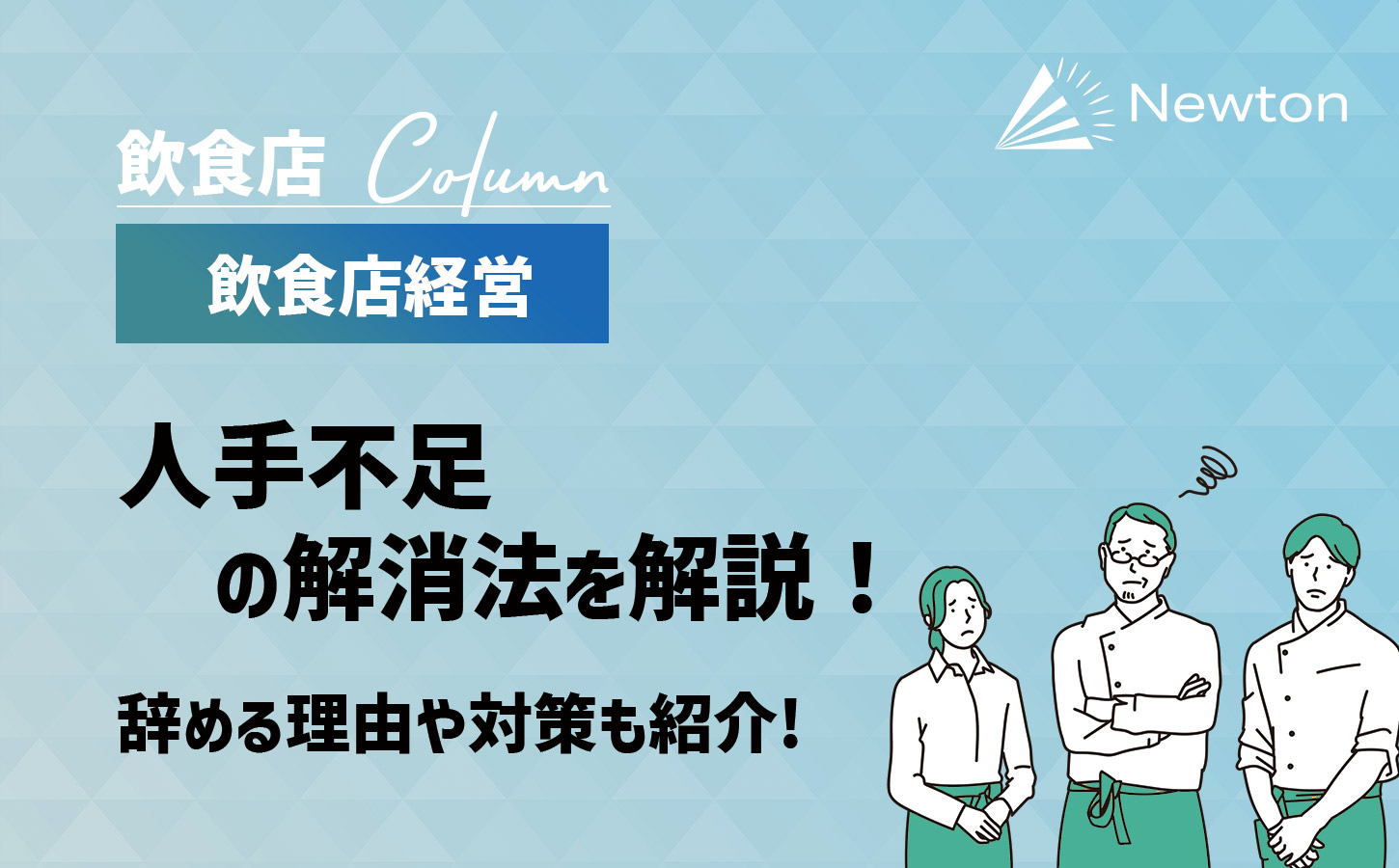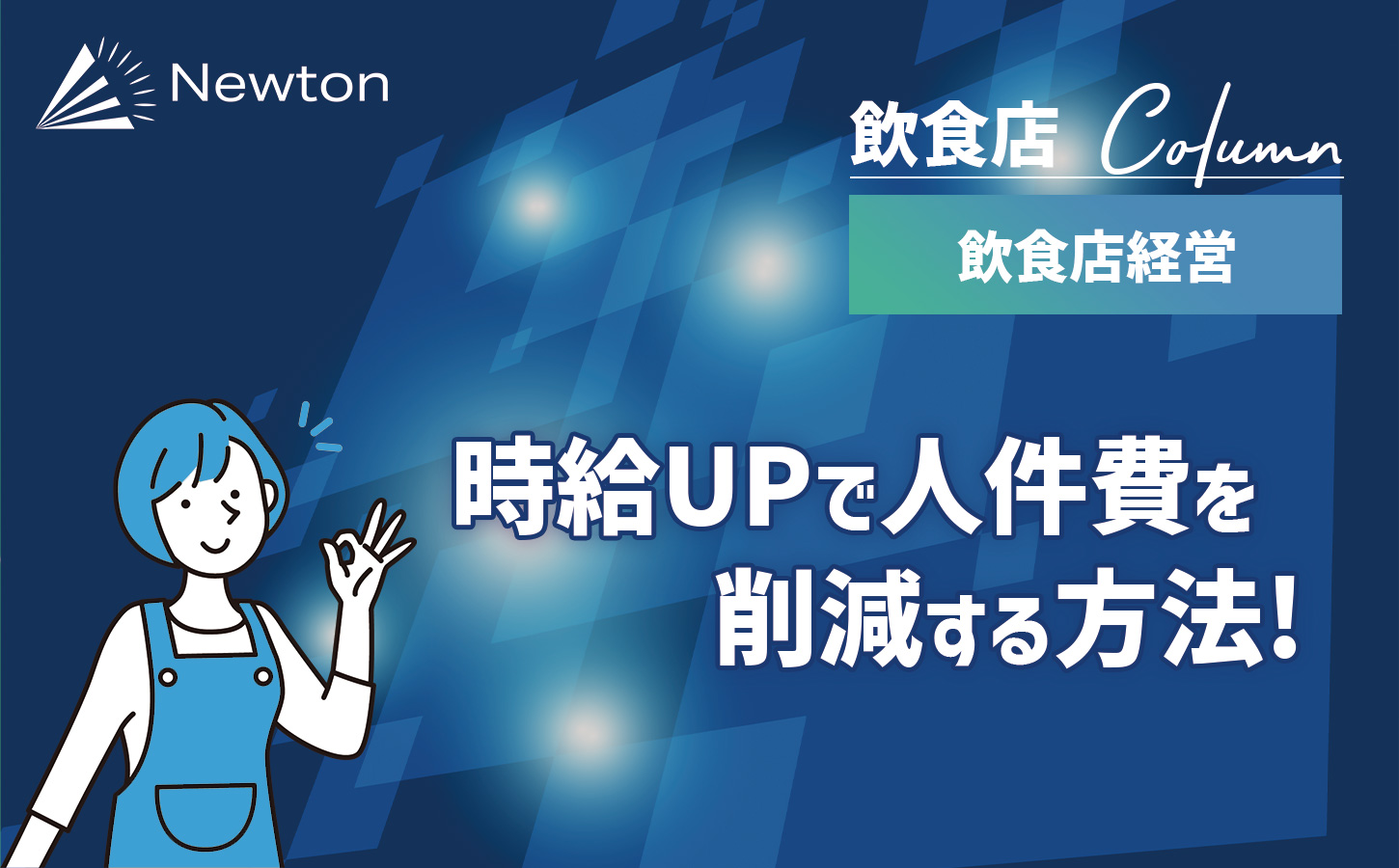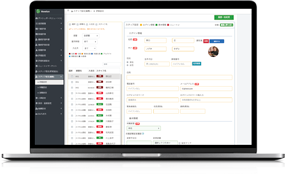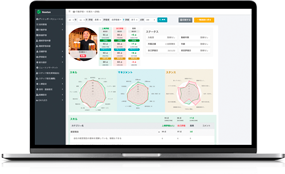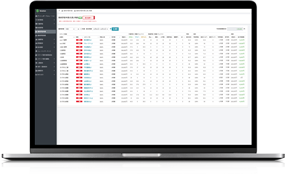飲食店の人事評価の導入うまくいかない理由とは?現場の悩みに寄り添う導入ポイント
2025/07/23
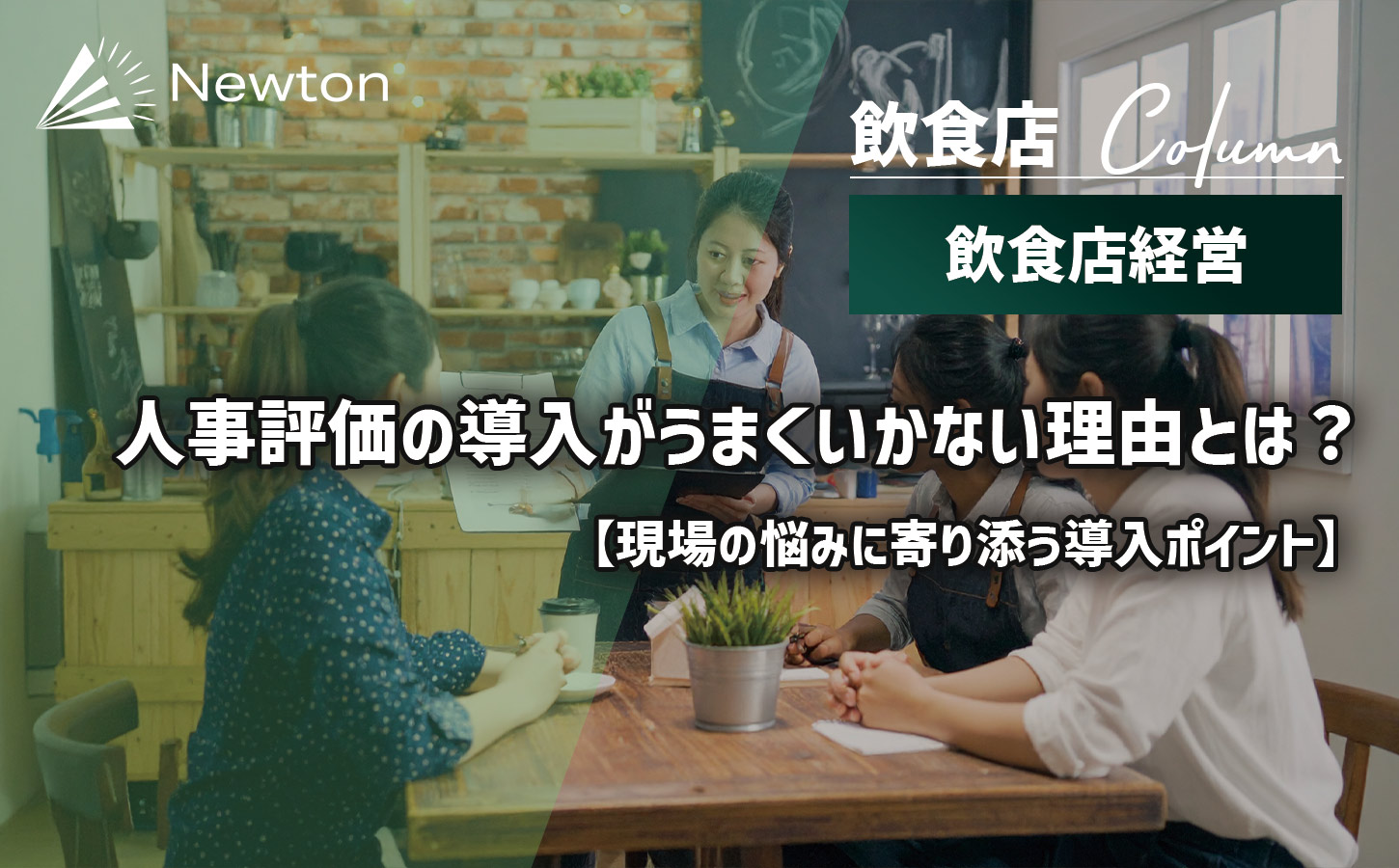
飲食業界では、スタッフの定着率の低さや人材の育成が長年の課題となっています。
現場任せのマネジメントや属人的な指導では限界があり、「公平に評価し、成長を支える仕組み」が求められるようになっています。
こうした背景から、人事評価制度を導入する飲食店が増えてきました。しかし実際には、制度を導入しても現場でうまく機能せず、途中で形骸化してしまうケースも少なくありません。
本記事では、
- 飲食店における人事評価制度がなぜうまくいかないのか
- “5つの失敗理由”を現場目線で掘り下げ
- どうすれば評価制度を継続・定着できるのか
- 具体的な改善策まで解説します
店舗運営に悩む経営者・マネージャーの方にこそ読んでいただきたい内容です。
飲食店で評価制度が求められる背景

業界特有の課題が評価制度の必要性を高めている
飲食業界は、慢性的な人手不足や従業員の定着率の低さに悩まされ続けています。現場では社員とアルバイトが入り混じり、個々のスキルや責任範囲にバラつきがある中で、育成やマネジメントが属人的になりやすいという課題を抱えています。
また、指導や評価が現場の店長やリーダーの「感覚」に依存してしまい、「なぜあの人が評価されるのか分からない」といった不透明さがスタッフの不満に直結してしまうケースも少なくありません。
若手・アルバイトのモチベーション管理が難しい
特に問題となるのは、若手やアルバイト層のモチベーション管理です。
-
正社員と違い、昇進や責任による差が出にくい
-
評価される実感が薄く、やりがいを見出しにくい
-
教育が不十分なまま戦力扱いされ、離職に繋がる
こうした背景から、誰が見ても公平で、努力や成長がきちんと報われる評価制度が必要とされています。
「見える評価」が定着と戦力化を支える
評価の内容が明確に可視化されていれば、「何を頑張ればいいのか」がスタッフ自身にも伝わりやすく、定着とスキル向上の両面に効果を発揮します。
経営層にとっての評価制度=処遇の根拠
一方、経営層にとっては、評価制度は処遇や昇給の根拠としての役割も期待されています。属人的な判断ではなく、データや基準に基づいた評価を行うことで、納得感あるマネジメントが可能になり、人件費の最適化や組織力の底上げにもつながっていきます。
評価制度がうまくいかない5つの理由と改善策

人事評価制度は、導入するだけでは意味がありません。現場に根付かず、期待した効果が出ないまま終わってしまう店舗も多く見られます。ここでは、飲食店で制度がうまく運用されない代表的な5つの理由と、それぞれに対応する改善策を紹介します。
❶ オープンから働くパートさんの反発
制度導入時、最初に反発が起こりやすいのが「長年店を支えてきたベテランパートスタッフ」です。
「今さら評価されるの?」「これまでの貢献は見てもらえないの?」という不満の声は、制度の新しさとこれまでの関係性との“ズレ”から生まれます。特にオープニングスタッフのような立場の人にとっては、急に評価基準を設けられることが、自身のプライドを傷つける結果にもなりかねません。
改善策
-
制度導入の目的を丁寧に共有し、「過去の貢献も含めた評価」であることを明示
-
初期は「査定」ではなく「対話重視」の面談形式で導入
-
評価制度の構築段階から、ベテランスタッフの声を反映する
制度は“人を選ぶ”ためではなく、“人を認める”ための仕組みであることをしっかり伝えることが重要です。
❷ 評価制度の使い方がわからない社員
制度を導入しても、「どう使えばいいのかわからない」という戸惑いが現場に残ります。特に店長やリーダー層は、「評価する側」としての教育を受けておらず、評価表の読み方や使い方が曖昧なまま運用が始まるケースが大半です。
よくある課題には以下のようなものがあります。
| よくある課題 | 内容 |
|---|---|
| 評価項目が抽象的 | 「協調性」「積極性」などが曖昧で判断しにくい |
| 作業が煩雑 | 手書きや表計算ソフトでの運用に時間がかかる |
| 判断に自信がない | 店長自身が“評価者として育っていない” |
改善策
-
評価基準の明確化と運用マニュアルの整備
-
誰でも扱いやすい評価ツールの導入
-
店長・リーダー向けの運用研修とフォローアップ支援
「使える制度」にすることで、評価が業務の一部として自然に馴染んでいきます。
❸ 導入したものの、継続できず断念
評価制度は、導入後に形骸化しやすいのも大きな課題です。とくに紙やExcelでの管理は工数がかかり、評価そのものが後回しになりがちです。また、店長が異動・退職したタイミングで、制度そのものが消滅してしまうケースもあります。
継続できない要因
-
毎月の記入や集計が煩雑で、忙しい現場には不向き
-
制度の成果が見えにくく、続ける意義が感じられない
-
店舗ごとに運用がバラバラになり、標準化できない
改善策
-
最初から完璧な制度を目指さず、運用しやすい範囲からスタート
-
評価の頻度を「四半期に1回」などに設定し、回数を減らす
-
クラウド型の評価ツールで、属人化を防ぎつつ継続可能にする
「継続できる仕組み」こそが、制度成功の鍵です。
❹ 「従業員のための制度」として伝えられていない
評価制度が浸透しない最大の理由は、制度の目的が現場に伝わっていないことです。多くのスタッフは「評価される=査定・監視される」と捉えがちで、制度がネガティブに受け取られる傾向があります。
上司が評価を一方的に行い、結果だけが通達される場合、スタッフは「不公平」「納得できない」と感じやすくなります。
改善策
-
評価制度を「育成のための道具」として明確に説明する
-
評価結果を伝える際は、必ずフィードバック面談を行う
-
昇給や表彰、インセンティブ制度と連動させて、“結果が返ってくる”設計にする
制度が「従業員のためにある」ことを伝え、納得感を得られるように運用することが肝心です。
❺ 評価がマニュアルや給与に反映されていない
制度を整えても、評価結果が処遇に反映されないままでは、スタッフのやる気は続きません。「評価はするけど、昇給には関係ない」というような状態では、形だけの制度になってしまいます。
また、評価項目と業務マニュアルや育成基準が連動していないと、何をどう改善すれば良いのかが本人にもわからず、成長支援としても機能しません。
改善策
-
評価内容を処遇・マニュアル・教育体制と連動させる
-
昇給・昇格の仕組みを設計し、制度としてスタッフに説明
-
役割等級やロール設定と紐づけ、キャリアステップを明示
評価→処遇→育成のサイクルが機能すれば、制度はただの査定ではなく、「働く価値」を見える化する仕組みになります。
このように、評価制度がうまくいかない理由には、現場の心理・業務の負荷・制度設計の不備など、複合的な要因があります。重要なのは、それぞれの課題に対して適切な改善策を講じ、“運用できる制度”として現場に根付かせることです。
評価制度を成功に導く3つのポイント

人事評価制度は導入することが目的ではなく、現場で運用され、スタッフの成長や定着につながって初めて意味を持ちます。そのためには、制度を“わかりやすく”“使いやすく”“納得できる形で”設計・伝達していく必要があります。ここでは、飲食店で評価制度を定着させるための3つの実践ポイントを紹介します。
「なぜ導入するのか?」を明確に伝える
制度導入において最も重要なのは、目的を全スタッフにしっかりと伝えることです。
「人を選別するためではなく、頑張りを見える化して、成長をサポートするために導入する」
──この意図が現場に伝わらなければ、制度は誤解され、拒否感を持たれてしまいます。
特に初期段階では、面談や説明会を通じて、以下のようなメッセージを繰り返し伝えることが有効です。
-
制度は罰ではなく、サポートのためにある
-
評価を通じて、強み・課題・次のステップを明確にする
-
全員に平等にチャンスがある
現場でも運用できる“簡単さ”と“継続性”を設計する
制度がいくら立派でも、「使いにくい」「続けられない」では意味がありません。特に飲食店の現場は常に忙しく、複雑な仕組みや手間のかかる運用は定着しづらいのが現実です。
そこで重要になるのが、以下の2点です。
| 要素 | 具体策 |
|---|---|
| 簡単に使える | 評価項目をシンプルに。チェック式や5段階評価など直感的な形式にする |
| 続けやすい | 評価の頻度や作業時間を適切に設定。ツール導入で集計や通知も自動化 |
評価システムなどを活用し、店長や社員が“無理なく続けられる仕組み”を構築することが鍵です。
評価結果が“見えるカタチ”で返ってくる仕組みを整える
評価制度の最大の目的は、「働く人が成長を実感できる」ことにあります。
そのためには、評価結果が本人にフィードバックされること、処遇やキャリアに反映されることが欠かせません。
-
評価→面談→目標設定→次回評価…という循環を作る
-
昇給・表彰など“見える報酬”とつなげる
-
キャリアマップやロール設計を用意して、未来の姿を描けるようにする
評価制度が単なる「点数づけ」で終わらず、個々の可能性を引き出すツールとして機能することが、継続的な制度運用の原動力になります。
制度は「人を選ぶ」ものではなく、「人を育て、職場を守るための仕組み」であるという考え方を全スタッフで共有し、チーム全体で成長していく土壌を整えていくことが、飲食店における評価制度成功の本質です。
負担をかけずに制度を定着させるには?評価システムという選択肢

評価制度を定着させる上で、最も大きな壁になるのが「現場の業務負担」です。飲食店では、人手不足や繁忙時間帯の連続で、評価業務に時間をかけられる余裕がないことがほとんどです。店長やマネージャーが紙の評価シートやExcelを前にして悩み、「結局、続けられなかった」というケースも少なくありません。
評価制度の“失敗あるある”
-
評価表を配っても誰も書かない
-
項目が多すぎて集計が大変
-
フィードバックの記録が残らない
-
店長が変わったら制度が消えた
こうした「評価制度が回らない」原因は、**仕組みの難しさではなく、仕組みの“運用負荷”**にあります。
システム導入で変わる、現場の“回しやすさ”
そこで注目されているのが、人事評価システムの導入です。とくに飲食店のような多忙な現場では、評価の入力・通知・集計・履歴管理をすべて“システムが代行”してくれることで、運用コストが劇的に下がります。
たとえば、こんな機能が便利です:
-
スマホやタブレットで評価入力
-
自動リマインドで記入漏れ防止
-
コメント・面談履歴を蓄積して可視化
-
各店舗・スタッフごとの評価傾向を分析
-
本部と現場で情報共有できるダッシュボード
Newtonのような評価システムなら、飲食業にもすぐ馴染む
「Newton」のような人事評価システムは、飲食業にもフィットする柔軟な設計が特徴です。あらかじめテンプレートが用意されているため、評価項目の設計に悩まずすぐに使い始めることができます。
-
テンプレート運用で導入ハードルを下げる
-
現場が使いやすいシンプルなUI
-
店舗数や規模に応じた段階的な導入も可能
-
評価制度の運用支援(導入サポート)も充実
「導入すること」ではなく、「続けられること」を重視して作られた設計だからこそ、制度が自然に現場へ浸透していきます。
評価制度×システム=現場の味方になる
人事評価は、本来「人を育て、やる気を引き出す仕組み」です。だからこそ、それを支えるツール側にも“育てやすさ”“伝えやすさ”“続けやすさ”が求められます。
紙やExcelに限界を感じているなら、まずは1店舗・1評価シートからでもシステム導入を検討してみてはいかがでしょうか。負担を最小限に抑えつつ、組織を育てる評価制度の土台が、着実に形になっていきます。
人事評価制度の導入と運用に関してのよくある質問
評価制度が現場で形骸化してしまう主な理由は?
紙やExcelでの運用負荷、評価項目の曖昧さ、店長交代時の属人化が原因になりがちです。入力・通知・集計を自動化し、項目をシンプルにすることで回りやすさが向上します。
ベテランスタッフからの反発を抑えるにはどうすればよい?
導入目的を丁寧に共有し、過去の貢献も含めて評価する方針を明示します。初期は査定より対話重視の面談形式で始め、構築段階から当事者の声を反映させます。
店長・リーダーが運用しやすい評価の作り方は?
スキルマップなど具体的基準を用意し、チェック式や5段階評価など直感的な形式に。運用マニュアルと簡単な研修、フォローアップで「評価する側」を育成します。
継続運用のために最初に整えるべきポイントは?
完璧主義を避け、四半期など適切な頻度で小さく開始。テンプレートとクラウド型ツールを使い、記入漏れ防止のリマインドや履歴管理で続けやすさを担保します。
評価結果を処遇や育成にどう結びつける?
評価→面談→目標設定→次回評価の循環を設計し、昇給・表彰・インセンティブと連動。業務マニュアルや役割等級と紐づけ、キャリアステップを明示します。
まとめ|評価制度は“現場に届く設計”がカギ

飲食店における人事評価制度は、スタッフの定着やモチベーション向上、育成の仕組みづくりに欠かせない要素です。しかし、現場の状況や人員構成に合わない制度を導入すると、反発を招いたり、運用が続かなかったりと、本来の目的を果たせないまま終わってしまうこともあります。
制度を成功させるために大切なのは、「なぜ導入するのか」という目的の共有と、「誰でも使える・続けられる」運用設計、そして評価結果がスタッフにきちんと返ってくる仕組みです。評価とは、管理のための手段ではなく、“人を育て、職場を守るためのツール”であることを、現場全体で理解し合うことが欠かせません。
人事評価システムNewtonで、“続けられる仕組み”を現場に

どんなに優れた評価制度でも、現場で運用できなければ意味がありません。紙やExcelでは「記入が面倒」「集計が大変」「続かない」といった課題がつきものです。
人事評価システムNewtonは、飲食業にも対応したシンプルで直感的な設計。スマホやタブレットから手軽に評価を入力でき、リマインドやフィードバック履歴も自動で管理されるため、店長やスタッフの負担を最小限に抑えられます。
制度を「作る」から「根づかせる」へ。Newtonが、評価制度を“継続できる仕組み”に変えてくれます。
この記事を書いたライター

Newton編集部
飲食店の人事に役立つ情報を発信していきます。人材から人材へ、人が育つ人事評価システムNewtonとは、飲食店に特化したタレントマネジメント+人事評価システムです。
管理者の人事管理のパフォーマンスを上げるだけでなく、スタッフのモチベーションアップや、離職率の低下、企業にとっての人材を守るシステムです。詳しくはこちら