人事評価制度には主に3つの評価基準があります。
数値化できる明確な成果を評価する「業績評価(成果評価)」、業務へのスキルや知識・資格を評価する「能力評価」、勤務態度や姿勢を評価する「情意評価」に分かれていますが、この中で実際の業務に直結するのが「能力評価」です。
能力評価は、業務を遂行するための技術や能力を元に従業員を評価するものです。
従業員の処遇を決めたり、人材育成に役立てたり、従業員に対してのさまざまなアクションの根拠として取り扱われます。
本記事では、人事評価に能力評価を導入するメリットやデメリットの他、導入の際の注意点を解説します。
人事評価制度の評価項目は、先述の通り「業績評価」「能力評価」「情意評価」の3つがあり、その中でも能力評価は対象の能力が多岐に渡ります。
能力評価とは、業務遂行に必要なスキルや能力を評価する人事評価基準で、従業員が、与えられた職務に対して、いかに能力を発揮し遂行しているか(職能)を評価の対象とします。
長期的な社員の意識向上や育成を目的としており、必要な知識や技能などが評価の対象になります。
その他にも、潜在的な能力として企画力、折衝能力、理解力も含まれます。
能力評価により上司が各従業員の業務遂行能力を可視化し把握できたり、仕事への適応性を判断できるようになると、仕事と人材のミスマッチが減り、社員のモチベーション向上や早期離職対策に繋がります。
個人の成長を効率よくサポートでき、キャリア形成に活かせるのもメリットです。
業績評価のような明確な基準を設けにくく、評価基準が曖昧になってしまうと不信感に繋がってしまうため、評価シートへの書き方には注意が必要です。

先に述べた能力評価以外にも、人事評価の評価基準は下記の2つが挙げられます。
能力評価を含めた3つを総合的に評価します。
それぞれ説明します。
業績評価、成果評価は、従業員の一定期間における会社への目的達成度などの貢献度を評価する方法です。
成果や目標の達成・成長度合い、成果に至るまでのプロセスを部門や個人単位で評価し、目標に対する達成度を評価します。
実績は数値として表すことができるため、明確な判断基準を設けられるのが特徴です。
情意評価とは、従業員の勤務態度、規律性、責任感、協調性、積極性など、仕事に対する姿勢を評価する方法です。
業績評価や能力評価と比べると一番主観の入りやすい評価項目で、定量化できないため評価者の主観が入りやすいのが注意点です。
客観的に判断するために、評価項目をしっかりと設定した上で、上司だけでなく、同僚や部下、取引先など、あらゆる立場の人から評価を集めることで、より正確な評価が下せるでしょう。

能力評価の項目は業種や企業によって異なりますが、ここでは基本的な能力評価の項目の具体例をご紹介します。
上記を元に、能力評価の評価項目を作成するのがおすすめです。

能力評価の実施により、企業側が得られるメリットが存在します。
ここでは能力評価を人事評価に導入することによる影響を、上記3つをご紹介します。
能力評価によって、各従業員にどのような仕事が向いているのか、どの部署の業務なら能力を発揮できるのかを可視化できます。
能力評価を通して従業員一人ひとりの能力が把握できるので、業務内容の適正を判断することができ、人材配置に活かすことができます。
人材の適材適所が実現されれば、業務効率化も期待できるでしょう。
能力評価によって、個人のスキルや能力の評価基準が可視化できます。
従業員自身が、成果を出し評価を高めるにはどうすれば良いか理解することができ、意欲的にスキルアップのための行動が取れるようになるでしょう。
さらにその行動が評価されることでモチベーションが高まり、効率良くスキルアップを目指すことができるという、良い連鎖が発生しやすくなります。
能力評価の実施により、人事評価の評価軸や結果についての根拠が明確になります。
そのため従業員が評価結果に納得しやすくなります。
より良い評価をされるための目的や目標を理解できれば、従業員は待遇にも納得しやすく、業務に取り組む姿勢が改善します。
結果、仕事に対する意欲も湧いてくるでしょう。
能力評価の実施によるメリットは多いですが、下記のようなデメリットも存在します。
それぞれ見ていきましょう。
能力評価は、人が人を評価する構造です。
そのため、評価する人によって評価基準が異なったり、年功序列により、年齢に評価が左右される可能性もあります。
公平性がない評価をしてしまうと、従業員は評価結果に納得できず、不信感を持ってしまいます。
このように公平性のない評価はモチベーションの低下を招き、離職率の増加にも繋がりかねません。
評価の際は、評価基準や評価項目を明確化し、公平・公正な評価を行うようにしましょう。
能力評価は、数字や明確な実績によって評価する業績評価(成果評価)と違い、定量化しづらい評価項目です。
そのため、評価者によって評価に偏りやバラつきが出やすく、曖昧さが発生しやすい部分があります。
このような事態を回避するために、社内で評価者の認識統一のための指導や研修などを実施したり、能力評価だけでなく、他の業績評価や行動評価も併用し、最終的な評価を決定するのがおすすめです。

評価基準が曖昧になりやすい能力評価を、正確におこなうためのポイントを紹介します。
評価者は、上記3つのポイントに気を付けて評価をおこないましょう。
先述のように、能力評価は客観的かつ公平におこなう必要があります。
まず客観性を持たせるためは、評価項目や評価基準を具体的に決めておくことが重要です。
評価者によって評価に違い出てしまうことのないよう、基準を確立しておきましょう。
もちろん評価者の訓練や教育も重要ですが、評価者は個人の感情で人を判断をしない事務的な人間が適しています。
評価者のバイアスや先入観が、評価に入り込まないよう工夫が必要です。
次に公平性を保つには、経営状況や経営戦略などの変化に応じて、その都度、評価項目を見直す必要があります。
より公平性のある評価にするためにも、360度評価や業績評価など、他の評価方法も取り入れましょう。
人事評価をおこなう際には、人事評価エラー(心理的要因による誤った評価)に注意しましょう。
人事評価エラーには、無難な評価をしてしまう「中心化傾向」や、一つの評価が他の評価に影響を及ぼす「ハロー効果」などがあります。
人事評価エラーを避けるためにも、評価者には育成研修を行い、評価時の注意点を理解してもらうようにしましょう。
人事評価は、従来の年功的評価に偏りがちな場合があります。
能力評価では、年齢や勤続年数に依存する年功的評価にならないよう特に注意しましょう。
業務においての能力を基準に判断し、公平に評価をするよう意識する必要があります。
能力評価シートは、基本的に上司からのフィードバックで構成されますが、評価される本人が自己評価を記入することもあります。
どちらの場合も、評価の基準となる具体的な数値を用いることで客観性を感じられ、目標とそれに向けたプロセスも明示しやすくなるでしょう。
能力評価シートの構成が分からないときは、厚生労働省のサイトに公開されている「職業能力評価シート」も活用するのがおすすめです。
能力評価は、従業員が持つ能力やスキルを評価するものです。
しっかりと仕組みを理解し、適切に活用することでさまざまなメリットを得られますが、公平性や客観性を欠いた評価を行ってしまうと逆効果です。
従業員の能力を適材適所で活かすためにも、正確かつ適切な人事評価を行い、従業員のモチベーションを高めましょう。
公平公正な人事評価を行う際には人事評価ツールを活用するのがおすすめです。
人事評価ツールNewton(ニュートン)を活用すれば、複数人による評価を自動取得でき、評価者の納得度も高まるでしょう。
また、社員教育や給与水準に対しての課題、個人の評価も見やすく多くの情報量を瞬時に判断できるシステムで、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な評価制度が特徴です。
適切な能力評価による人事評価制度に注力したいとお考えの方は、ぜひニュートンをご活用ください。
人事考課は、多様性のある社会において企業には不可欠な制度です。
従業員の給与や賞与の査定を始め、従業員のスキルアップやモチベーション向上に直結するため、公平性や客観性を取り入れることが求められます。
そんな人事考課ですが、よく並列して語られるのが「人事評価」です。
本記事では、人事考課について掘り下げるとともに、人事評価との違いについても解説します。
また、それぞれの目的やメリット・デメリット、評価基準についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
人事考課とは、従業員の業務への貢献度や能力を評価し、昇進や昇給の人事査定、給与や賞与等の報酬決定に直結する社員評価の仕組みです。
従業員一人ひとりに求める結果は異なるため、評価基準はそれぞれ別のものになります。
この評価基準は公正なものである必要があります。
基本的には金銭的な部分に関することを決定するのが、人事考課の範疇とされています。
人事考課の目的は、人材を適切に評価し、昇進や昇給、給与や賞与などの賃金管理の処遇全般を決定することです。
従業員の業務成果や能力、業績などをふまえた上で異動配置、能力開発などの根拠にします。
査定基準を可視化し、業務内容の差や人間関係による不公平感を排除することで、公平・公正・平等に実施されるのが理想的です。
人事評価は人事制度の構成要素の一つで、評価結果を従業員の育成や成長に繋げようとする考え方が特徴です。
従業員の業務結果や能力を正当に評価し、モチベーション向上や人材育成へと繋げることに重点が置かれ、直接的な賃金や地位の報酬よりも、やりがいを引き出すために賞賛や承認をおこなうために人事評価とされています。
人事評価の目的は、従業員が会社の基本指針・理念に沿った行動や成果を上げているかを把握し、適切な評価をすることです。
主に従業員の評価決定・育成を目的とする部分があるため、人事評価は給与と結びつけずにうまく運用することで社員の育成につながっていくでしょう。
「人事評価の目的」についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参照ください。

人事考課と人事評価についての違いですが、実は根本的な違いはないとされています。
古くから「人事考課」という言い回しが多くの企業で使われていたものの、最近では「評価」という誰にでも分かりやすい言葉を用いるようになってきたといわれています。
一般社会では人事考課と人事評価を区別せずに用いる企業も多いことから、ほぼ同じ意味と捉えても問題はありませんが、厳密な線引きとしては、下記のように区別されることがあります。
人事考課と人事評価は、社員を評価するという点では共通していますが、「人事考課」は給与や賞与など、金銭的な部分に関することが決定されるという認識で、狭義の評価を指します。
対して「人事評価」は、従業員の人材育成や能力開発を含め、人事異動などに関わる部分の評価で、より広義でとらえた評価と認識されています。
人事評価の方が人事考課よりも、より大きな評価対象の分類となります。

人事考課の評価基準は、企業によって異なります。
今回は、業界問わず広く使用されている3つの項目をご紹介します。
業績考課は、一定期間における、企業目標やノルマに対する達成度の評価です。
目標に対する達成度をMBOやOKR(目標管理制度)を活用して行われます。
目標への達成率が足りなければマイナス評価になり、大きく達成しているならプラス評価になるため、シンプルで納得性の高い評価方法ですが、その客観性や公平性を保つためには、数値化された明確な判断基準を設ける必要があります。
そのため業務考課では、中間目標としてKPIと最終目標としてKGIを、あらかじめ明確に設計しておきましょう。
能力考課は文字通り従業員のスキル、知識などの能力に加え、コミュニケーションスキルやリーダーシップ、企画力、計画力、実行力など、直接的な業務スキル以外も評価します。
各個人の能力が実際にどれくらい発揮されたか、それを開発しようと努力しているかも評価対象になります。
各能力をどの程度評価に落とし込むかは、業界や会社、業務内容、あるいは職位によっても異なってくるのが一般的です。
情意考課は、従業員の仕事に対する意欲や姿勢、態度を評価する方法で、業務に対する積極性や責任感などの姿勢、日々の行動などの勤務態度が反映されます。
規律性、責任感、協調性、積極性などを評価するため、定量化することが難しく、評価者(上司)の主観が反映されやすいことから公正な判断が難しい場合もあります。
一定の評価項目を設定し客観的に評価することができれば、周囲との協調性や企業のビジョンへの共感にも繋がる重要な観点となります。
人事考課で評価を行う際に、役立つ評価方法について確認してみましょう。
コンピテンシー評価とは、業務においての成績や業績が高い、ロールモデルになり得る従業員に共通する「コンピテンシー(行動特性)」に着目して、それを基準とした「コンピテンシーモデル(評価基準)」を設定し、ここの従業員の評価基準を策定する評価方法です。
優秀な人物に行動内容や能力が近づくほど、高い評価になります。
会社側としては、従業員に求める優秀な人材を評価項目として明確に示すことで、自社の方向性や理念を従業員と共有することができ、従業員側としては努力や自己研鑽の方向性も明確化することでモチベーション向上にも繋がります。
360度評価は、評価対象者の上司やリーダーのみではなく、同僚や部下、他部署や社外取引先など、複数名が評価する手法です。
さまざまな立場から評価することによっていち個人のバイアスが取り除かれ、評価対象者を客観的に評価することが可能になります。
360度評価によって評価対象者が職務遂行能力を備えているかどうかを判断し、公平性を保った公正な人事評価を行うことが可能になり、それにより評価に対する社員の納得感も高まる方法です。
MBOとはManagement By Objectivesの略称で、直訳すると「目標(Object)による管理(Management)」です。
元々は経営学者のP.F.ドラッカーが1950年代に提唱したマネジメントの概念で、「従業員が自分で目標を決める」というのが特徴です。
組織目標に対する貢献方法として従業員自身の目標を紐づけて設定します。
目標達成までの従業員の自主性を育み活性化し、モチベーションを向上させる仕組みとされています。

人事考課を行う際のメリットはたくさん存在しますが、大前提として、人事考課の評価基準が可視化され、かつ従業員に正しく伝達できていることが重要になります。
ここからは、人事考課によって得られるメリットを具体的にまとめていきます。
くわしく説明していきます。
人事考課を導入することで、企業側は査定基準を従業員に伝え、従業員側は仕事に対する希望やキャリアパス、疑問点等について、企業とコミュニケーションを活性化させることができる良い機会となります。
双方の理解が深まることで、企業は個々のキャリア形成に最適な人材マネジメントを実現することが可能になり、従業員は業務遂行においての不満解消にも役立ち、離職率の低下にも繋がります。
人事考課の際、企業は従業員に企業ミッションを提示することになります。
企業が描く方向性を共有し、従業員に期待する行動水準への理解を促すことで、従業員自身も仕事や、自身の必要性を認識することができるでしょう。
評価の優先度を見える化することで企業の将来像を伝えることができ、従業員も日々の業務を通し目標達成に向けて、主体性を持って行動できるようになるでしょう。
人事考課を通して企業は従業員に評価のポイントを伝えるため、従業員自身はどのようなスキルを身に付ければ評価されるのかを理解できるメリットがあります。
一人ひとりの自己研鑽・努力の方向性が明確になるため、従業員のモチベーションも高まります。
適切な評価・フィードバックで納得性のある人事考課を行うことができれば士気も高まり、企業全体の生産性向上も期待できるでしょう。
人事考課にはメリットが多い一方で、デメリットも存在します。
主なデメリットには下記があります。
把握した上で、人事考課を行うようにしましょう。
従業員全体を適切に評価するということはとても難易度の高い業務のため、評価者側にも非常に高いスキルが求められます。
従業員との対話を重ねることは、大変な時間と労力を要します。
その中でできる限り公正中立で平等な人事考課を行う必要があるため、とても困難であるといえるでしょう。
いくら評価者自身が公平性を保って評価しているつもりでも、評価対象者が不公平さを感じている場合には意味がありません。
また評価基準が曖昧になってしまい納得感のある人事考課が行われないと、従業員のモチベーションが低下する恐れもあります。
モチベーションの低下や離職を予防するためにも、公正でバイアスの生じない評価制度や、適切なフィードバックを通し、一定の納得性を持てるような人事考課を行う必要があります。
人事考課制度は、あくまでも「自社にとって望ましい人物像」に焦点を当てて評価します。そのため、画一的な人材開発に繋がってしまう可能性も孕んでおり、型にはまった人材育成となってしまうかもしれません。
このような事態を避けるため、人材要件に変化が生じた際に対応できるよう、評価基準について型にはめすぎないよう注意する必要があります。
今回は人事考課や人事評価の違い、それぞれの目的などについてご紹介しました。
人事考課や人事評価を通し従業員を適切に評価する制度は、従業員の業務に対するモチベーションを高めるだけでなく、人材育成にも繋がる重要な仕組みです。
そのため、適切な評価について理解を深め、公平且つ多角的に評価を進めることが大切です。
しかし、人材を適切に評価するということは決して簡単なことではなく、まして完璧な人事考課を行うことは極めて困難です。適切な評価を行うためには、評価する側にも非常に高いスキルが求められます。評価者・評価対象者双方が納得できることが重要です。
人事考課・人事評価への課題が増えてきたら、業務の流れを再検討し見直してみてもよいかもしれません。評価ミスを防ぐためにも、人材管理システム・タレントマネジメントシステムの活用がおすすめです。
人事評価ツールNewton(ニュートン)は、社員教育や給与水準に対しての課題や、スキル・マネジメント・スタンスなど個人の評価が細かく判断でき、課題や教育指針の共有が可能です。個人評価と上長評価の差異が一目で分かるため、教育の質・スピードが効率化されます。また独自のシステムにより、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な仕様が特徴です。
単独の評価者では評価にムラができやすいですが、複数人による多画的な評価をデータで自動取得できることにより納得度も高まるでしょう。(※特許取得済)
いつでもどこでも入力が可能なので手軽に導入しやすい点も喜ばれています。
組織・企業の成長に繋がる人材育成を実現したいとお考えの方は、ぜひニュートンをご活用ください。
現代では、企業が生き残るためには従業員の能力やスキルの活用が非常に重要な鍵となっています。
人事評価や評価データの管理は、Excelなどを利用して管理することもできますが、多くの人的リソースと時間が必要という問題があります。
そこで近年では、人事評価システムの導入が一般的になっています。
人事評価システムを導入することで、従業員の能力・スキルを活用でき、従業員のモチベーションやパフォーマンス向上、さらに業務の効率化まで期待できます。
特に人手の少ない中小企業こそ、人事評価システムを導入することで恩恵を受けやすいため、本記事では中小企業に焦点を当て、導入のメリットや選ぶ際の注意点などを解説します。
人事評価制度は、従業員の人材育成やモチベーション向上、さらに企業成長に不可欠な非常に重要な業務ですが、この評価制度をシステム化したものです。
人事評価の関連業務は多岐に渡り、多くの工数がかかるため、従業員数が少ないうちはアナログにExcel管理などでも可能ですが、人数が増えるほどリソースを確保するのが難しくなり、ミスが発生することも考えられます。
人事評価システムを導入することにより、この業務を効率よくミスなく行うことができます。
人事評価システムとは、従業員の業務に対する姿勢や能力、給与などのパーソナルデータを一元管理し、様々な角度から人材を分析することができるタレントマネジメントシステムです。
人事評価関連業務における評価シートの作成や配布、データの集計・管理などのさまざまな工数がシステム上で完結します。
分析した人事評価データを採用業務や育成計画の参考にするなど、組織づくりへの活用も見込めるため、組織の問題点の洗い出しや改善策の立案がしやすくなります。
人事評価システムを活用することで評価基準を明確にしながら主観による評価を防止することもできるため、公平で納得感のある評価に繋げることができるでしょう。
人事評価の方法として、よく活用される5つの方法があります。
一つずつみていきましょう。
MBOとはManagement by Objectivesの略で、直訳すると「目標管理制度」となります。
経営目標や部門目標を踏まえて個人目標を設定し、目標の達成度を評価する手法で、目標の達成度合いに応じて評価を決めます。
企業の経営目標をまず設定した上で、その内容をブレイクダウンして各組織、各個人の目標設定を実施し、個人の目標の達成度を人事評価システムによって評価し、全社的な目標達成度を測定する方法です。
OKRはObjectives and Key Resultsの略で、「目標と成果指標」と直訳されます。
組織としての目標設定を部門単位へ、さらに部門単位から個人単位まで落とし込み、最終的に企業の目標達成を実現することが目的です。
OKRは前述のMBOと比較されることが多いですが、最も大きな違いは、目標の高さ・頻度の違いにあります。
MBOは目標に対する達成度で評価するのに対し、OKRでは高い頻度で目標設定し、追跡、再評価を行う目標管理方法で、高い目標設定をすることに意味があるとした制度です。
360度評価とは、上司・部下・同僚など、社員に関係するさまざまな立場から多画的に評価を行う手法です。
上司だけでなく、一緒に仕事をしたことのある部下や同僚、顧客など、異なる立場の複数人から多角的な評価を得られるのが特徴です。
より客観性や公平性を保った公正な人事評価を行うことができ、評価に対する社員の納得性も高まる制度です。
コンピテンシー評価とは、職種ごとに高い業績・成果を上げているパフォーマンスの高い従業員に共通する行動特性を基準に、人事評価を行う手法です。
ハイパフォーマーの行動やインタビュー内容をもとに行動や思考の傾向を分析し、評価基準項目を抽出します。
自社のロールモデルを基準に設定することで、「どのような行動をすれば評価されるのか」が明確になり、従業員の意識を高めることが期待されるでしょう。
1on1ミーティングとは上司と部下「1対1」で行うミーティングのことで、上司と部下の間で、本人の能力開発について頻度高く面談する仕組みを指します。
従来の人事面談とは違い、部下の成長を促す意味合いで行われるのが特徴で、上司と部下の双方に有効なコミュニケーションをはかることができます。

人手不足の問題を抱えている中小企業では人事評価システムを導入することで、従業員の情報の一元化と業務の効率化が期待でき、解決できる課題も多いでしょう。
ここでは、人事システムで解決できる中小企業の課題について解説します。
社員の継続的な雇用や育成には、人件費を含めたさまざまな費用が発生します。
また、多角的で公平・公正な人事評価を実施するためには、人的・時間的コストも求められます。
人事評価システムを導入することで、人事評価においての評価シート作成から分析、給与の自動計算、休暇管理までがスムーズに進みます。
さらに自社の企業ミッションへの理解を従業員に促すことができるため、従業員の行動水準を高めることにも繋がります。
人材評価システムを導入することで、個々のスキル・レベルに合わせた適材適所の人員配置を実施できます。
Excelや紙など手作業で従業員のデータを管理するとなると、膨大な時間と労力が必要になりますが、人事評価システムの人事データには過去の業務経験や能力、スキル、資格などが含まれるため一目で人事データを分析できるようになります。
適材適所の人員配置は、従業員自身の実力発揮ができる場に配置されるということなので、従業員のモチベーション向上や離職率の低下にも繋がります。
人的リソースを割きづらい中小企業にとっては、企業全体のパフォーマンス向上にも繋がるでしょう。
中小企業では社長や幹部が現場に出たり、人事評価を担うという状況も多く、経営業務に専念できないという問題があります。
人事評価システムを導入することで人事評価関連業務の圧倒的な工数削減に繋がるだけでなく、報酬や昇進に関する決定もサポートできるため、社長や幹部は現場を離れ、経営業務に専念することができるようになります。
さらに人事評価においての査定基準が明確になるため、業務の質向上とあわせて、従業員のモチベーション向上や離職率の抑制にも役立ち、組織全体の生産性を高めていくことができるでしょう。

中小企業が人事評価システムを導入するメリットは数多く存在します。
くわしく解説していきます。
人事評価制度には公平・公正な人事評価が必要ですが、人が人を評価するという性質上、評価に主観が入ってしまうことも少なくありません。
評価基準が曖昧だったり、評価者によって評価にバラつきが出たりしてしまうと、公平性に欠けてしまい、従業員の不満に繋がり、最悪の場合離職に繋がってしまう可能性があります。
人事評価システムを導入することで、蓄積したデータを元に判断できるようになるため、主観に頼らない公平・公正な人事評価が可能になります。
人事評価システムには、従業員の評価や勤怠、給与や異動履歴などのパーソナルデータが一元管理されています。
これらのデータを多角的に分析することで、組織の問題点の洗い出しや改善策の立案がしやすくなるほか、各従業員のスキルレベルが可視化されるため、適材適所の人材配置や人材育成にも活用できるでしょう。
人事評価制度において、フィードバックやアドバイスは非常に繊細な業務で、このプロセスを丁寧に踏まないと従業員のモチベーションを下げることになりかねません。
人事評価システムを導入することによって、システムに組み込まれた形で評価プロセスを踏むことができるため、従業員のモチベーションを下げることなくコミュニケーションの活性化をはかることができるでしょう。
人事評価システムの導入により、人事評価の工数の多い業務プロセスを自動化・システム化し、人事業務の効率化をはかることができます。
従業員一人一人のスキルやレベルに合わせた人材配置ができるため、強固な組織づくりへと繋がり、業績アップも期待できるでしょう。
人事評価システム導入のためにはいくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは人事評価システムを導入する際の進め方をご紹介します。
人事評価システムを効率的に導入するにあたり、まずは自社の人事評価制度の見直しが大切になります。
自社の評価制度自体が不確定だと、システムを導入しても恩恵を得られない場合があるため、あらかじめ評価制度の整理・見直しましょう。
人事評価システム導入検討の際は、その導入目的と評価基準を整理し、明確にしておくことが重要です。
まずは自社の評価制度を見直したものを分析し、システム導入により実現したい目的を定めた上で、従業員へ明示する評価基準を整理します。
評価基準をしっかりと明確化して従業員へ周知することで、評価結果の意図や理由を理解しやすくなり、納得感のある効果的な評価運用に繋げることができます。
人事評価システムの導入にあたり、最適なシステム選びも重要なプロセスです。
自社の評価制度や導入目的を整理した上で、必要な機能と不要な機能を洗い出します。
機能性や操作性をしっかりと確認しつつ、コスト面も考えてオーバースペックにならないよう、適切なものを選定しましょう。
この時、企業の規模に合ったものを選ぶことも重要です。
中小企業と大企業では従業員数や評価制度が異なる部分があるため、自社の規模に合ったシステムを導入するのが大切です。
人事評価システム導入が決定した際は、従業員への周知を行います。
新たにシステムを導入するとなると、従業員はシステムの操作方法や運用について覚える必要があったり、従来の人事評価制度から変更がある場合もあります。
負担を最小限に抑えられるよう、社内研修や説明会などを用意してわかりやすい説明を行い、運用体制を整備しておきましょう。
統一した評価基準や客観的な視点で評価できるよう、評価者への教育も大切なポイントです。

人事評価システムを導入する際には、自社に合ったものを選定することが重要です。
人事評価システムの選び方のポイントをまとめました。
一つづつ見ていきましょう。
人事評価システムを導入する前に、まずは自社の導入目的を明確にしておくようにしましょう。
人事評価システムはさまざまあり、多機能なシステムは便利ですが、その分コストもかかります。
まずは自社の課題を明確にした上で、求めている機能を備えた物、使わない機能が少ない物を選びましょう。
また、今後の制度や法律改定を踏まえた機能があるかどうかも注目しておくのがおすすめです。
カスタマイズ機能があるものを選ぶと、システム導入以降も将来的に長く使用していけるでしょう。
人事評価システムを導入するには費用がかかりますが、機能が増えるほど当然高額になります。
限られた予算の中で効率的に活用するために、必要な機能をしっかりと洗い出ししておきましょう。
システム導入には、初期費用だけでなく、運用やメンテナンスにも費用がかかるため、その点も考慮しておく必要があります。
予算と機能をバランス良く調整することで、中小企業や小規模企業でもコスト効率の高い人事評価システムを導入できるでしょう。
人事評価システムの形態にはクラウド型とオンプレミス型の2種類があり、それぞれメリットとデメリットがありますが、中小企業の場合、導入コストが安価なクラウド型のシステムがおすすめです。
クラウド型は、インターネット経由で利用するタイプで、インターネットに接続されていればどんな場所・端末でも利用することができるため、出張中やテレワーク等でも対応が可能です。
ウェブのクラウド上にシステム環境を構築し、各データを集約して利用するため、サーバーの設置が不要で、導入コストも安価です。
デメリットとしては、機能のカスタマイズ性の低さと、通信状況の影響を受けやすい点が挙げられます。
オンプレミス型は、自社にサーバーを構築するタイプで、自社内に設置するため、セキュリティ対策がしやすいのが特徴です。
自社内に設置した専用サーバー内に構築したシステムをインストールして運用するので、機能のカスタマイズ性が高く、自社に合ったシステムを構築したい場合におすすめです。
デメリットとしては、サーバー設置のための構築・維持に多額のコストがかかる点でしょう。
人事評価システムでは、社員のさまざまな個人情報を管理します。
情報漏洩などのトラブルを避けるために、セキュリティ機能をしっかりと搭載したシステムを選ぶようにしましょう。
クラウド型のシステムの場合、ウェブ上にシステム環境が構築されており、セキュリティ対策はベンダー側が行います。
ベンダーのデータセンターにおいて、どのような対策がとられているのかを事前に確認しておくようにしましょう。
導入する予定の人事評価システムが、従業員にとって使い勝手が良いかも重要なポイントです。
人事評価システムを使用する評価者が、マニュアルを読まずとも、感覚的に情報を即座に把握できるシンプルな作りの物であること、また誰が見ても分かりやすい分析結果が出るかどうかも大切です。
人事評価ツールNewton(ニュートン)は、社員教育や給与水準に対しての課題や、スキル・マネジメント・スタンスなど個人の評価が見やすく、多くの情報をひと目で確認できます。
多角的に従業員を評価することができ、人材情報の一元管理はもちろん、評価基準の明確化や、育成計画の目標管理も可能です。
単独の評価者では評価にムラができやすいですが、複数人による多画的な評価をデータで自動取得できることにより納得度も高まるでしょう。(※特許取得済)
人事評価制度により組織・企業の成長に繋がる人材育成を実現したいとお考えの方は、ぜひニュートンをご活用ください。
人事評価制度とは、企業の従業員の能力や業績を評価する制度で、社員のパフォーマンスや働きぶりを査定し、それを報酬や等級に反映させるシステムです。
以前は能力よりも勤続年数や年齢で役職を決定する年功序列制が主流でしたが、近年では個人の能力や実績を理解し、評価する人事評価・人事考課が注目されています。
適切な人事評価制度の運用ができれば、従業員のモチベーションを高められるだけでなく、生産性の向上、人材育成などにも役立ちます。
本記事では、人事評価制度において存在するメリットとデメリットをまとめました。また各手法の特徴や対策もご紹介していくので、人事評価制度を有効活用したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
人事評価および人事考課とは、従業員の能力やパフォーマンス、業務への貢献度などを可視化して評価し、従業員個々の給与・賞与・昇進などに反映させる制度です。
正しく運用することでさまざまな組織課題の改善に役立つ制度ですが、その一方で不適切・不公平な運用を進めてしまうと、組織運営や業績に悪影響をもたらします。
人事評価を行う際には、自社がどのような目的で人事評価を行うのかをしっかりと理解しておくことが大切です。
人事評価制度の主な目的としては、企業のビジョンや方針、指標、従業員に期待する行動や能力の明確化が挙げられます。
評価制度を活用することで評価基準が明確になり、従業員の成果やプロセス、能力に応じて評価できるので、適切な待遇を決めやすくなります。
公平な評価によって適切に昇給や昇格がされれば、従業員のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。その際の従業員の給与や等級の査定には、個人の主観を挟まない公平な評価が欠かせないため、この点は注意が必要です。
人事評価制度により個々の技術や経験もデータベース化できるため、適切な人材配置を行うことができ、マネジメントの効率化も期待できます。

人事評価は、大きく分けて3つの評価制度で構成されています。それぞれの人事評価を解説します。
この3つの要素は、相互に関係しながら人事評価制度を構成しています。一つずつみていきましょう。
等級制度とは、社員に求める能力(どのようなスキルを持っているか)、職務(どのような仕事をして欲しいか)、役割(どのような役割を組織内で発揮して欲しいか)などを分類し、企業ごとに分類、階層化したものです。
等級定義を明示することで、従業員も次の目標が明確になり、企業内での成長のステップを認識してもらうことができます。
評価制度とは、上述の等級制度によって決定された評価を元にして、企業の行動指針をふまえ、部長や課長などが各従業員の行動や成果を評価するものです。
個人の業績や成果の他、行動指針の体験度合いや成長度合いといった定性的な目標も設けて評価していきます。「等級制度」によって決定された等級ごとに評価項目が変化するのが特徴です。
報酬制度とは、上述の評価制度に基づいて、報酬や役職、給与や賞与などの待遇面に反映させるものです。
日常の勤怠状況や業務意欲・態度・貢献度、責任感や協調性を評価し、決められた等級ごとに、報酬の上限や下限を変化させます。
給与、インセンティブといった金銭的な報酬以外にも、仕事や役割など非金銭的な報酬に反映される場合もあります。

人事評価制度の運用は、会社にさまざまなメリットを与えます。
人事評価制度におけるメリットを確認していきましょう。
人事評価制度を導入する際、企業理念やビジョンを評価面談の場で共有することになります。
企業理念やビジョンとは、企業の価値観や方向性、目指すべき将来像などを示したもので、社員が理解を深めることで、企業の理想とする目指すべき従業員象を目指すモチベーションにも繋がります。
また、企業理念・目標設定への理解をしてもらうことで、会社と従業員の方向性のズレを軌道修正する効果もあるでしょう。
従業員の成果に見合った正当な人事評価制度を導入すると、従業員自身の努力が待遇に反映されるため、給与・待遇を上げるための労働意欲が向上し、職場の生産性や業績の向上へと繋がるでしょう。
さらに、人事評価制度において各従業員が来期に向けてどう取り組むべきかの個人目標を設定し、その個人目標の達成度合いによって評価をするため、目標達成までのプロセスや進捗度合い、目標達成に向けた行動などが分かりやすくなり、マネジメントもしやすくなります。
人事評価制度導入時には、具体的な人物像を設定して評価をします。そのため、評価基準を明確にできるという点もメリットです。
人事評価制度では公平な評価を行うことが重要です。客観的視点で個人の主観を挟まずに給与や等級の査定を行うため、社員の処遇を決める根拠として有用でしょう。
人事評価制度では、人材データを元に評価を行います。従業員の成果や業績以外にも、それぞれのスキルや課題を把握することができるため、適材適所への配置が叶い、従業員のスキルアップ・成長の手助けのサポートができます。
それぞれの問題点を指摘したり、従業員ごとに目標・研修を提示したりすることで能力開発に繋がり、人材開発・人材育成に取り組むことができます。
人事評価制度では評価面談や1on1などを行うこととなるため、上司と部下の業務においての信頼関係を築くことができます。普段話さないような内容の会話ができる機会となるため、相談や提案がしやすくなったりと、コミュニケーションの促進が期待できます。
評価に関するフィードバックを通して、従業員のモチベーションアップにも繋がるでしょう。
人事評価制度の運用は、さまざまなメリットがある反面、注意すべきデメリットも存在します。
それぞれ確認していきましょう。
人事評価制度では、基本的に序列ができてしまうのは仕方のない点ですが、正しく評価できなかった場合、従業員は企業に不満を抱き、モチベーションの低下により退職に至ってしまうケースもあります。優秀な人材ほど見切りをつける判断が早いとされているため、せっかくの人材が他社へ流出してしまうこともあるでしょう。
特に、自己評価よりも会社からの評価が低かった場合に大きな不満要素となります。従業員からの不満に関する問題を解決するために、評価への適切なフィードバックとフォローが不可欠です。
人事評価制度で評価されると、給与や処遇に反映されます。そのため、従業員が評価の向上だけに囚われて、高評価の得られる業務しかしなくなり、評価対象外の業務がおろそかになるリスクがあります。
不適切な評価は従業員への不当な扱いにつながり、組織内周囲での業務のバランスを乱し、全体の効率性に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
また、人事評価の基準を細かく指定しすぎると、求める能力や目指すべき人物像の幅が狭まってしまい、個性のない組織に育ってしまう危険性もあります。
このような事態を避けるために、従業員それぞれの個性や資質に合わせた評価をする必要があります。抽象的な項目や基準も採用すると、多様な人材の育成が見込まれるでしょう。
人事評価の運用には、手間がかかるものです。
評価者となる担当者は、正当かつ公平な評価を行う必要があります。しかし、主観が入らない評価を行うのは難しく、評価者間で評価のつけ方にばらつきが出るケースもあります。そのため人事評価者のスキルアップのための適切な評価者教育が必要です。
管理が難しいと感じる場合は、人事評価システムを導入するのもおすすめです。
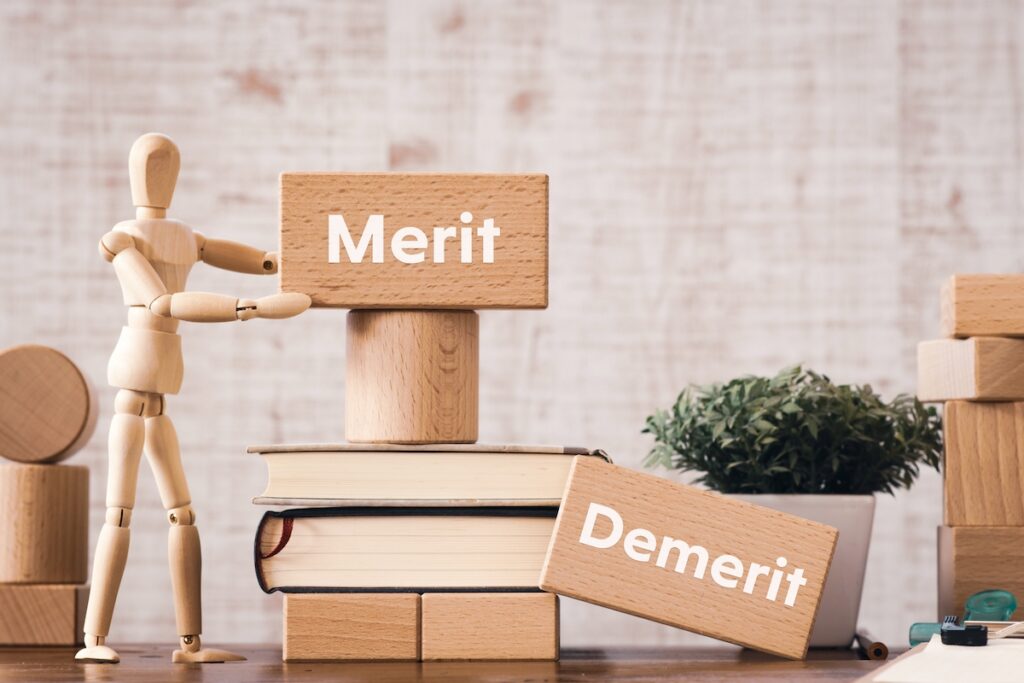
人事評価にはさまざまな手法があります。
今回は3つの評価制度について、メリットとデメリットをご紹介します。
360度評価・多画評価とは、上司・部下・同僚など、社員に関係するさまざまな立場から多画的に評価を行う手法です。異なる立場の複数人からの評価や意見を反映させることにより、客観性や公平性を保った公正な人事評価を行うことが可能になり、それにより評価に対する社員の納得感も高まります。
メリット
デメリット
コンピテンシーは、「業務を遂行する能力や行動特性」を指します。
コンピテンシー評価とは、社内で高い業績を上げる人材の行動特性(コンピテンシーモデル)を評価基準に落とし込み、従業員の評価基準を作成する人事評価制度の手法です。
コンピテンシー評価により、企業が求める人物像や明確な組織目標が明示されるため、従業員の意識を高めることが期待されるでしょう。
ノーレイティングとは、ランクづけをしない人事評価制度の手法です。
ランク付けをされないことで、従業員のモチベーション低下を防止し、個性や多様性を認めた評価ができると期待されているため、社員の成長を促し即座にモチベーションをアップさせることができます。
メリット
デメリット
目標管理制度(MBO)とはManagement by Objectivesの略で、直訳すると「目標管理制度」となります。
1954年にP.F.ドラッカーが著書「現代の経営」で提唱した組織マネジメントの理論で、経営目標や部門目標を踏まえて個人目標を設定し、目標の達成度を評価する手法です。目標とその結果が明確なので評価が容易にでき、多くの企業で人事考課に組み込まれています。
メリット
デメリット
人事評価制度には、「明確な評価基準」「公正な評価」「適切なフィードバック」が必要です。
評価者が制度への理解をしっかりと深めた上で、明確で透明性の高い評価基準を設定し、公平な立場で従業員を評価できるよう研修を実施すること、また評価に対しての適切なフィードバックを意識しましょう。
特に評価が低かった従業員ほど企業に不満を感じる可能性が高いため、納得感を持てるようなフィードバックや制度作りが重要です。
人事評価制度を有効活用することで企業理念の共有や社員のスキル把握、コミュニケーションの促進など、さまざまなメリットがあります。
上手く使えば組織力を大幅に向上させることが可能ですが、一方でデメリットも存在するため、導入の際には注意が必要です。
導入の負担は、人事評価をシステム化することで、評価の質や納得度を上げることができるでしょう。従業員の信頼が格段にアップすれば、生産性や品質の向上に期待できます。
これからタレントマネジメントの仕組み化・見直しをお考えの方には、人事評価に特化した特許取得済のツール、「Newton(ニュートン)」がおすすめです。
各従業員のスキルや個人評価をはじめとした多くの情報を瞬時に確認できる独自のシステムで、個人に適した項目や基準設定により絶対評価が可能になり、組織・企業の成長に繋がる人材育成の実現が目指せるでしょう。
人事評価制度とは、組織目標達成や人材育成のための制度の一つで、個々に合った育成の実施や、配置転換の決定といった人材マネジメントにも用いられます。
従業員の能力や会社への貢献度などを可視化・評価し、報酬や等級などの待遇に反映させる仕組みであり、従業員のモチベーション向上や適切な人材配置・人材育成へと繋がる重要な制度です。
本記事では、人事評価制度の目的や仕組み、主な人事評価手法の他、効果的に評価を行うためのポイントについて解説します。
人事評価制度を有効活用することで、業績向上も期待できるでしょう。
見直しを考えている方は参考にしてください。
人事評価制度とは具体的に、従業員の能力やパフォーマンス、業務への貢献度などを可視化して評価し、従業員個々の給与・賞与・昇進などに反映させる制度です。
従来のように、年齢給と職能給の合算で給料を決める年功序列制度ではなく、各従業員の能力値・貢献度に合わせて処遇を決定するため、従業員は自身の評価向上を目指して、意識や行動を変える努力をするようになるメリットがあります。
透明性のある公正な評価基準や、昇進・昇給の可能性を明示することで、従業員も安心して業務に集中することができます。
また、企業と従業員の信頼関係が生まれることで離職の回避に繋がる上、エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。
各企業によって人事評価のタイミングや評価基準は異なりますが、多くの企業では四半期・半期・1年などの期間を設け、定期的に見直し評価がおこなわれます。
ただし、人事評価制度は人が人を評価する制度であることから、「評価エラー」が起こる可能性があり、リスクの一つとなっています。
起こりやすい評価エラーの例として、「ハロー効果(一つの良い/悪い印象により他の部分まで同様の印象を受けてしまうこと)」や、「寛大化/厳格化傾向(特定の部下に対して全体的に甘い/厳しい評価をしてしまうこと)」などが挙げられます。
そのため、客観的な基準に基づいた公正な評価制度が必要になります。
複数の異なる立場の人の意見を集めたり、人事評価ツールを導入することで、評価エラーを回避しやすくなるでしょう。

人事評価を行う際には、自社がどのような目的で人事評価を行うのかをしっかりと理解しておくことが大切です。
自社の企業目標を設定した上で、各従業員の評価を適正に行いましょう。
人事評価制度を導入する目的は、主に下記の4点が挙げられます。
それぞれ詳しく解説していきます。
人事評価制度を導入する際に、自社の企業目標を明確化することは大切です。
組織目標と人事評価制度を連携させることで、従業員の現状スキルや能力の差を明らかにすることができます。
適切な評価、フィードバックにより、従業員の能力・意欲形成にも繋がり、業績の向上も期待できるでしょう。
企業のビジョンを実現するには、従業員一人ひとりの意識を向上させることが重要ですが、人事評価制度により、企業が従業員に期待し求める能力や行動が明確になります。
会社からの評価や判断基準を理解することで、従業員自身が目指すべき行動・戦略を取りやすくなるため、自主的・積極的に行動し、組織に貢献していける人材となりやすいでしょう。
従業員が行動するための指針となり、従業員の能力発揮を促すことも人事評価制度の目的の一つです。
人事評価が適切に行われ、評価結果を元に給与・賞与や昇進・昇格、異動などの処遇手当が決まることで、公平性が保たれた組織改革を行うことができます。
従来の国内企業では、年齢給と職能給の合算で給料を決める年功序列制度が主流でしたが、この制度では、年齢が若い従業員や社歴が浅い従業員の中に優れた人材がいても、能力に見合った処遇を与えることができません。
人事の管理面ではわかりやすいですが、若年層から不信感・不満が残るリスクがあります。
各従業員の能力値に合わせて処遇を決定することで、従業員は自身の評価を高めるために、意識や行動を変える努力をするようになるというメリットがあります。
納得できる人事評価により、従業員のモチベーションの向上に繋がり、業務内容にやりがいを見出し、能力・スキルの向上を目指すことができるため、結果的に組織の活性化につなげることができるでしょう。
人事評価制度により、社員それぞれの長所や短所、特徴が明確になり、個々の技術や経験もデータベース化できるため、適切な人材配置を行うことができます。
各従業員が上司と相談し個々の個人目標を設定することで、目標達成までのプロセスや進捗度合い、目標達成に向けた行動などが見えるようになるので、マネジメントの効率化にも繋がるでしょう。

適切な人事評価制度を導入・運用できれば、社員だけでなく経営層にもメリットがあります。
人事評価制度を構成する要素として、以下の3つが主に挙げられます。
この3つの要素は相互に関係しながら、人事評価制度を構成しています。
一つずつみていきましょう。
等級制度とは、社員に求める能力(どのようなスキルを持っているか)、職務(どのような仕事をして欲しいか)、役割(どのような役割を組織内で発揮して欲しいか)などを分類し、企業ごとに階層化したものです。
等級・階層化することで、従業員も次の目標が明確になり、企業内での成長のステップを認識してもらうことができます。
評価制度とは、上述の等級制度によって決定された評価を元にして、部長や課長などが各従業員の行動や成果を評価するものです。
企業の行動指針に基づいて、個人の業績・成果の他、成長度合いも評価します。
「等級制度」によって決定された等級ごとに評価項目が変化するのが特徴です。
報酬制度とは、各従業員の行動や結果に応じ、報酬や役職、給与や賞与などの待遇面に反映させるものです。
評価基準や項目、評価手法は会社ごとに異なり、前述の等級制度によって決められた等級ごとに、報酬の上限や下限が変化します。
日常の勤怠状況や業務意欲・態度・貢献度、責任感や協調性を見て判断しますが、評価者の主観が入りやすく公平性に欠ける可能性があるため、複数人で評価するなどの工夫が必要です。
人事評価の評価基準としては、以下の3つが挙げられ、これらを総合的に評価します。
3つの評価基準についてそれぞれ詳しく解説します。
能力評価とは、業務を遂行する上で求められるスキルや知識といった従業員の能力や、その能力自体がどれくらい発揮されたかを評価する方法です。
主な評価項目には「企画力」「計画力」「実行力」などがあります。
業績評価、成果評価とは、一定期間における会社への貢献度を評価する方法です。
従業員の成果や目標の達成・成長度合い、成果に至るまでのプロセスを部門や個人単位で評価します。
部門や社員の目標の達成度を評価するために、数値化された明確な判断基準を設ける必要があります。
情意評価とは、従業員の規律性、責任感、協調性、積極性など、仕事に対する姿勢や態度を評価する方法です。
数値化できない部分の評価に向いている方法ですが、定量化できないため評価者の主観が反映されやすいのが注意点です。客観的に評価するために、一定の評価項目を設定する必要があります。

人事評価制度にはさまざまな種類の評価方法があります。
ここでは5つの代表的な評価制度をご紹介するので参考にしてみてください。
会社によって、単独で運用する場合と、複数の手法を組み合わせて運用する場合があります。
自社に合った手法を選び、正しい方法で評価するために、主な評価制度を理解しておくようにしましょう。
それぞれ詳しくみていきましょう。
コンピテンシーは、「業務を遂行する能力や行動特性」を指します。
コンピテンシー評価とは、パフォーマンスの高い従業員に共通する行動特性を評価基準に落とし込み、従業員の評価基準を作成する人事評価制度の手法です。
業績を上げている従業員の行動を観察し、インタビューなどを通して、行動や思考の傾向を調査・分析します。
コンピテンシー評価により、企業が求める人物像や明確な組織目標が明示されるため、従業員の意識を高めることが期待されるでしょう。
従業員が持つ能力を客観的に評価できることから、人事評価の3つの評価基準のうち、「能力評価」に向いています。
MBOとはManagement by Objectivesの略で、直訳すると「目標管理制度」となります。1954年にP.F.ドラッカーが著書「現代の経営」で提唱した組織マネジメントの理論で、経営目標や部門目標を踏まえて個人目標を設定し、目標の達成度を評価する手法です。
年間売上などの目標を全社的に部門目標に分け、さらに個人目標に落とし込むのがMBOの特徴です。
360度評価とは、上司・部下・同僚など、社員に関係するさまざまな立場から多画的に評価を行う手法です。
基本的に人事評価というと上司がおこなうものが一般的ですが、360度評価では異なる立場の複数人からの評価や意見を反映させます。
客観性や公平性を保った公正な人事評価を行うことが可能になり、それにより評価に対する社員の納得感も高まります。
ノーレイティング(No Rating)とは、ランクづけをしない人事評価制度の手法です。
一般的な人事評価制度では、一定期間で上司がフィードバックを行う手法になりますが、ノーレイティングはリアルタイムで人事評価をするのが大きな違いです。
ランク付けをされないことで、従業員のモチベーション低下を防止し、個性や多様性を認めた評価を期待できるため、社員の成長を促し即座にモチベーションをアップさせることができます。
変化が激しい現代に合った評価手法といえるでしょう。
注意点として、ノーレイティング評価を導入する際にはリアルタイムフィードバックや1on1面談などを併用するため、評価者である上司と部下の密なコミュニケーションが最重要になります。
ノーレイティングを採用している代表的な企業としては、GoogleやMicrosoft、GE、GAP、アクセンチュアなどがあります。
OKRはObjectives and Key Resultsの略で、「目標と成果指標」と直訳されます。
米国のインテル社が開発した目標管理手法で、組織としての目標設定を部門単位へ、さらに部門単位から個人単位まで落とし込み、最終的に企業の目標達成を実現することが目的です。
OKRは前述のMBOと比較されることが多く、MBOで設定する目標が努力すれば達成可能なため達成度100%を目指すのに対し、OKRでは高い目標設定をすることに意味があるとした制度です。
OKRでは達成基準は60~70%に設定されるのが一般的で、社員の育成や企業全体の生産性向上を目的としているという違いがあります。
人事評価制度は、組織目標達成や人材育成にも大きく関わる重要な仕組みです。
多角的に従業員を評価するには、人材情報の把握はもちろん、評価基準の明確化、育成計画や現場での目標管理や定期的なフィードバックの実施も必要になります。
これからタレントマネジメントの仕組み化・見直しをお考えの方には、タレントマネジメントシステムの活用がおすすめです。
人事評価ツールNewton(ニュートン)は、社員教育や給与水準に対しての課題や、スキル・マネジメント・スタンスなど個人の評価が見やすく、多くの情報をひと目で確認できます。
また独自のシステムにより、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な仕様が特徴です。
単独の評価者では評価にムラができやすいですが、複数人による多画的な評価をデータで自動取得できることにより納得度も高まるでしょう。(※特許取得済)
いつでもどこでも入力が可能なので手軽に導入しやすい点も喜ばれています。
人事評価制度により組織・企業の成長に繋がる人材育成を実現したいとお考えの方は、ぜひニュートンをご活用ください。
人事評価制度は、従業員の役職や職位、報酬などの処遇を決定する際の指標となるもので、従業員のモチベーションを左右する重要な制度です。
そのため、自社にあった適切な制度を構築し、運用していく必要があります。
適切な人事評価制度を構築するためには、評価項目の設定がポイントとなります。
インターネットを検索すればさまざまな評価シートのサンプルが手に入りますが、業種や職種、役職、職位にあった評価項目でなければ意味を成しません。
また、自社の経営理念や行動指針を評価制度に反映させていくことも大切なポイントです。
当記事では、人事評価の項目や具体的な評価基準、人事評価制度運用のポイントを解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
人事評価制度とは、従業員の能力や業績、意欲、勤怠などを客観的な指標によって評価し、役職や職位、報酬などの処遇の決定に反映させるための制度です。
人事評価制度は、以下の3つの要素で成り立っています。
3つの要素は互いに影響し合い、1つの制度に変更が生じると、他の2つの制度にも影響を及ぼします。
それぞれの詳細を解説します。
評価制度とは、組織目標に対する従業員の貢献度合いを客観的な基準によって評価するための制度です。
評価の項目や方法、評価基準は企業によって異なるため、どのような行動や姿勢が高い評価につながるのか、従業員にしっかり周知することが大切です。
等級制度とは、職務や成果、スキルなどに応じた等級を設定し、従業員の序列を決めるための制度です。
等級は、従業員がキャリアパスを描くうえで重要な指針となります。
また、等級は報酬に直結するため、従業員の関心が高い要素でもあります。
報酬制度とは、等級や評価を報酬に反映する際に用いる制度のことです。
評価制度や等級制度が整っていても、それが報酬制度に反映されなければ従業員のモチベーションは上がらないでしょう。
評価制度および等級制度とのバランスがポイントとなります。
人事評価制度を考えるうえで理解しておくべき事項として、相対評価と絶対評価の違いがあります。
「相対評価と絶対評価はどちらがよいか」といった議論になることがありますが、それぞれメリット・デメリットが存在します。
なお、日本においては相対評価が主流でしたが、近年では労働環境の変化に伴い、個人の成長に目を向ける傾向が高まり、絶対評価を取り入れる企業が増えています。
相対評価とは、所属する組織内の他者との比較によって評価する方法です。
たとえば、A~Eの5段階で評価をつける場合、AとEは10%、BとDは20%、Cは40%とあらかじめ枠を決めておき、従業員を枠にあてはめていきます。
従業員同士を比較し、決められた枠に振り分けていく手法のため細かな評価基準を定める必要がなく、評価者の個人的な主観も入りにくい点がメリットです。
一方で、職務に精通している従業員が高い評価を得やすく、新入社員のような経験の浅い従業員は高い評価を得にくいため、個人の成長につながりにくい点がデメリットといえるでしょう。
絶対評価とは、あらかじめ定めた評価基準に照らし合わせて従業員を評価する手法です。
たとえば、評価基準に対して120%以上の達成度ならA、100%ならBといった具合に評価ランクを設定します。
もし、すべての従業員が120%の達成度であった場合、全員がA評価となります。
絶対評価のメリットは、従業員個々の達成度に応じて評価が決まるため、評価に対する納得感が得やすい点です。
また、自分自身に不足している点や課題も発見しやすいため、個人の成長へつながっていきます。
一方で、相対評価と比較すると評価基準を定めることが難しい点がデメリットです。
簡単に達成できる評価基準を設定してしまうと全員が最高評価となってしまったり、難しすぎる場合は誰も最高評価を得られず従業員のモチベーションが下がってしまうリスクがあります。
また、絶対評価はプロセスではなく結果で判断するため、外的要因によって目標達成できなかった場合でも低い評価にせざるを得ないといった側面もあります。

人事評価の項目は、以下の3つに分けられます。
それぞれの詳細を解説します。
業績評価は、「期初に定めた目標を期間内にどのくらい達成できたか」が評価基準となります。
「業務目標の達成度」と、業務目標を達成するために必要な課題の達成度を示す「課題目標達成度」の2つに基づいて評価します。
評価の際は定量的な成果だけでなく、定性的なプロセスも含めて評価対象とするケースが多くあります。
能力評価は、「業務の遂行にあたって必要な能力がどのくらい備わっているか」が主な評価基準となります。
具体的には、企画力や実行力、改善力などがあげられます。
他にも、リーダーシップやリスクマネジメント力など、役職や職位、部署によって必要な能力が異なります。
顧客対応部門の場合は、クレーム対応も評価項目に含める場合があります。
業績評価が数値などの客観的な基準に基づくのに対し、能力評価は日ごろの行動や発言などを評価するため、評価者の主観に影響される点が特徴です。
情意評価とは、「勤務態度や業務への意欲の高さ」が主な評価基準となります。
情意評価は業績評価や能力評価とは異なり、従業員の人間性を評価できる項目として価値がありますが、評価自体が難しいことや能力評価と同様に評価者の主観に左右されるため、これまであまり重視されてきませんでした。
しかし、情意評価は「成果絶対主義からの脱却」という重要な役割を担っています。
情意評価は短期的には大きな効果は見込めないかもしれませんが、長期的な目線で企業の人材育成を考えるうえで、大切なポイントとなります。
情意評価は以下の4つの項目に分けられます。
それぞれの詳細を解説します。
規律性とは、「遅刻や欠勤をせず、決められたルールに沿う行動ができているか」、「勤務態度に問題はないか」など、組織の基本的なルールを守れるかを問う項目です。
規律性を評価対象とすることにより、組織全体の規範意識の向上が期待できます。
一方で、規律性は評価者の主観が入りやすい項目であるため、評価基準に公平性を持たせることが大切です。
責任感とは、自分に与えられた業務を最後まで責任を持って遂行する姿勢を問う項目です。責任感は、将来のリーダー候補を育成するうえでも指標となる大切な項目です。
責任感の評価基準を明確化することで、人材育成や人員配置に役立てられます。
積極性とは、仕事に対する能動的な姿勢を評価する項目です。
積極性に優れた人材は個人として高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、組織全体にもプラスの影響を与えます。
積極性の項目は、「経験のない事例に対しても物怖じせず取り組めるか」、「自分の長所を生かし、業務に反映させる工夫をしているか」などさまざまな指標が考えられるため、評価基準を明確にする必要があります。
協調性とは、「周囲と協力関係を築きながら1つの物事に取り組めるか」、「組織目標やビジョンに沿う行動ができるか」などを評価する項目です。
必要に応じて他のメンバーに力を貸したり、他部門の従業員とも良好な関係を築けるかといった点も協調性に含まれます。

職種や役職、職位によって求められる能力が異なるため、業績評価および能力評価の評価項目はそれぞれに合ったものを設定する必要があります。
例として、営業職・事務職・管理職の評価項目を紹介します。
営業職は数値目標を重視するため、業績評価がしやすい職種です。
売上数や売上金額、顧客獲得数などを業績評価の評価基準にするとよいでしょう。
能力評価においては、商談時の企画力や実行力、交渉力などが重視されます。
他にも、コミュニケーション能力やスケジュール管理能力なども大切な要素です。
| 評価基準 | 評価項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標の達成度 |
| 課題目標達成度 | 業務目標達成のために必要な課題の達成度 | |
| 能力評価 | 企画力 | 顧客に対して価値ある提案ができたか |
| 実行力 | 目標達成に向けた行動量は適切であったか | |
| 交渉力 | 顧客とのスムーズな合意形成に至ることができたか | |
| 改善力 | 自主的に業務改善に取り組んだか | |
| コミュニケーション力 | 顧客や社内のメンバーとのコミュニケーションは円滑であったか | |
| スケジュール管理能力 | 自ら定めたスケジュールに沿う行動ができたか |
事務職は営業職と比較するとルーチンワークの比率が高いため、業績目標を設定しにくい職種です。
「現在5営業日要している業務を効率化し、3営業日に短縮する」、「上半期までに事務マニュアルを完成させる」など、業務の効率化や納期を業績評価の評価基準にするとよいでしょう。
能力評価については、ルーチンワークの特性上、正確性やスケジュール管理能力が求められます。
他にも、給与計算や労務管理、経理業務で重要な専門知識やコスト意識なども必要な要素です。
| 評価基準 | 評価項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標の達成度 |
| 課題目標達成度 | 業務目標達成のために必要な課題の達成度 | |
能力評価 |
改善力 | 自主的に業務改善に取り組んだか |
| 正確性 | ミスなく正確に業務を遂行できたか | |
| スケジュール管理能力 | 自ら定めたスケジュールに沿う行動ができたか | |
| 専門知識 | 業務に必要な専門知識を習得しているか | |
| コスト意識 | コスト意識を持ち、コスト削減に寄与したか | |
| コミュニケーション力 | 円滑なコミュニケーションをとりながら業務遂行できたか |
管理職は、チームや部署全体の目標の達成度合いが業績評価の重要な評価基準となります。そのため、目標設定の段階でチームや部署単位の業績目標を設定します。
能力評価については、企画力や実行力に加えてリーダーシップやリスクマネジメント力、部下に対する指導・育成能力などが求められます。
また、経営方針や組織目標を部下に伝え理解を促す役割も担っており、幅広い評価項目が必要です。
| 評価基準 | 評価項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標の達成度 |
| 課題目標達成度 | 業務目標達成のために必要な課題の達成度 | |
能力評価 |
企画力 | 顧客や組織に対して価値ある提案ができたか |
| 実行力 | 目標達成に向けた行動量は適切であったか | |
| 改善力 | 自主的に業務改善に取り組んだか | |
| リーダーシップ | リーダーシップを発揮し、組織をまとめられたか | |
| リスクマネジメント力 | 予想されるリスクへの対応は適切であったか | |
| 部下指導・育成 | 部下の成長に寄与したか | |
| 組織目標の理解と促進 | 組織目標や経営方針を部下へ伝え、理解を促したか | |
| マネジメント力 | スケジュール管理やコスト管理を含め、総合的なマネジメント力は備わっているか | |
| コミュニケーション力 | 管理職に必要なコミュニケーション力が備わっているか |

人事評価にはさまざまな手法が存在します。
従来の日本では、年功序列で役職や職位、報酬などの処遇が決まることが一般的でしたが、人材の流動化や働き方の多様化をはじめとする環境変化に伴い、評価方法も変化しています。
代表的な人事評価の手法は、以下の4つです。
それぞれの特徴を解説します。
MBO評価は「目標管理制度」とも呼ばれ、組織の目指す方向性と従業員個々の目標やビジョンをすり合わせ、効率的な目標達成を支援するマネジメント手法のことです。
MBO評価の特徴は、従来の目標管理とは異なり、従業員自らが目標を定め自主的に行動し、その達成度で評価を受ける点です。
従業員の自主性やモチベーションアップにつながり、結果として組織の生産性向上など、多くの効果が期待できるといわれています。
MBO評価と混同されがちな評価手法としてOKR評価があります。
OKR評価とは、組織の目標と従業員個々の目標をリンクさせ、従業員が一丸となって同じ方向を目指して行動することで目標達成を目指すマネジメント手法のことです。
MBO評価とOKR評価の大きな違いは、人事評価への反映の有無です。
MBO評価は設定した目標を100%達成することを目指し、結果を人事評価へ反映させますが、OKR評価は設定することで組織全体を活性化することを目的としているため、結果が人事評価へ反映されることはありません。
コンピテンシー評価とは、仕事で高い成果をあげている人の行動特性を評価基準に取り入れた評価手法のことです。
従業員の中でパフォーマンスの高い人材をモデル化したり、企業の経営方針や戦略を基にモデル像を設定し、評価基準を細かく定めていく点が特徴です。
個人の能力だけでなく「高い成果をあげている人がどのような行動をとっているか」に着目して評価基準へ反映させるため、人材育成の面で高い効果を発揮します。
360度評価とは、上司だけでなく同僚や部下、他部門の関係者などさまざまな立場の人から評価を得る手法のことです。
あらゆる角度から評価されるため、「多面評価」とも呼ばれます。
上司だけからの評価と比較すると多面的かつ多様な意見が得られるため、自分自身では気づけない長所や短所を知るきっかけとなります。
客観性や公平性に優れた評価手法といえるでしょう。
人事評価を効果的に行うポイントは、以下の4つです。
それぞれについて詳しく解説します。
経営理念や行動指針は掲げているだけでは意味を成しません。
積極的に人事評価に反映させることで、理念や指針を従業員に浸透させることにつながります。
評価基準や結果を書き込む評価シートは、全員が一律のものを使用するのではなく、業種や職種、役職や職位によって使い分ける必要があります。
営業職は数値目標が明確なため業績評価がメインになりますが、事務職では能力評価や情意評価のウェイトが高いなど、それぞれ求められるものが異なるためです。
新入社員向けに積極性や協調性のウェイトを高めた評価シートを作成するなど、年次によって使い分ける方法もあります。
評価シートは一度作成したら終わりではなく、適宜見直し・整理をはかり、最適な状態を保つことが大切です。
人事評価は、従業員がよりよいパフォーマンスを発揮するための指針となるものです。
上司から部下に対するフィードバック面談の機会を設けることは、大切なステップの1つです。
面談では、評価の理由と、良かった点・改善が必要な点について伝えるとともに、今後に向けての意見のすり合わせをします。
適切なフィードバックにより、部下のやる気を引き出せる可能性があります。
人事評価システムとは、これまで人事担当者がおこなっていた人事評価業務に不随する業務を自動化できるシステムです。
人事評価シートを自動作成・管理できるだけでなく、客観的なデータ分析による評価基準の設定や従業員のスキル管理、評価の実施、評価結果の管理などを一元的に行うことができます。
ニュートンは、自社にあった柔軟な人事評価制度の設計を実現させるクラウド型人事評価システムです。
後回しになりがちな評価項目の見直し・整理や更新が簡単にできるため、常に最適な評価制度が保たれます。
評価情報は管理者が一元的に管理できるため、これまで人事評価業務に要していた工数を大幅に削減可能です。
煩雑でミスが発生しやすい集計業務もニュートンを活用すれば瞬時に完了します。
人事評価制度の構築や運用に課題を抱えている場合は、ぜひクラウド型人事評価システムニュートンの導入をご検討ください。