人事評価の結果を聞いて、「どうしてこの評価なんだ」「自分の頑張りが全く認められていない」と、強い不満や疑問を感じていませんか。
上司からのフィードバックは曖昧で、評価の根拠もよくわからない。
そんな状況では、仕事へのモチベーションが下がり、このまま会社にいて良いのかと不安になるのも当然です。
この記事では、人事評価に納得いかないあなたのモヤモヤした気持ちを整理し、後悔しないための具体的なアクションを解説します。
感情的に行動して損をする前に、まずはこの記事を読んで冷静に状況を分析し、あなたにとって最善の道を見つけるための一歩を踏み出しましょう。

人事評価に不満を抱くとき、その原因は一つではないことがほとんどです。
「納得いかない」という感情の裏には、いくつかの典型的な問題が隠されています。
まずは、あなたの不満がどのパターンに当てはまるのかを客観的に見つめ直してみましょう。
原因を特定することが、解決への第一歩となります。
「何を達成すれば評価されるのか」が明確に示されていないケースです。
評価項目が大まかすぎたり、部署や評価者によって基準が異なったりすると、従業員は不公平感を抱きやすくなります。
例えば、営業部門では数値目標が重視される一方、管理部門では評価基準が曖昧といった状況です。
これでは、自分の努力が正しく評価に結びついているのか分からず、納得するのは難しいでしょう。
本来、評価は客観的な事実に基づいて行われるべきです。
しかし、実際には評価者である上司の主観や、個人的な好き嫌いが影響してしまうケースは少なくありません。
「ハロー効果」と呼ばれる、一つの良い点(または悪い点)に引きずられて全体の評価を決めてしまう心理的なエラーもその一例です。
上司と個人的に親しい同僚が優遇されているように感じるなど、実績以外の要因が評価を歪めている可能性も考えられます。
あなたは自分の成果や日々の努力を十分にアピールできているでしょうか。
多くの場合、上司は部下一人ひとりの業務内容を完璧に把握しているわけではありません。
自己評価シートに書ききれない細かな改善や、チームへの貢献などが評価者に伝わっていなければ、自己評価との間に大きなギャップが生まれてしまいます。
これはあなたの能力不足ではなく、コミュニケーションや報告の仕方に課題があるのかもしれません。
評価面談で、ただ結果だけを伝えられて終わってしまった経験はありませんか。
なぜその評価になったのかという具体的な理由や、次に向けて何を改善すればよいのかという建設的なフィードバックがなければ、評価を受け入れることは困難です。
一方的な通告は、あなたが成長する機会を奪うだけでなく、会社への不信感を増大させる原因にもなります。
評価は、あなたの成長を促すための対話であるべきです。
| 原因カテゴリ | 具体的な状況の例 | 読者が感じる不満 |
|---|---|---|
| 評価基準の曖昧さ・不公平 | – 目標設定が具体的でなく、達成基準が不明確 – 部署やチームによって評価の厳しさが違う – 結果だけでなくプロセスも評価してほしいのに、その基準がない |
「何を頑張ればいいのかわからない」「隣の部署は楽そうで不公平だ」 |
| 評価者の主観・人間関係 | – 上司の個人的な好みで評価が左右されている気がする – 特定の社員だけがいつも高く評価される – 最近の失敗だけを過大に評価された(直近誤差) |
「上司に気に入られないとダメなのか」「仕事の実力より人間関係が大事なのか」 |
| 成果・プロセスの未伝達 | – 自己評価でアピールした内容が、上司に理解されていない – 目に見えにくい貢献(他部署との連携、後輩の指導など)が評価されていない – 多忙な上司が、自分の働きを普段から見てくれていない |
「あんなに頑張ったのに、伝わっていない」「結果しか見られていない」 |
| フィードバックの不十分さ | – 評価面談で評価ランクを告げられただけで、具体的な説明がなかった -「もっと頑張れ」といった抽象的な指摘しかされない – 次の目標設定に向けた具体的なアドバイスがない |
「なぜこの評価なのか理由がわからない」「改善しようにも、どうすればいいか不明だ」 |

評価への不満をそのまま上司にぶつけてしまうのは、最も避けるべき行動です。
感情的な態度は、あなたの主張の正当性を弱め、「ただ文句を言っているだけ」と捉えられかねません。
冷静かつ論理的に対話するためには、事前の準備が不可欠です。
事実に基づいた主張を組み立てることで、あなたの話に説得力が生まれ、状況を好転させる可能性が高まります。
面談の場で頭が真っ白にならないよう、事前に聞きたいことをリストアップしておきましょう。
感情的な言葉ではなく、客観的な事実と未来の行動指針を引き出すための質問を準備することが重要です。
以下の表を参考に、あなた自身の状況に合わせた質問リストを作成してみてください。
| 質問の目的 | 質問リストの具体例 |
|---|---|
| 評価理由の明確化 | – 今回の評価(例:B評価)に至った具体的な理由を教えていただけますか。 – 特に、どの点が評価のマイナス(またはプラス)要因となったのでしょうか。 |
| 自己評価とのギャップ確認 | – 私が自己評価でAとつけた「〇〇のプロジェクト」について、どの点が目標未達と判断されたのか、具体的に伺えますか。 |
| 今後の行動指針の確認 | – 次回の評価で最高評価(S評価)を得るためには、具体的にどのような行動や成果が求められるでしょうか。 – 評価基準について、私の認識と相違がないか、改めてすり合わせをさせていただきたいです。 |
「頑張りました」という主観的なアピールでは、相手を説得することはできません。
あなたの貢献度を、誰が見ても理解できる客観的な事実や数値で示すことが重要です。
期間、目標、具体的な行動、そしてその結果どうなったのかを整理しましょう。
以下のシートを参考に、あなた自身の実績を棚卸ししてみてください。
| 項目 | 記入例 | あなたの場合 |
|---|---|---|
| 評価期間 | 2024年4月1日~2024年9月30日 | |
| 担当業務 | 〇〇プロジェクトのリーダー | |
| 設定された目標 | プロジェクトの売上を前年同期比10%向上させる。 | |
| 具体的な行動 | – 新規顧客開拓のため、テレアポリストを再構築し、月50件の新規アポイントを獲得した。 – 既存顧客向けにアップセル提案資料を作成し、チーム内に展開した。 – 週1回の進捗会議を主催し、課題の早期発見と解決に努めた。 |
|
| 結果(数値) | – 目標10%に対し、売上を15%向上させた。 – 提案資料を活用した結果、チーム全体のアップセル受注率が5%改善した。 |
|
| 会社への貢献 | 目標達成により、部署全体の売上目標達成に貢献した。 |
不満を伝えるだけで終わらせず、次回の評価に向けた前向きな対話に繋げることができれば、上司のあなたに対する見方も変わるはずです。
過去の評価を覆すことだけを目的とせず、「どうすれば次はもっと高く評価されるのか」という未来志向の姿勢で臨みましょう。
この姿勢は、あなたが自身のキャリアに真剣であり、会社に貢献したいという意欲の表れとして、ポジティブに受け取られる可能性が高いです。
上司を「評価する側」と「される側」という対立構造で捉えるのではなく、「共に目標達成を目指すパートナー」として巻き込むことを目指しましょう。

準備が整ったら、次はいよいよ行動に移します。
ただし、いきなり人事に駆け込んだり、不服申し立てをしたりするのは得策ではありません。
まずは身近なところから、段階的にアプローチしていくことが重要です。
事を荒立てすぎずに、円満な解決を目指すための3つのステップを紹介します。
最初のステップは、評価者である直属の上司と改めて1on1(1対1の面談)の機会を設けてもらうことです。
準備した「質問リスト」や「自己評価シート」を基に、冷静に対話しましょう。
面談を依頼する際は、「先日の評価について、今後のために詳しくお話を伺いたく、少しお時間をいただけないでしょうか」といったように、あくまで前向きな相談というスタンスで切り出すのがポイントです。
感情的に相手を非難するのではなく、評価の事実確認と、今後の改善に向けたアドバイスを求める姿勢を貫きましょう。
上司との対話で納得のいく回答が得られなかったり、そもそも上司自身が不満の原因であったりする場合には、次のステップに進みます。
多くの企業には、人事部や、ハラスメントなどを相談できる専門の窓口が設置されています。
これらの部署は、従業員と会社の間に立ち、中立的な立場で問題解決をサポートする役割を担っています。
相談する際は、これまでの経緯を時系列で客観的に説明することが重要です。
感情的にならず、準備した資料を見せながら事実を淡々と伝えましょう。
最終手段として、会社の公式なルールである「不服申し立て制度」を利用する方法があります。
この制度は、就業規則や人事評価規程に定められていることが多く、従業員が評価結果に対して正式に異議を唱える権利を保障するものです。
まずは、自社にこの制度があるかを確認しましょう。
制度を利用する際は、定められた書式や手続きに従い、客観的な証拠を添えて申し立てを行う必要があります。
これは会社に対して明確な対立姿勢を示すことになるため、利用する際は相応の覚悟が必要です。
| 相談ステップ | 相談相手 | 目的とポイント | 注意すべきこと |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 直属の上司 | – 評価の真意と具体的な根拠を確認する – 次の目標達成に向けたアドバイスを求める – あくまで「相談」という姿勢で対話する |
– 感情的にならない – 相手を一方的に非難しない – 面談の場で結論を急がない |
| ステップ2 | 人事部・社内相談窓口 | – 客観的な第三者の視点で意見を聞く – 上司との対話で解決しなかった経緯を説明する – 事実を時系列で整理して伝える |
– 匿名での相談が可能か確認する – 相談内容が評価者にどう伝わるかを考慮する – 必ずしも自分の望む解決策が提示されるとは限らない |
| ステップ3 | 不服申し立て制度 | – 公式な手続きに則って評価の再検討を要求する – 就業規則などを確認し、客観的な証拠を揃える – 評価の不当性を論理的に主張する |
– 最終手段と認識する – 会社との関係が悪化するリスクがある – 申し立てが必ず通るとは限らない |

「納得いかない」という感情が強くなると、「この評価は不当で、もしかしたら違法なのでは?」と考えることもあるでしょう。
実際に、単なる厳しい評価の域を超え、法的に問題となるケースも存在します。
ここでは、どこからが「不当評価」と見なされるのか、その境界線について解説します。
冷静に自分の状況を判断するための知識として、ぜひ参考にしてください。
人事評価の裁量権は基本的に会社側にありますが、その権利を濫用したと見なされる場合は違法となる可能性があります。
過去の裁判例などから、違法と判断されやすいのは以下のようなケースです。
これらの主張をするには、メールの文面や面談の録音など、客観的な証拠が極めて重要になります。 [1]
社内での解決がどうしても難しいと感じた場合は、社外の専門機関に相談する道もあります。
一人で抱え込まず、外部の力を借りることも選択肢の一つとして考えておきましょう。
| 相談先 | 特徴 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 労働局(総合労働相談コーナー) | 国が設置する公的な相談窓口。 | – 無料で相談できる – 中立的な立場で助言や情報提供を受けられる – 「あっせん」による和解の可能性がある |
– 法的強制力はない – 会社が話し合いに応じない場合もある – あくまで解決のサポート役 |
| 弁護士 | 法律の専門家。 | – 法的観点から具体的な解決策を提示してくれる – 代理人として会社と交渉や訴訟を行える – あなたの権利を守るための強力な味方になる |
– 相談料や着手金などの費用がかかる – 依頼する弁護士によって得意分野が異なる – 裁判になると時間と労力がかかる |

社内で解決に向けて努力したものの、状況が改善されないこともあるかもしれません。
その場合は、あなたの貴重なキャリアを守るために、環境を変える、つまり「転職」という選択肢を真剣に考えるべきタイミングです。
感情的な勢いで退職を決めるのではなく、客観的なサインを見極めて判断することが重要です。
ここでは、今の会社を見限るべき3つのサインを解説します。
あなたが誠実に対話を求め、具体的なデータを示して相談しても、会社や上司が全く取り合ってくれない。
「会社のやり方だから」「不満があるなら辞めてもいい」といった態度で、制度や運用を見直す姿勢が全く見られない。
このような場合は、残念ながらあなたの力で状況を変えるのは極めて困難です。
組織の文化や個人の価値観は簡単には変わりません。
消耗し続けるよりも、あなたの努力を正当に評価してくれる新しい環境を探す方が賢明です。
人事評価への不満が強いストレスとなり、眠れない、食欲がない、仕事に集中できないといった状態が続いていませんか。
それは、あなたの心と体が発している危険なサインです。
仕事の評価も大切ですが、あなた自身の健康は何物にも代えがたい財産です。
心身に不調をきたしてまで、しがみつくべき仕事はありません。
自分を守ることを最優先に考え、休職や転職を真剣に検討しましょう。
今回の評価問題をきっかけに、会社の求める人物像や今後の事業方針と、あなたが思い描くキャリアプランとの間にズレがあることに気づくかもしれません。
それは、実は転職を考える絶好の機会と捉えることもできます。
会社に評価されることだけが目的ではありません。
あなたがプロフェッショナルとしてどのように成長していきたいのか、どんなスキルを身につけたいのか。
そのビジョンを実現できる環境を、自ら主体的に選んでいくことが大切です。
| 転職を考えるべきサイン | チェックリスト |
|---|---|
| 会社・上司の姿勢 | □ 対話を求めても無視されるか、形式的な対応で終わる。 □ 評価制度の見直しについて、具体的な議論や動きが全くない。 □「会社の決定事項だ」の一点張りで、個別の事情を考慮する姿勢がない。 |
| 自身の心身の状態 | □ 仕事のことを考えると眠れない、または夜中に何度も目が覚める。 □ 以前は楽しめていた趣味にも、興味が持てなくなった。 □ 原因不明の頭痛や腹痛、気分の落ち込みが続いている。 |
| キャリアの方向性 | □ 会社の求める役割と、自分が目指すキャリアの間に大きなズレを感じる。 □ この会社で働き続けても、自分の市場価値が高まるとは思えない。 □ 目標としたいと思える上司や先輩が、社内にいない。 |

人事評価に納得できないという経験は、非常につらく、仕事への意欲を失わせるものです。
しかし、この出来事をあなたのキャリアを見つめ直すための重要な機会と捉えることもできます。
まずは、感情的にならずに、なぜ不満なのかを客観的に分析し、事実に基づいた証拠を揃えましょう。
その上で、上司や人事部と冷静に対話し、段階的に社内での解決を目指すことが重要です。
もし、それでも状況が改善されず、会社に未来がないと感じたならば、あなたの価値を正しく評価してくれる新しい環境を求めて、転職という選択肢を前向きに検討してください。
今回の辛い経験は、あなたがより良いキャリアを築くための、きっと大きな一歩になるはずです。

「人が辞めないお店にしたい」
「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」
「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」
そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。
ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。
アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。
明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現
評価結果を元にしたフィードバックでモチベーションアップ
昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる
現場でも使いやすい画面と運用設計
管理職の“感覚評価”から脱却し、組織力が底上げされる
制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。
人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?
「OKR(Objectives and Key Results)」は、近年ビジネス界で注目を集めている、組織全体で効果的に目標を達成するための目標設定・目標管理のフレームワークで、Googleやインテルなどの有名企業をはじめとして、多くの企業で採用されています。
OKRを導入することで従業員の意欲を高めることができるといったメリットが存在するため、人事評価制度の改定を検討する際にはOKRの導入が選択肢に挙がるケースも多いでしょう。
本記事では、OKRの基本と、導入・運用する際に人事評価と連動させるメリットデメリットを紹介します。
他の目標管理制度との併用や実際の企業における事例も解説するので、ぜひ参考にしてください。
OKRは、「Objectives and Key Results」の略称で、業績評価制度の一つです。
目標設定と成果の管理のフレームワークを指します。
組織や個人が目指す目標(Objective)と、それを達成するための定量的な成果達成指標(Key Results)を定めて、進捗を追いながら成果を上げていく方法で、この2つの要素をもとにして業績を評価し、進捗を定期的に確認・改善していきます。
具体的には、OKRは以下のように業績評価に活用されます。
OKRは定期的に見直し・更新されることが多く、特に成長を重視する企業やチームでよく使われます。
業績評価制度として個人やチームの成果を明確にし、全体の目標と個々の貢献度を一貫性を持って管理できるため、目標達成に向けた動機づけや効率的な成果向上が期待されます。
OKR(Objectives and Key Results)の目的は、「組織やチーム、個人が明確な目標に向かって一貫して努力し、その進捗を測定しながら成果を最大化すること」です。
目標を明確にし、進捗と貢献度を定期的に評価することで、成果を最大化し、組織や個人の成長を促進することです。
主なメリットは以下のとおりです。
具体的に解説します。
OKRは、組織全体で共有する目標を明確に定めることで、全員が同じ方向に一丸となって進むように促すことができます。
これにより、個々の役割がどのように全体目標に貢献しているのかがわかりやすくなります。
「Key Results(重要な結果)」を数値や具体的な成果基準で設定することで、進捗を客観的に可視化して測定することができます。
数値で成果を測るため、達成度を明確に把握しやすく、改善が必要な点を早期に発見し、迅速な対応が可能になります。
OKRでは、単に「達成可能な目標」ではなく、挑戦的で意欲を引き出すようなチャレンジングな目標(Objective)を設定します。
この挑戦的な目標によって、組織やチームの成長を促進し、イノベーションを生み出す原動力になります。
OKRは、定期的に進捗を共有し、フィードバックをおこなうことで、組織・職場内のコミュニケーションを活性化させることも目的です。
OKRは通常、組織全体で共有されるため、誰がどのような目標に取り組んでいるのかが明確になります。
上司と部下で目標と成果を共有することで、組織内の透明性が高まり、協力や連携が促進され、納得感も高まります。
OKRは、限られたリソースで最大の成果を上げるために、最も重要な目標に集中することを促します。
これにより、組織が効率的に動き、重要な成果にフォーカスできるようになります。
OKRは四半期ごとに設定され、進捗を評価した後、次のサイクルで改善点を反映させることができます。
この柔軟な調整によって、環境の変化や新たな課題に対応することが可能です。

OKRと人事評価制度(MBOやKPI)は、目標設定と業績評価の手法として似た点もありますが、アプローチや目的が異なります。
ここからは、以下の関係性についてまとめます。
詳しく見ていきましょう。
MBO(目標管理制度)とは、「Management By Objectives」の略で、直訳すると「目標による管理」のことです。
MBOは、主に個人やチームの目標を達成することに焦点を当てた制度で、目標達成度に基づいて評価をおこないます。
OKRも目標を設定する点では似ていますが、MBOは目標設定と評価が「トップダウン型」であることが多く、目標達成度の評価基準が比較的固定的で、結果に対して報酬や昇進が直接リンクすることが一般的です。
一方、OKRは、目標設定のプロセスが柔軟で、挑戦的な目標を設定し、達成度を数値化して進捗を管理します。
OKRは、通常、「組織全体やチームの目標と個人の目標をリンクさせる」ことを重視し、組織全体の方向性を共有する点が特徴です。
また、OKRでは「達成度が100%でなくてもOK」とされ、挑戦的な目標に対して高い達成度を目指し、失敗から学ぶ文化を促進します。
KPI(重要業績評価指標)は、特定の業務やプロジェクトのパフォーマンスを測るための指標であり、主に成果を定量的に評価するために使用されます。
OKRにおける「Key Results」に似ていますが、KPIは通常、具体的な「業務の達成度を測定」するものです。
OKRの「Key Results」はKPIより広範で、挑戦的な目標を支援するための指標となります。
OKRにおけるKey Resultsは、KPIよりも「目標達成のプロセス」に焦点を当てており、必ずしも数値目標だけではなく、成果に焦点を当てます。
そのためOKRは、KPIよりもより高い視点から目標を設定し、組織のビジョンや戦略に基づいた大きな目標を達成するための道筋を示しています。
MBOやKPIが業績評価に直結し、成果主義的な評価を強調するのに対して、OKRは評価だけでなく、学びと成長の過程を重視します。
OKRでは、目標を達成しなくても進捗が評価されることがあり、失敗や挑戦から得られる学びを重視します。
また、OKRは通常、四半期単位で評価され、進捗に合わせて目標や戦略を柔軟に調整できます。
そのため、OKRと人事評価や報酬は切り離すべきという考え方もあります。
これに対し、MBOやKPIは年単位で設定されることが多く、そのため変更が少なく、評価が比較的固定的です。

OKRと人事評価を連動させることには、組織の目標達成を支援するだけでなく、社員のモチベーションや成長を促進する効果も期待できるというメリットがありますが、一方でデメリットやリスクもいくつか存在します。
また評価の公平性や柔軟性を欠く可能性があります。
OKRと人事評価を連動させた場合のメリットは以下のとおりです。
詳しく解説します。
OKRと人事評価を連動させることで、組織全体の目標と個人の評価基準を一致させ、全員が同じ方向に向かって努力することができます。
これにより、目標の達成度が明確になり、組織の戦略と個人の貢献が一貫して評価されるため、成果が上がりやすくなります。
さらに個人の目標と組織の目標がリンクし、目標達成のために具体的にどのようなアクションが必要かが明確になります。社員は自分の役割を理解しやすくなり、評価に向けた具体的な行動計画を立てやすくなるでしょう。
OKRに基づいて人事評価を行うと、目標に対する成果が評価基準になるため、成果主義が強化されます。
達成した目標に対して報酬や昇進などのインセンティブが結びつくことで、社員のパフォーマンス向上が期待できます。
OKRは四半期ごとに見直され、進捗を確認しながら目標の調整が可能です。
この柔軟性を人事評価に組み込むことで、中間評価や定期的なフィードバックを通じて、社員は自分の進捗を把握し、必要な改善を早期に行うことができます。
評価が年に一度だけでなく、定期的に行われるため、成長が促進されます。
またOKRは、環境の変化に応じて目標を見直すことができるため、組織の状況や市場の変化に対応しやすくなります。
社員は変化に適応しやすくなり、組織全体の対応力が高まります。
OKRと人事評価を連動させた場合のデメリットは以下のとおりです。
詳しく解説します。
OKRは、挑戦的で野心的な目標を設定することが一般的であるため、社員が達成できない目標に対するプレッシャーを感じることがあります。
特に、OKRの達成度が直接的な昇進や報酬に結びつく場合、目標未達成に対する心理的負担が大きくなり、モチベーションの低下の原因となることがあるでしょう。
OKRの目標設定が過度に挑戦的である場合、社員が不公平感を抱くことがあります。
例えば、各部署やチームで目標設定の難易度に差がある場合、あるチームは容易に目標を達成できても、別のチームは不可能に近い目標を設定されることもあります。
このような不均衡が評価に反映されると、社員間で不満や不公平感が生まれる可能性があります。
OKRが人事評価に密接に関連していると、社員が評価に過度に依存するようになり、「どう評価されるか」を最優先に考えてしまうことがあります。
これが過剰になると、社員が自分の成長や学びよりも、評価されることにのみ焦点を当て、結果として自己成長や本質的な成果の追求が疎かになる可能性があります。
また、結果主義の強化の影響により、社員は「目標を達成することが最優先」となりがちです。
過程や方法論よりも結果だけが重視され、不正行為や短期的な対策(例:目標達成のために不正確な手段を取る、他の人の成果を奪うなど)を招くリスクがあったり、組織の長期的な戦略や文化が疎かになることもあるでしょう。

OKR(Objectives and Key Results)の導入事例は、特に成長志向の企業やイノベーションを推進している企業で多く見られます。
代表的な導入事例2社について、目的・特徴・成果ごとに紹介します。
GoogleはOKRの最も有名な導入事例です。
創業者は、インテルの元CEOであるアンディ・グローブからOKRを学び、Googleに導入しました。
Googleでは、OKRを使って、組織全体の目標を共有し、社員に明確な方向性を示すことを重視
OKRを導入することで、Googleは迅速な成長を実現し、社員のモチベーションを高め、組織全体でイノベーションを推進する文化を築くことができた。
OKRはもともとIntelで生まれたものであり、創業者のアンディ・グローブが実践的に導入したのが始まりです。
IntelではOKRを使って、成長の方向性を明確にし、会社全体を一貫して進ませるために活用しました。
Intelでは、OKRを使って、社員一人ひとりの目標が会社全体の戦略にどうつながるかを明確にし、組織の一体感を生み出している
IntelはOKRによって、競争力を維持し、革新を続けながら迅速に市場の変化に対応できる組織文化を作り上げた
OKRを導入した企業は、透明性の向上、目標の明確化、モチベーション向上、迅速な意思決定など、多くのメリットを享受しています。
特にGoogleやIntelなどはOKRを効果的に活用し、急成長を遂げました。
OKRは、組織全体の目標達成に向けた一貫した方向性を提供し、社員一人ひとりの成果を具体的に測定できるため、特に成長や変革を求める企業にとって非常に有効な手法となっています。
OKRは短い期間で振り返りをおこなうため、その分労力がかかることがあり、全社的な取り組みが必要になります。
効率的な運用や既存の人事評価制度との併用のためには【システム化】がおすすめです。
ツール導入しシステム化することで、評価の質や納得度が向上し、よりスムーズに人材育成システムの戦略人事に展開し、組織開発の促進につなげることが可能です。
「人事評価ツールNewton(ニュートン)」は各従業員のOKRの設定から、進捗管理と評価までをシンプルに管理できるため、社員一人ひとりの成長をサポートする体制を、評価の公正性や透明性を保ちながら整え、情報を一元管理することができます。
過程やプロセスにも焦点を当てることで、持続的な成長を促進し、社員のエンゲージメントやチームワークの向上にも繋がるでしょう。
Newtonについて詳しく知りたい方はこちら!
人事評価において、従業員を平等に評価し、昇格や昇給、賞与の参考指標にするため「5段階評価」を人事評価に取り入れている企業が増えてきています。
しかし、そんな5段階評価の割合や、評価の仕方について悩まれている方は多いのではないでしょうか。
5段階評価がうまく機能しない場合、正しい評価ができず従業員の不信感を招き、モチベーションの低下や、企業への不満が発生してしまう可能性があります。
また企業にとって導入するメリットがわからないと、活用するまでに至らないケースも多いでしょう。
本記事では、人事評価における5段階評価の基準や割合配分の決め方を解説します。
また、関連する2つの評価方法の特徴やメリット、デメリットについても説明しますので評価担当者はぜひ参考にしてください。
人事評価における「5段階割合」とは、社員や従業員の評価を5段階に分類し、それぞれの評価段階に対応する割合を決定する方法です。
この方法は、個々の従業員の業績や行動をランク付けし、その結果を反映させるために使用されます。
具体的な内容は企業によって異なることがありますが、一般的な評価段階とその割合について説明します。
具体的には以下のような5つの段階を設定するケースが多いでしょう。
5段階評価は古くから活用されている評価手法です。
シンプルでわかりやすいため、今でも多くの企業で採用されています。
5段階評価による評価基準は企業によって異なりますが、ここでは基本の評価基準をまとめました。
評価の際の参考にしてください。
「非常に優れている(S評価)」に該当する従業員は、単に目標達成を超える成果を上げるだけでなく、リーダーシップを発揮し、自己成長を積極的に推進し、チームや会社の模範的な存在として非常に価値のある存在です。
基準の中では最高等級評価に値し、こうした従業員は、組織にとって「模範的」な存在であり、業績や態度において他の社員が目指すべき基準となります。
「期待以上によい(A評価)」という評価は、設定された目標を超えるパフォーマンスを発揮するだけでなく、自発的な成長、問題解決力、チームへの貢献といった複数の要素への取り組みが重要な評価基準となります。
目標達成度が高く、期待以上の成果を上げて基準を満たしているが、S評価に該当するほどの卓越性や革新性がない場合にA評価となることが多いでしょう。
「期待通り(B評価)」は、業務遂行が期待される水準に達しているが、それ以上でもそれ以下でもないという評価です。
この評価を受ける社員は、業務において標準的なパフォーマンスを維持し、目標や基準を満たしているものの、特に目立った成果や優れた貢献があるわけではありません。
評価基準としては「通常通りの期待通り」というレベルに収まり、さらなる成長や改善の取り組みが期待される段階の社員に適用されます。
「C評価(改善が必要)」は、社員の業績や行動が、期待される水準に達していない場合に付与される評価です。
この評価を受ける社員は、業務の成果やプロセスにおいて改善が必要であり、何らかの具体的な問題や課題があると見なされます。
ただし、C評価は必ずしも「最悪」の評価ではなく、改善の余地があるという点で重要です。評価が低い社員に何もフォローをしなければ、不満を抱いて離職につながりかねないため、通常、この評価がつけられた場合、改善プランやフィードバックが提供されることになります。積極的に改善策を講じることが重要です。
「D評価(不適格)業務に支障をきたす」という評価は、社員が業務において重大な問題を抱えており、そのパフォーマンスが周囲・組織にとって深刻な影響を与えていると認識される場合に付けられます。
この評価は、最低評価の一つであり、通常は改善の可能性がほとんど見込めない、または非常に難しい場合に使用されます。
D評価を受けた社員には、組織の業務運営に重大な支障をきたすレベルで深刻な問題が存在しているため、改善の機会を与えられる場合もありますが、その改善が見込めない場合には、より厳しい措置が取られることもあります。

5段階の評価の決め方としては、企業が定める割合で各評価を付与します。
この割合は、企業の方針や評価制度によって異なることがありますが、一般的な配分例としては次の種類があります。
それぞれみていきましょう。
人事評価における「均等配分」とは、全社員の評価を均等に分ける方法を指します。この方法では、各評価ランクに、評価対象者の一定割合(例えば20%)を割り当てることが一般的です。
均等配分の例:
このように、各ランクが評価対象者の全体の中で均等な割合に配置されることが「均等配分」の特徴です。
「均等配分」は、評価結果を均等に分ける方式であり、公平性や客観性を担保し、社員全体のパフォーマンスに均等な分布を求める場合に有効で、各段階の人数が同じであることから、低い評価となった社員は強い劣等感を感じなくて済むのがメリットですが、業績や貢献度に基づく柔軟な評価がしづらくなるというデメリットがあります。
人事評価における「正規分布」とは、評価結果を正規分布に基づいて分ける方法です。
正規分布は、データが中央に集まり、両端に少なくなるという特徴を持つ分布のことを指します。
この方法を人事評価に適用する場合、社員の評価が高評価や低評価に偏ることなく、中央値周辺に多く集まり、両端(優れた社員やパフォーマンスの低い社員)は少数しか分配されないようにします。
正規分布を用いた配分の例:
正規分布の採用は、特に多くの社員が同じような業績を上げている場合や、評価の標準化を重視する場合には有効です。
しかし、企業やチームによっては、業績の差が大きい場合や、特定の社員が群を抜いて成果を上げている場合において、正規分布に基づく評価が適切でない場合もあります。
そのため、その組織の業績や文化に合わせて評価方法を調整することが重要です。

人事評価における5段階割合には、おもに2つの種類があり、評価基準や方法において根本的な違いがあります。
絶対評価は、個人のパフォーマンスや成果を、事前に設定した基準や目標に基づいて評価を決める方法です。
この方法では、社員のパフォーマンスを他の社員と比較することなく、個人の実績や能力を基準に、自分の設定された目標や業務の基準を達成しているかどうかで評価します。
均等配分や正規分布などはおこなわれず、判断されるため、全員がA評価といったこともありえます。
相対評価は、社員を他の社員と比較して評価を決める方法で、個々の業績や成果を、他の社員と比較してランク付けします。
この方法では、社内全体で、相対的にどれくらいの位置にいるか(例えば、最上位、中間、最下位など)を評価の基準とします。
人事評価の2種類の評価方法によって、給与や社員のエンゲージメントにも影響します。メリットやデメリットと合わせて詳しくみていきましょう。
絶対評価は、目標達成度に基づいて最終的な評価が決まるため社員一人一人の評価基準が明確で公平性が高いというメリットがあります。
評価対象者の課題や目標が見えやすいため、上司も部下に対するアドバイスがしやすくなり、結果を出した場合は正当な評価がされるため、仕事へのやる気にもつながるでしょう。
所属する部署や年功序列制度、勤続年数が評価には影響しないことや、事前に決められた基準によって評価が判断されるので、評価内容に不明瞭な点がないのが特徴であり大きなメリットです。
絶対評価のデメリットには、評価基準設定の難しさがあげられます。
基準が厳しすぎると多くの社員が目標を達成できず、低すぎても達成が簡単になり社員の成長につながりません。
目標が曖昧だったり過度に難しい場合、評価が不公平に感じられることがある点や、組織内での相対的な業績比較ができないため、全体的なパフォーマンスの傾向を把握しにくい場合があるのがデメリットでしょう。
社員には、自部署内での相対評価の順位だけでなく、他部署との比較視点も持っておく必要があります。
相対評価では、社員同士を比較し、業績の差を明確にする評価方法で、パフォーマンスの差が浮き彫りになりやすいのが特徴です。
社員は他の社員と競い合うため、競争心を刺激し、高い成果を上げようと社内で切磋琢磨するモチベーションが高まります。
また、評価をグループ内で均等に分けることで、例えば高評価が集中し過ぎることを防ぎ、全体のバランスが取れた評価が得られます。絶対評価のように目標達成した社員全員が給与アップやインセンティブ対象となることがないため、人件費もコントロールしやすいのもメリットです。
相対評価を採用すると、評価の合理性が欠けてしまうという点は否めないため、従業員のモチベーションが下がるケースもあり注意が必要です。
同じ部署やチームに成績のよいライバルがいる場合、いくら頑張っても高い評価を得られないからです。
特定の評価ランクに対して、必ず一定人数を配置するという方法を取ると、業績に関わらず必ず何人かが低評価にならざるを得ないため、優れた社員であっても相対的に評価が低くなることがあります(例えば、A評価が決まった人数分しか割り当てられない)。
また評価が他の社員と比較されるため、実力が十分に発揮できない場合や、他の社員が非常に優れている場合に、自分のパフォーマンスが過小評価されていると感じることがあります。
競争を促進する反面、チームワークを損なう可能性もあるため、注意が必要です。
| 特徴 | 絶対評価 | 相対評価 |
| 評価基準 | 自分の業績や目標達成度に基づく評価 | 他の社員との比較による評価 |
| 比較対象 | 他の社員と比較しない | 他の社員と比較してランク付け |
| 目的 | 個人の成長や業績達成度を評価 | 全体の中での相対的な位置を評価 |
| メリット | 公平で明確な評価基準 | 業績の差別化がしやすく、競争を促進する |
| デメリット | 社員間の比較ができず、業績が目立たないことがある | 競争が過度になる可能性があり、不公平感が生じることがある |

人事評価を5段階評価でおこなうことで、評価付けが明確になるという特徴があります。制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性向上にもつながるため、最終的には企業全体の成長も期待できます。
各評価の割合、評価方法によってもそれぞれメリットやデメリットがあるため、しっかりと理解した上でどのような形で採用するかを検討しましょう。
ただし、こうした分布によって、正当に評価がされなくなったり、公平性に欠ける評価システムになってしまった場合、会社にとっても大きな不利益となります。
このように人事評価の導入にはコツが必要で、時間もかかるものですが、導入の負担は、人事評価をシステム化することで、評価の質や納得度をまとめて上げることができるでしょう。
人事評価に特化した特許取得済のツール、「Newton(ニュートン」なら、各従業員のスキルや個人評価をはじめとした多くの情報を瞬時に確認できる独自のシステムで、個人に適した項目や基準設定により絶対評価が可能になり、組織・企業の成長に繋がる人材育成の実現を目指すことができます。
人事評価制度において、評価制度設計やその他人事評価業務でお悩みのある方は、ぜひ「Newton(ニュートン」の導入をご検討ください。
人事評価において、上司と部下との信頼関係は非常に大切なポイントです。
信頼関係が構築されていなかった場合、人事評価の結果がよくなかった際に、評価内容について納得ができず、モチベーションや生産性の低下、最悪の場合は退職につながってしまうこともあります。
本記事では、人事評価が低い社員が辞めてしまう理由とその原因、また社員のモチベーション低下やトラブルを防ぐための注意点・対策法もご紹介します。
不満の出やすい「やってはいけない」人事評価についてもまとめたので、公平な人事評価に課題を感じている方はぜひご活用ください。

人事評価では、成果・能力・情意のバランスを考え、結果だけでなく、仕事に取り組む姿勢も客観的に評価する必要がありますが、この人事評価にはどうしても不満はつきものです。とはいえ会社としてはなるべく改善の対応をし、育成していきたい部分でもあります。
人事評価の低い社員が不満を持つには以下のような理由か考えられます。
ひとつずつ解説します。
人事評価で社員が不満を持つ大きな理由の一つに、評価基準が曖昧という点が挙げられます。
なぜその評価になったのかが理解できないと、社員も努力の方向性がわからず、自社に対し不信感を抱いたり、モチベーション低下に繋がったりする可能性があります。
評価者と従業員の感覚のズレを修正するためにも、評価基準は明確にするよう心がけ、なるべく数値化するなど工夫しましょう。
社員が自分自身を高く見積もっている場合、実際の評価結果に不満を持つ可能性があります。
評価が低い理由がわからなければ、社員の不満を高めてしまうでしょう。
自己評価が実績より高い社員に対しては、評価者がなぜこのような評価結果を出したのか、説明やフィードバックをおこなうのがおすすめです。
前向きな声かけやフォローを合わせて徹底するようにしましょう。
上司や人事と社員の間に信頼関係ができているかどうかも大切なポイントです。
人事評価をおこなう評価者と部下とのコミュニケーションが不足していてフィードバックが不十分な場合や、伝え方に気を回すことができなかった場合、不満が生まれやすいとされています。
評価者が部下から信頼されていない場合、評価内容についても納得感が得られず、やる気を失う原因にもなりかねません。
また、評価する上司が現場を知らないと、社員が不満を溜める原因になります。
自分を評価する人を信用できなければ、部下はモチベーションをなくしてしまい、離職につながってしまうことが考えられます。
人事評価でよい評価を得たにもかかわらず、昇給や昇格など処遇に反映されないケースも、社員が不満を持つ理由の一つです。
たとえ評価が公平公正なものであっても、評価結果が昇給や昇格に反映されない制度では、「がんばっても給与が上がらないからやる気をなくす」といった影響を与えてしまい、従業員のモチベーションを維持するのは難しくなります。
評価がどのように処遇に反映されるかを明確にし、どれくらいの基準を達成したらどれくらいの報酬や等級に値するのかなどを数値化しておくことが納得感に繋がるでしょう。

人事評価への不満は、個人だけでなく組織全体に大きな影響を与える可能性があります。
評価システムの透明性と公平性を確保する手法をとり、フィードバックや改善の機会を設けることが、社員の不満を減らし、組織の健全な運営に繋がるでしょう。
詳しく見ていきましょう。
人事評価の結果に対し、不公平に感じたり、自分の努力が評価されていないと感じることで、社員のモチベーションが大きく低下し、業務のパフォーマンスにも大きな影響を与えます。
評価に対して不満がある社員は、組織に対する信頼感が薄れ、自分がいくら努力しても報われないと認識してしまうため積極的な貢献をしなくなることが多く、結果として仕事の効率や成果も停滞する恐れがあります。
モチベーションが下がることにより自己成長もなくなるため大きな仕事を任せてもらうこともなくなり、スキルや収入も上がらないという悪循環に陥ってしまう可能性があります。
人事評価のシステムが公平で透明でないと、会社全体の評価システムやマネジメントに対する信頼が低下します。
社員は組織の方針に対して疑念を抱くようになり、結果として組織文化が弱体化する可能性があります。
評価に不満を持つ社員が、組織に対する不信感を抱くようになると、最終的には転職を考えることが増え、離職率が上がる可能性があります。多くの場合、優秀な社員が転職の決断をしがちです。組織にとっては大きな損失となるでしょう。
上司と部下の関係が悪化し、コミュニケーションが取りづらくなることで、業務の遂行に支障をきたすこともあります。
特に評価の不公平感が人間関係に影響を与え、チームの信頼関係が損なわれ、トラブルにつながることがあります。
不満が蓄積されると、職場内での対立や摩擦が増え、コミュニケーションが減ることでチームワークが乱れ、協力が困難になるのが問題点です。
この点は特に注意が必要でしょう。

人事評価で「評価エラー」がある場合に、社員からの不満が出やすいとされています。評価エラーとは、評価者の主観や感情により、実際とは異なる誤った評価を下してしまうことを指します。
人事評価をおこなう際には、これらの評価エラーがないか十分に確認する必要があります。
ここでは、よく挙げられる7つの評価エラーを紹介します。
詳しく解説しますので、これらの要素をなくすように徹底しましょう。
「ハロー効果」は、人事評価や心理学の分野で使われる効果の一つです。
特定の人物や対象の全体的な印象が、その人物の特定の評価や属性に影響を与える現象を指します。
例えば、ある社員が非常に明るくて社交的で、人間関係が得意な場合、その「よい印象」が他の仕事のパフォーマンスやスキルにも影響を与え、その社員が実際にはあまり業務を効率的にこなしていない場合でも、「彼は人間関係がよいから、仕事もできるだろう」と合わせて評価してしまうことです。
この場合、社員の特定の長所が全体的な評価に影響を与えて、他の側面(業務能力、成果、勤勉さなど)の評価が不正確になってしまいます。
「中心化傾向」とは、人事評価において、公正であることを意識しすぎるあまり、評価者が評価を極端な良い評価や悪い評価に偏らせることを避け、無難な中心化した評価=中間的な評価を選びがちな傾向のことを指します。
これにより、全ての従業員が「平均的」とされる結果になり、個々の社員の実際のパフォーマンスが適切に反映されなくなってしまいます。
このような評価を行うと、実際の成果や業務能力が正確に反映されなくなり、評価が不正確になるため、社員の実績や努力が十分に認識されないことに繋がります。
「寛大化傾向」は、人事評価において評価者が評価対象者に対して過剰に甘く、よい評価を与えがちな心理的偏りを指します。つまり、実際のパフォーマンスや成果にかかわらず、評価が優れたものと見なされる傾向です。
評価者が部下や同僚に対して好意的であったり、良好な関係を保ちたいと思うあまり、厳しい評価を避け、寛大な評価をしてしまう場合や、あまりにも低い評価をつけると、後で不平や不満を言われることを恐れ、あまりに高い評価をつけることで問題を避けようとする心理が働く場合もあります。
最悪の場合、全ての社員が「よい評価」を受けることになり、実際のパフォーマンス差が反映されません。
これにより、優秀な社員が適切に評価されず、業績が不十分な社員の評価が高くなる可能性が生じます。
「厳格化傾向」とは、人事評価において評価者が評価対象者に対して過剰に厳しく、低い評価を与えがちな心理的偏りを指します。実際のパフォーマンスより低い評価となり、よい仕事をしている社員であっても、評価が不当に低くなる現象です。
評価者が自身の基準を非常に高く持っている場合に、社員がその基準に達しないと感じると、厳しめの評価をしてしまうことがあります。
また評価者が特定の社員に対して高い期待を抱いている場合、その期待に応えられていないと感じると、評価を厳しくする傾向があります。
組織や部門に「成果主義」「高い業績基準」が強調される文化がある場合も、評価者もその影響を受け、成果が不十分と感じた場合に過剰に厳しい評価をしてしまうことがあるでしょう。
「極端化傾向」とは、人事評価において評価者が評価を極端な方向に偏らせる傾向のことを指します。
評価者が社員のパフォーマンスを実際よりもよい、または悪いと感じ、全体的な評価が極端なものになってしまうことで、平均的な評価や中間的な評価を避ける現象です。
評価者本人が「極端な評価の方がわかりやすい」と無意識に思い込んでいる場合、全ての社員に対して極端な評価をつけることがあります。
また、評価の結果が重要な意味を持つ場合(昇進、賞与など)、評価者が失敗を避けたいというプレッシャーから、過剰に低い評価(失敗を避けるため)や高い評価(リスクを避けるため)をしてしまうことがあります。
「論理誤差」とは、人事評価において評価者が論理的に不正確な思考や推論を基にして評価を行うことを指します。評価者が社員のパフォーマンスを判断する際に、事実や具体的な証拠に基づくのではなく、論理的に誤った前提や関連性のない要素を評価に持ち込むことです。これにより、実際の業績や能力が適切に反映されず、不正確な評価をしてしまうことがあります。
評価者が、個人的な感情や無意識に持つ先入観や偏見、不完全な情報に左右され、論理的な判断ができなくなる場合に起きやすくなります。
「対比誤差」とは、人事評価において、評価者がある社員のパフォーマンスを他の社員と比較することで、実際の業績や能力を不正確に評価してしまう現象です。
評価者が、他の社員の業績やパフォーマンスと比較して評価したり、評価対象者を「他の社員と比べてどうか?」という観点で評価してしまうため、その社員が本来持っているパフォーマンスや能力とは異なる基準で評価される可能性があります。
評価者が評価の基準を明確に持っていない場合、他の社員との比較によって評価が歪むことが多くなります。
基準があいまいな場合、最も印象に残った社員と比較して評価してしまうことがあるでしょう。また複数の社員を評価する際、評価者が評価の順番を覚えていない場合や、評価対象者が他の社員の直後に評価されると、前の社員との比較に引きずられやすくなります。
人は自然に「相対的」に物事を評価する傾向があり、特に同じ時期に複数の評価を行っている場合、比較が強く影響するため注意が必要です。

モチベーションが低くなった社員は離職の決断に繋がることも多く、対策・対応が急務です。評価エラーを無くすのはもちろんのこと、問題点を解決し、社員のやる気を引き出し、生産性を高めるためのポイント・注意点について解説します。
詳しく解説いたします。
人事評価をおこなう際、何を基準に評価をしているのか、人事評価基準を部下としっかりと共有する必要があります。
部下それぞれに求められている姿を提示し徹底的に共有することが、上司と部下の意見のズレの解消に効果的でしょう。
評価基準をしっかりと数値化し、目標設定を明確にした人事評価のシステムを作成することで部下は仕事に対してモチベーション高く取り組むことができます。
人事評価において、社員一人ひとりの能力や特性を正確に理解し、その社員に最適な役割や職務・職種に配置することは、組織全体の効率性や生産性、業績、社員の満足度を向上させるための基本的な戦略です。
適正な人事により本人が得意とする分野や興味のある最適な業務に従事することで、社員はやりがいを感じ、モチベーションが向上します。
しかし適材適所でない配置がされている場合、社員はその役割に必要なスキルや知識が不足していたり、逆に業務内容に興味がなかったりするため、パフォーマンスが低下し、無駄な努力や時間が浪費される可能性があります。
優秀な評価者は対話量が多いといわれており、コメントやフィードバックでは前向きな内容も伝えるのが大事なポイントです。
定期的な面談で丁寧にヒアリングを重ね、対話や質問の量を増やし関係性を強化することで、上司と部下との評価に対するギャップが少なくなり、評価への不満が積もって突然離職するケースが減るとされています。
注意点としては、伝え方を意識することです。
よい点があれば見逃さずに積極的に褒め、悪い点は、対策を含めて励まし教育するように心がけましょう。
処遇とは、報酬、昇進、賞与、昇給、評価など、社員の業務に対する対価や評価を意味します。適切な処遇を行うことで、組織は次のような重要なメリットを享受できます。
正当に評価された社員は、その努力や業績が認められたことに満足し、さらに高いモチベーションで仕事に取り組むことができ、「スキルを高めれば報われる」という意識を持つことで、自己投資や学習への意欲・やる気も高まります。
逆に、不公平な処遇が行われると、社員は会社の対応に不満を感じ、仕事への意欲が低下し、他の職場を探し始めて組織からの離職が進む可能性もあるでしょう。
社員のモチベーションの低下を防ぐには、人事評価を正しく徹底して運用することが大切です。
自社の人事評価にエラーがないか定期的に見直しをおこなうことが重要です。
社員のパフォーマンスを最大限に活かすことにつながります。
評価基準をわかりやすく明確にし、適材適所の人材配置をおこなうためには、仕組み化されている人事評価ツールの活用が便利でしょう。
納得度の高い人事評価制度により組織の成長に繋がる人材育成を目指したいなら、タレントマネジメントや人材育成に特化した特許取得済の人事評価システム「ニュートン」がおすすめです。
お気軽にお問い合わせください。
人事評価において、従業員本人による自己評価を導入している企業も多いでしょう。
社員の昇給や昇進、部署異動といった処遇の決定に欠かせない人事評価ですが、本記事では、人事評価における自己評価とはどのような意味があるのかを詳しく解説します。

人事評価制度では、自己評価シートが活用されることがあります。
自己評価シートとは従業員が自分自身の業績や能力、仕事の姿勢などを自己評価するための文書です。
定期的なパフォーマンス評価や人事評価のプロセスの一環として使用されるもので、従業員が設定した目標達成度や会社への貢献度、自身の強みや改善点を自身で評価し、上司や人事部門の評価と照合した上で具体的なフィードバックを交換するための基礎として活用されます。
自分の強みと弱みを客観的に把握することで自己理解を深め、会社とのエンゲージメントを高めて、成長につなげることが期待できるでしょう。
自己評価シートと人事評価シートは、どちらも従業員の業績や行動を評価するためのツールですが、評価の視点や役割が異なります。
人事評価は、上司や人事部門が従業員の業績や行動を評価するためのもので、外部からの視点を反映しており、会社によっては人事考課とも呼ばれます。
組織の目標にどれだけ貢献したかや、評価基準に対する適応度、リーダーシップや協調性などを重視するため、より客観的で公平な視点が求められます。
対して自己評価は、従業員自身が自分の業績、スキル、行動、態度などを振り返り、自己認識を高めることを目的にしています。
従業員が自分自身の強みや改善点を考え、どれだけ目標を達成したか、どのように業務を遂行したかを自己分析し、自己評価をおこないます。
自己評価は主観的な意見が含まれがちで、自分の成果を強調したり、改善点を挙げたりすることがあるため、人事評価との客観的な照合が必要でしょう。
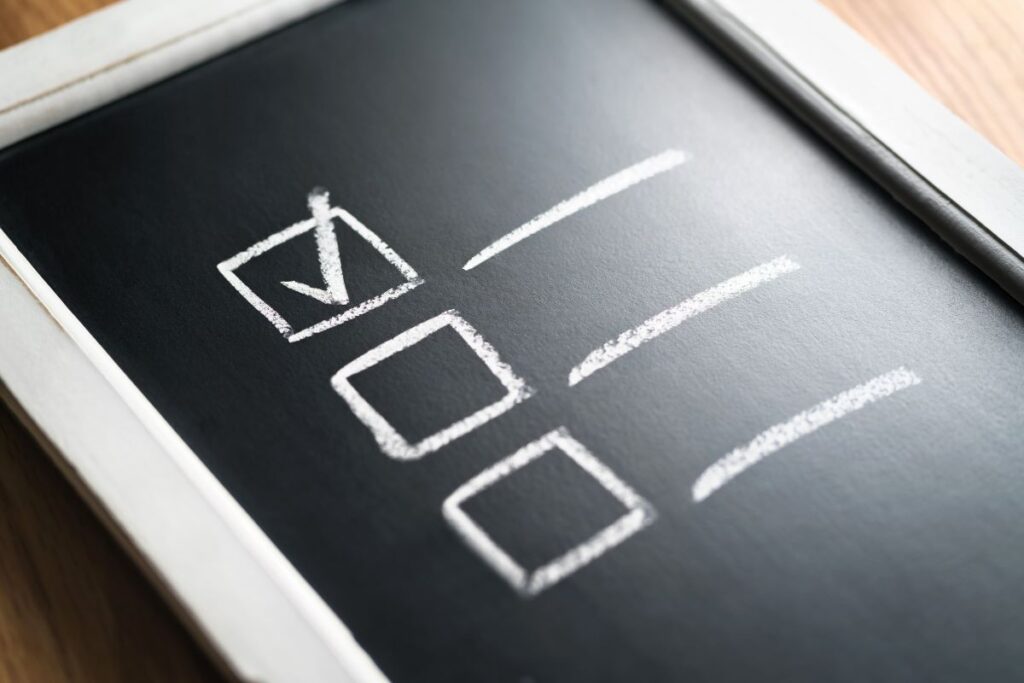
自己評価をおこなう目的と重要性について解説します。
自己評価をおこなうことで、従業員が自分自身の業績や行動を客観的に振り返り、自分の強みや改善すべき点を理解する助けになります。
次回の評価に向けた目標や改善策を立てるためにも役立てることができるでしょう。
また、上司や人事担当者とのコミュニケーションを通じて、自己評価をもとに意見交換やフィードバックをおこない、適切・適正な人事につなげ、業績向上や組織全体のパフォーマンスを向上させるのが目的です。
360度評価など、人事評価の種類によっては自己評価が必須のものもあります。
自己評価は、従業員自身が自分の業績や行動を振り返り、自己認識を深めるプロセスであり、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献します。
従業員が自分の仕事や行動を客観的に振り返る機会を提供するため、自分の弱点や改善が必要な部分を明確にすることができ、今後の成長に向けた具体的な行動計画を立てやすくなります。
従業員自身の成長を促進し、上司や人事部門と効果的な対話をおこなうための重要なプロセスとなるほか、従業員が自己評価をおこなうことで、一方通行ではなく双方向の評価となることが重要な点といえるでしょう。
また、自己評価を上司からの評価と照らし合わせることで、従業員と上司の視点の違いや差を明確にし、公正な評価を促進します。
なお、営業職や管理職、事務職など、それぞれの職種に合わせて自己評価のポイントは変わるため、職務内容や業績目標に沿った具体例を作成する必要があります。

自己評価を導入することは、従業員、上司、さらには組織全体にとって多くのメリットがあります。
自己認識の向上や組織の成長を促進するだけでなく、評価プロセスの透明性を高め、従業員のモチベーションを向上させる効果もあります。
自己評価の導入による主なメリットは以下のとおりです。
それぞれみていきましょう。
自己評価によって、従業員は自分の得意な分野や業績を実感できる一方で、改善が必要な点にも気づくことができます。
業績、スキル、行動、強み、そして改善すべき点を振り返ることで、自己の強みと弱みを認識することができ、自己改善や成長の意識が芽生えます。
さらに自己評価を通じて、従業員は自分のキャリア目標や今後の成長方向についても再評価することができ、現実的で達成可能な目標を立てることができるため、成長促進の助けになり、キャリアパスを見つけるきっかけにもなり得るでしょう。
自己評価の結果をもとに、従業員と上司は具体的な業績や行動に関してミーティングをおこなうなど建設的な対話をすることができます。
これにより、フィードバックがより具体的で意味のあるものになり、従業員の成長を支援する内容にすることができます。
上司と従業員が評価に対する見解を共有することで、認識のギャップが明らかになり、誤解を解消するきっかけとなります。
フィードバックの質が高まり、よりよいコミュニケーションを生み出します。
適正な自己評価を取り入れることで、多面的な評価が可能になります。
従業員自身の視点を評価に反映させることができるため、上司による一方的な評価だけに頼らず、より公平な評価につながるでしょう。
従業員は評価基準を意識しやすくなることで、上司との評価基準に対する共通理解が生まれます。
これにより評価プロセスの透明性や公正性が高まり、評価が不公平であるという不満が減少する可能性があります。
自己評価が日常的におこなわれることで、組織全体が自己改善を重視する文化を形成し、従業員が自分のパフォーマンスを常に振り返り、向上心を持つようになります。
また従業員は自分のパフォーマンスに対する責任を自覚し、より積極的に業務に取り組む姿勢が強化されます。
これにより自己改善を重視する文化の醸成と、責任感の向上へとつなげることができ、組織全体の文化や風土によい影響を与えることができます。

自己評価を導入することには多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットや課題も存在します。
自己評価は従業員の自己認識を高めたり、フィードバックを促進したりする一方で、適切に運用しないと評価が歪んだり、評価プロセスが不公平になったりするリスクもあります。
ここからは、自己評価を導入するデメリットを説明します。
一つずつ解説していきます。
自己評価は、従業員自身の意見や感覚に基づくため、客観性に欠ける場合があります。
従業員が自己評価を通じて、自分をよく見せたいという意識が働くことがあり、結果的に過剰によい評価をつけたり、自分の成果を過大評価したりといったことが生じる可能性があります。
また自分に自信がない従業員や成果に対して過度に謙虚な従業員は過小評価をしてしまう場合があります。
過大評価・過小評価については後の章で詳しく紹介しています。
従業員と上司が評価基準に対する認識や理解が異なる場合、自己評価と上司の評価が大きく食い違って差が生まれてしまい、評価の整合性が取れないことがあります。
自己評価が上司の評価と大きく異なる場合、評価の整合性を取るために追加の調整や議論が必要になりますが、これが評価プロセスを複雑にし、評価の信頼性を低下させる可能性があります。
評価プロセスを遅延させ、従業員にとっても不安や不満を生む原因になることがあり、不公平に感じられることもあるでしょう。
自己評価をおこなうことで、評価プロセスが透明で公平であることを期待する一方、自己評価が自己満足に終わったり、上司に伝わらなかったりすると、従業員が不信感を抱くことがあります。
自己評価をしても、それが上司や組織に十分に反映されないと感じた場合、評価の意味を疑問視することがありえます。
この場合、自己評価をおこなうモチベーションが低下し、評価プロセスへの信頼感が損なわれる可能性があり、最悪の場合、離職率が高まる危険性も考えられます。
自己評価は、従業員にとって時間と労力がかかる作業になることがあります
特に、評価項目が多い場合や自己分析をしっかりとおこなう必要がある場合、負担に感じることがあるでしょう。
自己評価は従業員に追加の作業を強いるため、忙しい業務の中で負担に感じる場合があります。
この作業負担の増加により、ストレスやフラストレーションを生む可能性があります。

人事評価において、自己評価が過大になる従業員は、さまざまな心理的・行動的な特徴を持っていることがよくあります。
過大評価する傾向が強い従業員は、自分の業績や貢献度を過剰によく見せようとすることがあり、評価が不正確になる可能性があります。
本人も無自覚なため、注意が必要です。
評価基準を明確にし、上司と従業員の間での継続的なフィードバックや対話を通じて、自己評価の偏りを防ぐことが重要です。
自己評価が高くなりがちな従業員の具体例・特徴をいくつかまとめます。
詳しく解説します。
自己評価が過大になる従業員は、しばしば自己中心的な性格を持つことがあります。
そういった従業員は、自分の意見や考えが最も重要だと考え、他者の意見や視点を十分に考慮しない傾向があるといえるでしょう。
自分の成果や貢献を過大に認識し、自分のやり方が正しいと信じ込んでいるため、他者の意見やフィードバックを軽視する、いわゆる自己優越感が強い傾向にあります。
仕事の成果や貢献を独自の視点で解釈し、他者の視点を十分に考慮しなかったり、客観性に欠いた視点を持っていたり、個人の成果を強調し、チームや組織全体の貢献を過小評価することが多いため注意が必要です。
昇進や評価に強い関心を持つ従業員は、自己評価を意図的に高くつけることで、自分の業績や貢献を強調し、評価の結果をよくしようとすることがあります。
成果や結果が評価される環境に強く依存している従業員は、成果を上げた部分を過剰に強調し、他の重要な要素(例えば、プロセスやチームワーク)の貢献を軽視する傾向があるといえるでしょう。
自己肯定感が高すぎると、自分の仕事の成果や取り組みが他の人と比べて優れていると信じる傾向が強くなり、客観的な評価が難しくなります。
自分の行動や成果を正当化し、他人からのフィードバックや批判を受け入れなくなります。
過剰な自己肯定感により、自分の役割や貢献を過大に評価し、組織やチームの一部としての成果を見逃す可能性もあるでしょう。
自分が達成した業務や結果を過剰にポジティブに解釈し、自分の業績を実際よりも高く認識するため、失敗やミスを他人や外部の要因に責任転嫁し、弱点をほとんど認めない場合も考えられます。
競争心が強い従業員は、自分の社会的地位や価値を高く保ちたいと考え、自己評価を高くつける傾向があります。
他人と比較して自分の方が優れていると感じることが多く、その結果、自己評価が高くなりやすいといえるでしょう。
自分の業績を他の従業員と比較し、競争心から自分の成果を過大に評価することがあり、評価が低くなることを避けるために、自分の貢献を過剰に評価し、否定的なフィードバックを受け入れなくなります。
ポジティブな自己イメージを保ちたいという心理が働くことも、自己評価を過大にする原因となります。
他人からの評価や自己の価値に対する不安を感じるため、過大評価をしてしまう傾向があるでしょう。

自己評価が過小になりがちな従業員は、自己認識が低かったり、過度に謙虚だったりする場合が多く、結果的に自分の業績や貢献を正当に評価しない傾向があります。
積極的なフィードバックやサポートをおこない、自信を持たせ、自己評価のバランスを取る手助けをすることが重要です。
以下に、自己評価が低くなってしまう従業員の具体例・特徴を挙げます。
詳しく解説します。
謙虚な従業員は、自分の業績や貢献を大げさに主張することなく、他人の評価を過度に重要視する傾向があります。
自分が達成したことを「当たり前だ」と感じ、過剰に謙遜するため、自分の実力や成果を過小評価して「私はまだまだ」「他の人の方がもっとできる」と考えがちです。
また、自己評価なのに他人の評価に頼ることが多く、自分の力や成果を正しく評価できないのが大きな特徴です。
否定的な評価を恐れるあまり、自己評価を過小にし、評価が低くても仕方がないと感じることもあるでしょう。
完璧主義的な性格を持つ従業員は、常に高い基準を自分に課しており、その基準に満たないと感じたときに自己評価を低くしがちです。
自分のパフォーマンスが完璧でないと感じた場合、自己評価を過小にすることがあります。完璧主義者は自分の成功を認めることができず、常に「もっとできたはず」と基準に達しない自分に焦点を当てます。
また小さなミスを大きく捉える特徴もあるため、自分がミスした部分や改善点を過剰に意識し、それが全体のパフォーマンスに大きな影響を与えていると感じてしまうことがあります。
自己肯定感が低い従業員は、自分に自信がなく、自分の業績や成果を十分に評価できないことがあります。
自分の成果を他者と比べて低く評価し、「自分には大したことができていない」と感じる自己評価の過小化の傾向があり、成功や貢献があっても、それを「偶然だった」と考えたり、他人の助けが大きかったと過小評価をする場合があります。
また自分の弱点やミスばかりを意識し、ポジティブなフィードバックを受け入れにくい点も自己評価を低くする要因の一つです。
自己批判が強い場合、自分の仕事に対して過度に厳しく、他人からのフィードバックに対してもすぐに否定的に反応してしまい、自分のミスや不足している点に過剰にフォーカスし、自己評価を低くする傾向があります。
過去に失敗やネガティブな経験をした従業員は、その経験が影響し、自己評価が低くなることがあります。
特に、以前の評価が低かったり、過去の成果が認められなかったりして、それを克服してこなかった場合、自己評価に悪影響を与えることがあります。
人事評価シートにおける自己評価は、制度の公平性を高め、キャリア形成や適切な評価を受けるために非常に重要です。
自己評価を実施することで、客観的に仕事ぶりを見つめ直すことができます。
公平公正な人事評価を行う上でも、人事評価ツール導入がおすすめです。人事評価ツールを使うと評価フローが可視化され、管理や運用の手間が省けます。
人事評価ツールNewton(ニュートン)は、データ駆動型の評価やリアルタイムのフィードバック、カスタマイズ可能な評価基準などが特徴で、自己評価の項目設定や入力はもちろん、使いやすいインターフェースにより効果的な人事評価をサポートし、組織のパフォーマンス向上に寄与します。
ツールを通して評価制度の課題をクリアにし、制度の浸透や評価プロセスの見える化を進め、納得度の高い人事評価制度を運用しましょう。 Newtonについて詳しく知りたい方はこちら
現代の企業の組織の効率性や従業員の満足度を向上させるためには、人事評価制度は欠かせないものとなっています。しかし、効率的に活用できなければ、従業員の不信感を煽り、離職にも繋がりかねません。
そこで本記事では、人事評価制度の作り方を中心に詳しく解説します。まず何から取り組めばいいのか?どうすれば失敗しないのか?など、基本からポイントを押さえて解説します。導入を検討している人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
人事評価制度は、組織の目標達成に貢献するために従業員のパフォーマンスを適切に評価し、改善を促進するための重要な制度です。
従業員の業績や能力を体系的に評価し、評価制度や等級制度、報酬制度に反映させる仕組みで、組織の目標達成や従業員の成長を支援するシステムです。
社員一人一人の能力やパフォーマンス(貢献発揮)などを評価し、等級や賃金に反映させます。適切に運用されることで、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まり、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。

そもそも人事評価制度には、どのような種類があるでしょうか。
人事評価は「能力評価」「業績評価」「情意評価」という3種類で構成されており、これら3つは相互関係にあります。
能力評価は、従業員のスキルや知識、能力を評価する方法で、従業員が持つ技術的なスキル、専門知識、問題解決能力、リーダーシップ能力など、職務遂行に必要な能力を評価します。
評価される項目には、専門知識、スキル、業務に関連する能力(例えば、プロジェクト管理能力、コミュニケーションスキルなど)が含まれます。通常、自己評価、上司評価、同僚評価などが用いられ、評価は定量的(スコアや評価点)または定性的(具体的なフィードバックやコメント)で行われます。
従業員の能力やスキルが明確に評価でき、キャリア開発や教育訓練の方向性が見えやすいのがメリットですが、評価者の主観が入りやすく、評価が一貫しない場合があるのがデメリットです。
業績評価は、従業員の仕事の成果や業務に対する貢献度を評価する方法です。
具体的な業務結果や成果物を評価するもので、評価される項目には、売上、利益、プロジェクトの達成度、業務の効率性、顧客満足度などがあり、業務の具体的な結果や成果が評価対象となります。業績目標に対する達成度を評価するために、数値的な成果やKPI(重要業績評価指標)を使用することが多いでしょう。
明確な成果や業績に基づいて評価が行われるため、比較的客観的な評価が可能ですが、業績評価は短期的な成果に焦点を当てることが多く、長期的な成長やスキルの発展が見落とされる可能性があります。
また達成すべき目標が高すぎると、従業員に過度なプレッシャーを与えたり、不正行為を引き起こす可能性があります。
情意評価は、従業員の態度やモチベーション、職場での行動や人間関係のスキルを評価する方法です。
従業員の態度、仕事への取り組み方、職場での人間関係、コミュニケーション能力、チームワークなどの感情面や行動面を評価します。
評価される項目には、職場での態度、チームワーク、コミュニケーションスキル、問題解決へのアプローチ、ストレス管理能力などが含まれます。
情意評価は主に定性的な方法で行われることが多く、評価者の観察やフィードバックに基づく評価が一般的です。具体的には360度評価(自己評価、上司評価、同僚評価、部下評価など)や、定期的なパフォーマンスレビュー、観察に基づくフィードバックが使用されます。
従業員が組織の文化や価値観にどれだけ適合しているかを測ることで、職場環境の調和を保つのに役立ちますが、情意評価は主観的な要素が多く、評価者の感情や偏見が影響を与える可能性があるのがデメリットでしょう。
次に、人事評価制度の評価手法のご紹介です。
人事評価の評価手法は複数ありますが、今回は最もベーシックに活用される3種類をご紹介します。
それぞれ解説します。
MBOは、「MBO(Management by Objectives)」の略で、組織の目標と個々の従業員の目標を一致させ、従業員が設定した目標に対する達成度を評価する方法です。
目標設定とその達成度に基づいて評価や報酬を決定します。
明確な目標を設定することで、従業員の業績を向上させ、組織の戦略的目標を達成することを目指します。
従業員が明確な目標を持つことで、業務に対する焦点が定まりやすくなりますが、不適切な目標設定や非現実的な目標が設定されると、評価が不公平になる可能性があり、短期間の目標に集中しすぎると、長期的な視点や成長が見落とされる可能性があります。
目標設定や進捗管理の方法に注意を払い、公平かつ現実的な評価を行うことが成功の鍵です。
コンピテンシー評価は、従業員の職務遂行能力や行動特性(コンピテンシー)に基づいて評価を行う方法で、従業員が持つ特定のスキル、知識、行動特性(コンピテンシー)に基づいて、その業務遂行能力を評価します。
これには、業務の遂行に必要な具体的な能力や行動パターンも含まれます。
職務に関連する能力や行動特性を評価することで、従業員の適性やパフォーマンスを向上させ、適切な育成やキャリア開発を支援することが期待できます。
業務の結果だけでなく、職務遂行に必要な能力や行動特性を総合的に評価できるため、従業員の全体的なパフォーマンスを把握しやすいものの、コンピテンシー評価は主観的な要素が含まれるため、評価者の偏見や見解が影響する可能性があります。
評価の基準を明確にし、主観性を減らすための工夫が必要です。
360度評価は、従業員の業務パフォーマンスや行動を複数の視点から評価する方法で、具体的には、自己評価、上司評価、同僚評価、部下評価など、異なる立場の評価者からのフィードバックを集めて、総合的に評価を行います。
従業員のパフォーマンスを多角的に評価するために、複数の評価者からのフィードバックを収集し、その情報をもとに総合的に評価を行います。
多様な視点からのフィードバックを通じて、従業員の強みや改善点をより正確に把握し、より公平でバランスの取れた評価を行うことを目的としています。
評価者には、自己評価者、直属の上司、同僚、部下など、異なる立場の人々が含まれ、評価は通常、匿名で行われることが多いでしょう。
評価される項目には、仕事のパフォーマンス、リーダーシップ、コミュニケーションスキル、チームワーク、問題解決能力などが含まれます。
複数の評価者からのフィードバックを得ることで、従業員のパフォーマンスに対する多面的な視点を得ることができますが、評価者の主観が反映されるため、意見が偏る可能性があります。
評価の公平性やフィードバックの質を保つための工夫が必要です。
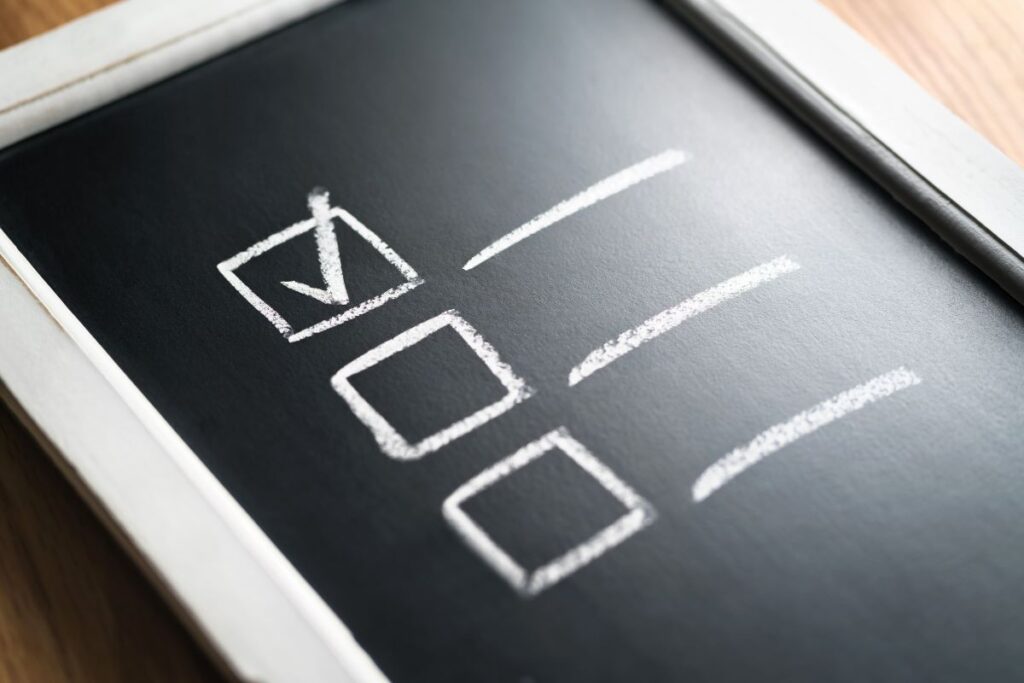
人事評価制度を作る目的は、組織内の従業員の業績や能力を体系的に評価し、組織の目標達成を支援することです。
具体的には、以下のような目的が考えられます。
それぞれ解説していきます。
人事評価制度を活用することにより、従業員の業績を公平かつ客観的に評価し、組織の目標に対する貢献度を把握することができます。
これにより、業績が高い従業員を認識し、適切な人材配置を行うことができるでしょう。
人事評価の結果に基づいて、給与の調整、ボーナス、昇進などの報酬を決定します。
業績や能力に応じた公正な報酬制度を確立することで、従業員のモチベーションを高めることができます。
従業員の強みや改善点を明確にし、キャリアの成長やスキルの向上に役立てるための具体的なフィードバックを提供することで、従業員の能力開発促進が期待できます。
人事評価制度を通じて、組織の価値観や文化を従業員に浸透させ、共有することができます。また、従業員が期待される行動や価値観を具体的に理解できるようになります。評価制度を利用して組織の目標と個々の目標を整合させることで、全員が共通の目的に向かって働くようになり、共通の価値観や目標に基づく文化の形成を促進します。これにより、組織全体の方向性と一貫性が保たれます。
効果的な人事評価制度を作るためには、以下の11ステップを踏むことが重要です。
これにより、公正かつ透明性のある評価プロセスを効果的に構築し、組織の目標達成を支援することができます。
順番にみていきましょう。
まずは人事評価制度の目的や目標を明確に設定します。
例えば、業績の評価、キャリア開発、報酬決定など、制度がどのような役割を果たすのかを明確にします。組織の戦略やビジョンに基づき、評価制度がどのように貢献するかを考えましょう。
評価の対象となる基準を定義します。これには、業績、スキル、行動、目標達成度などが含まれます。
具体的で測定可能な基準を設定し、従業員が理解しやすい形で提示します。
SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き)目標が役立つでしょう。
評価を行う方法や手法を決定します。
例えば、自己評価、上司評価、同僚評価、360度評価などがあります。
適切な評価方法を選び、評価プロセスが一貫性を持つように注意しましょう。
複数の評価手法を組み合わせることも検討するのがおすすめです。
評価のスケジュールやプロセスを設計します。
評価の頻度やタイミング、プロセスの各ステップ(目標設定、評価実施、フィードバック提供など)を決定します。
評価の各段階で必要なアクションやデッドラインを設定し、スムーズな進行を確保しましょう。
評価プロセスを支援するためのツールやシステムを選定します。
これには、評価フォーム、ソフトウェア、データベースなどが含まれます。
使いやすいツールやシステムを選定し、プロセスの効率化をサポートできるようにしましょう。
評価を行う管理者やリーダーに対して、評価の方法や基準に関するトレーニングを実施します。
公平かつ効果的な評価を行うためのスキルや知識を提供するのが重要です。
従業員に対して評価制度の目的、プロセス、基準について十分に説明します。
透明性を確保し、従業員が制度に対して理解し、納得できるようにしましょう。説明会や資料の提供が有効です。
評価結果をもとに、従業員に具体的なフィードバックを提供し、必要なサポートを行います。フィードバックが建設的で実践的であるようにし、従業員の成長を促進します。
評価結果をもとに、昇進、報酬、トレーニング、キャリアの計画などに反映させます。
評価結果が公正かつ効果的に活用されるようにし、組織の戦略的な意思決定を支援します。
評価制度の効果を定期的にレビューし、改善点を特定します。
従業員や管理者からのフィードバックを集め、必要に応じて制度を見直し、改善します。
評価制度が労働法や規制に適合するようにします。
法的要件を確認し、制度がコンプライアンスを確保するようにします。

失敗しない人事評価制度を作るためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。ここからは、具体的な注意点やポイントをご紹介します。
効果的で信頼性の高い人事評価制度を構築し、組織の目標達成と従業員の成長をサポートしましょう。
自社の状況をしっかりと把握した上で、評価制度の目的を具体的に定めましょう。
例えば、業績向上、キャリア開発、報酬決定など、組織のビジョンや戦略と一致させるのが重要です。
評価の方法を標準化し、公平で一貫性のあるプロセスを設計します。
複数の視点(自己評価、上司評価など)を組み合わせ、評価基準を具体的かつ測定可能な業績、スキル、行動などに設定しましょう。
人事評価において、誰が見てもわかりやすく、納得できる評価基準を設定し、それを可視化できる仕組みを整えるようにしましょう。
結果はもちろん、評価に至るまでの評価基準やプロセスについても従業員に明確に説明する必要があります。
ドキュメントや説明会での共有も有効です。
評価結果の共有のために、定期的にフィードバックを提供し、従業員の成長を支援します。1on1のフィードバックセッションを設けるのが効果的でしょう。
評価を行う管理者・評価者に対して適切なトレーニングを実施するのが大切です。
公正かつ効果的な評価方法を教えるようにしましょう。
評価制度を定期的にレビューし、必要に応じて改善します。
従業員や管理者からのフィードバックを集めるのも有効です。
労働法や規制に従い、コンプライアンスを確認します。
法律に基づいたチェックと更新を欠かさないようにしましょう。
人事評価制度の正しい作り方を理解することで、適切で効果的な人事評価を目指すことができます。適切な人事評価を通し、個人と会社の成長をはかりましょう。
人事評価制度の作成・運用に、人事評価ツールNewton(ニュートン)がおすすめです。社員教育や給与水準に対しての課題や、スキル・マネジメント・スタンスなど個人の評価が見やすく、多くの情報をひと目で確認できます。
また独自のシステムにより、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な仕様が特徴です。
人事評価業務を効率化し、公平な評価基準の浸透・実現のために、「人事評価ツールNewton(ニュートン)」でシンプル化してみてはいかがでしょうか。
多くの日本企業では、人事評価制度を通して従業員の能力を評価し、給与や昇進の根拠として採用してきました。
しかしその一方で、この人事評価制度が抱える課題から、近年ではあえて人事評価でのランク付けを廃止した「ノーレイティング」を導入する企業も増えてきています。
本記事では、人事評価制度に関する最新の状況と、注目されている新しい人事評価制度、ノーレイティングについて詳しく解説します。
今後の経営活動の参考にしてください。
従来の人事評価制度は、主に「業績評価・能力評価・情意評価」を評価対象としており、報酬・待遇の決定や、有効な人材配置や人材育成に生かすことができます。
しかし、同時にいくつかの課題もあり、従来の制度を見直そうとする動きがみられています。
ここからは、従来の人事評価制度を廃止する企業が増えている理由について解説します。
廃止の主な理由は上記2つになります。
それぞれみていきましょう。
近年では、従業員に求められる能力が多種多様化しているため、これまでのようにあらかじめ決められた項目のみでの評価では対応しきれなくなっています。
主な評価方法の一つであった「MBO(目標管理制度)」も、目標達成度を評価するというランク付け自体が目的化してしまうことがあり、評価基準の複雑化のためランク付けを廃止するべきという考えが増えています。
従来の人事評価制度によるランク付けでは、従業員同士の優劣が明確になってしまい、企業内にヒエラルキー構造が生まれるというのも課題の一つです。
正しく評価されなかったり、低評価をされた人材はモチベーションが下がり、離職率の増加にも繋がりかねません。従業員が評価ばかりを気にしてしまう環境からの打破として、あえて人事評価を廃止する企業が出てきています。

次に人事制度が抱える課題について、下記3つを解説します。
従来の古い人事評価制度は、在籍年数や年齢を元に評価していたこともあり、企業によってはどうしてもその影響を受けている場合があります。
その際に特に若手層が評価に「納得いかない」「不公平である」と感じやすいのが現状です。
また、人事評価制度は評価者の主観に基づいた評価となるため、評価者のバイアスや偏見によって不満や不公平感が生まれる可能性があります。
これらの状況を打破するためには、客観的な評価方法や透明性のある評価基準を積極的に導入し、主観的な評価要素を減らしていくのが重要です。
人事評価制度は、時代によって対応を変えていく必要があります。
近年ではテレワークの導入が進められていますが、実際に働いている環境を確認することができないため、業務への積極性などが評価しづらいという部分があります。
ウェブ会議やチャットでのコミュニケーションを増やす企業もありますが、対面に比べるとどうしても評価の質は下がるでしょう。
人事評価制度の評価は、成果主義の思想をベースに、自社の経営ビジョンに基づいて行われます。
しかし、日本企業は導入の際に経営ビジョンとそれに伴い必要となる評価要素について熟考してこなかったため、評価軸が定まらない面があります。
人事評価制度自体が不完全であることから、そもそも評価制度を無くしてしまおうという動きが出てきています。
現在、アメリカでは人事評価制度を廃止する動きが出てきています。
「人事評価制度を廃止」と聞くと、人材の評価自体をやめることに思えますが、人材や企業の成長を促す上で、人材の評価自体を完全に廃止することは難しいでしょう。
人事評価を廃止する、というのは、「人材のランク付けや点数付けをやめる」ということで、評価をしなくていいというのは誤解です。人事評価の負担は変わらないと考えて良いでしょう。
米国発の新しい評価制度「ノーレイティング」は、点数で評価を行うのではなく、目標に対してのプロセスを評価する方法です。
目標達成までの行動の内容、どのように目標を達成したのか、目標の見直しは行われたのかなどといったことも含め、高頻度でフィードバックを中心にした1on1ミーティングを実施し、面談を通して人事評価を行う方法です。
日常的に上司と1対1で面談を行うことからコミュニケーションが取りやすく、フィードバックの機会を頻繁に設けることで、従業員の効果的な評価や育成に繋げていきます。
現在はGEやマイクロソフト、アドビシステムズ、GAPなど、欧米の数多くの企業が続々と従来の人事評価を廃止し、ノーレイティングに移行しています。
アメリカの企業は成果主義という考え方が強いことから、ノーレイティングの導入や人事評価の廃止が比較的スムーズに受け入れられる傾向にあるのでしょう。

人事評価制度において「ノーレイティング」が広まった理由はいくつかありますが、主な理由として挙げられる下記4つをご紹介します。
なお、ノーレイティングは、評価プロセスをより建設的で、成長を促進するものを目指すために導入されています。
従来の評価制度は、評価者と被評価者の双方に対して大きなストレスや負担を伴うことがありました。
評価の結果に基づいて昇進や報酬が決まるため、評価がプレッシャーとなることがありますが、ノーレイティングのアプローチでは、点数やランキングに依存せず、より建設的で前向きな対話に焦点を当てることで、ストレスを軽減し、社員の成長促進を目指すことができます。
点数や評価の数値だけでは、具体的な行動や成果に対する理解が不十分であることが多いですが、ノーレイティングでは、定量的な評価ではなく、詳細なフィードバックや対話を通じて、社員が具体的にどのように改善できるかを明確にすることができます。
このアプローチにより、社員の自己改善やスキル向上が促進されます。
ノーレイティングの制度では、評価よりも協力やチームの成果に焦点を当てることが多いため、これにより個人の競争よりもチーム全体の協力を促進し、社員のエンゲージメントやチームワークを向上させることができます。
現代のビジネス環境では、スピード感や柔軟性が求められるため、従来の人事評価制度では、長期間にわたる評価プロセスが業務の進捗に対して迅速に対応できないことがあり、今までのランク付けによる評価では査定が困難になりつつあります。
アメリカでは日本よりも終身雇用廃止の流れが進みつつある中で、より多面的に評価する必要が出てきているため、定期的なフィードバックや改善を重視し、業務の変化に迅速に対応することが可能なノーレイティングが重宝されています。
人事評価制度を撤廃し、ノーレイティングを導入することには、いくつかの明確なメリットがあります。
一つずつみていきましょう
ノーレイティングでは、評価が点数やランクに依存しないため、評価者のバイアスや偏見の影響を軽減できます。
従業員は、具体的なフィードバックを通じて自分の強みや改善点を理解でき、評価の公平性が高まるのが一番に挙げられるメリットです。
点数や評価のための管理作業が減ることで、人事部門やマネージャーの負担が軽減され、より効率的にリソースを活用できます。
評価プロセスが簡素化されることで、日常業務に集中しやすくなるでしょう。
従来の人事評価制度のような決まったフォーマットや条件がないため、時短勤務や在宅勤務など、現代の多様な働き方に臨機応変に対応することができます。
定期的なフィードバックや対話を通じて、変化するビジネス環境や業務ニーズに迅速に適応することができ、評価制度の見直しや更新が不要なため、柔軟に対応することが可能になるでしょう。
ノーレイティングを導入することにより評価が建設的で前向きなものになれば、従業員のエンゲージメントやモチベーションが高まることが期待されます。
フィードバックが成長のための支援となり、仕事に対する意欲が向上するでしょう。
フィードバックを通じて定期的にコミュニケーションを図ることで、上司と部下の関係が改善され、よりオープンな対話が促進されます。
これにより、問題解決や目標設定がスムーズになるでしょう。

人事評価制度を撤廃し、ノーレイティングを導入する際には、下記のようなデメリットや課題も存在します。
企業がノーレイティングを導入する際には、これらのデメリットを考慮し、適切な準備とサポートを行うことが重要です。
ノーレイティングには点数やランクがないため、従業員の昇進や報酬の決定に対して、どのように判断を下すかが難しくなることがあります。
具体的な評価基準がないと、昇進や報酬に対する透明性が欠け、社員の不満を招く可能性があります。
従来の人事評価制度では定量的な成果が明確に示されますが、ノーレイティングでは成果を具体的に数値化しないため、個々の貢献度や業績の評価が難しくなる場合があります。
これが昇進や報酬の決定に影響を及ぼすことがあります。
ノーレイティングの導入には、管理者やリーダーが効果的なフィードバックを提供するためのトレーニングやサポートが必要です。
このトレーニングが不十分だと、フィードバックの質が低くなり、ノーレイティングの効果が十分に発揮されない可能性があるでしょう。
企業の文化や慣習が強く評価制度に依存している場合、ノーレイティングの導入が既存の制度と衝突することがあります。
従業員やマネージャーが新しい制度に対して抵抗を示すことがあり、変革の過程で混乱が生じることがあるでしょう。
本記事では、今後の人事評価制度の仕組みの変化について解説してきました。
ノーレイティングに移行する企業も増えてきていますが、日本の文化や慣習とは相性が良いとは一概には言い切れません。
とはいえ企業の成長を促すためには、従業員を評価するということには変わりはありません。正しい方法で実現し、評価制度自体を大きく改革するのがおすすめです。
人事評価ツールNewton(ニュートン)は、データ駆動型の評価やリアルタイムのフィードバック、カスタマイズ可能な評価基準などが特徴で、使いやすいインターフェースにより効果的な人事評価をサポートし、組織のパフォーマンス向上に寄与します。
ツールを通し制度の浸透や評価プロセスの見える化を進め、納得度の高い人事評価制度を運用しましょう。
人事評価のコメント作成、毎年頭を悩ませていませんか。
部下の日々の頑張りを認め、成果を的確に言葉にするのは、簡単なことではありません。
「もっと気の利いた、的確な表現はないか」
「改善点を伝えるときに、相手のモチベーションを下げてしまったらどうしよう」
PCの前でうんうん唸りながら、多くの管理職が同じ悩みを抱えています。
この記事では、そんなあなたのために、人事評価の上司コメントに関するあらゆる悩みを解決します。
コピペしてすぐに使える職種別の豊富な例文から、部下のやる気を引き出し、成長を促すための具体的な書き方のコツまで、網羅的に解説します。
この記事のポイント
この記事を読めば、評価コメントの作成時間を大幅に短縮できるだけでなく、部下一人ひとりに寄り添ったフィードバックが可能になります。
結果として、部下からの信頼を高め、「良い上司」としてチームのパフォーマンスを最大限に引き出すことができるでしょう。

まずは、すぐに使える上司コメントの例文をまとめてご紹介します。
部下の状況や自社の評価シートに合わせて、最適な例文を見つけてください。
このセクションでは、以下の3つの視点で例文を整理しています。
これらの例文は、少し修正するだけで現場で使える実践的なものばかりです。
ぜひあなたの言葉でアレンジして、活用してみてください。
部下のパフォーマンスレベルに応じて、コメントの伝え方を工夫することが重要です。
単に褒める、あるいは指摘するだけでなく、どのように伝えれば相手が前向きに受け止め、次の成長に繋げられるかを考えましょう。
ここでは、「ポジティブ評価」と「標準〜改善点がある場合」の2つのシナリオに分けて、具体的な例文とポイントを解説します。
優れた成果を出した部下には、その事実を具体的に称賛し、さらなる活躍への期待を伝えることが大切です。
本人が自身の強みを客観的に認識し、自信を持って次のステージに進めるようなコメントを心がけましょう。
| 状況 | コメント例文 |
|---|---|
| 目標を大幅に達成した | 目標達成率120%という素晴らしい成果は、〇〇さんの粘り強い顧客訪問と的確な提案力の賜物です。特に新規開拓における行動量はチーム全体の手本となっており、今後のさらなる飛躍を期待しています。 |
| チームに大きく貢献した | 〇〇さんが主導した業務改善プロジェクトにより、チームの残業時間が月平均10時間削減されました。常に全体の効率を考え、主体的に行動する姿勢を高く評価します。 |
| 新しいスキルを習得した | 未経験だった動画編集スキルを自主的に学び、社内広報用の動画を完成させた行動力に感銘を受けました。新しい挑戦を恐れない姿勢は、今後のキャリアにおいて大きな武器になるでしょう。 |
多くの管理職が最もコメントに悩むのが、このケースではないでしょうか。
重要なのは、できていない点の指摘だけでなく、まずできている点を認めた上で、具体的な改善策と期待をセットで伝えることです。
このような「サンドイッチ型」のフィードバックは、部下が指摘を素直に受け入れ、前向きな行動変容を起こす助けとなります。
| 状況 | コメント例文 |
|---|---|
| 成果は標準だが、プロセスに課題 | 目標達成に向けた真摯な取り組みは評価しています。一方で、タスクの優先順位付けに課題が見られ、締め切り間際に業務が集中する傾向があります。来期は週次での進捗確認会を通じて、計画的な業務遂行スキルを一緒に身につけていきましょう。 |
| 特定のスキルに改善が必要 | 顧客への丁寧な対応は素晴らしく、お客様からの評判も上々です。その上で、より提案の幅を広げるために、製品Bに関する知識を深めることを期待します。来月の製品研修への参加を推奨します。 |
| 勤務態度に少し懸念がある | 日々のルーティン業務を正確にこなしてくれる点には、いつも助けられています。ありがとうございます。一方で、会議での発言が少ない点が気になります。〇〇さんの視点は貴重ですので、来期はまず一度、意見を述べることを目標にしてみませんか。 |
ここでは、より具体的に、職種ごとの特性を踏まえたコメント例文をご紹介します。
読者の皆様が担当する部下の職種は多岐にわたるため、幅広いケースを想定しました。
各職種で特に評価されるポイントに焦点を当てていますので、部下の顔を思い浮かべながらご覧ください。
営業職では、売上などの数値目標(定量評価)と、顧客との関係構築や行動プロセス(定性評価)の両面から評価することが重要です。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 目標達成度 | 上半期目標であった新規契約数10件に対し、15件という素晴らしい結果を残しました。特に、競合とのコンペでA社から大型契約を獲得できたのは、〇〇さんの粘り強い交渉と緻密な情報分析の成果です。 |
| プロセス・行動 | 安定して高い成果を出し続けているのは、日々の行動計画と徹底した顧客管理の賜物です。〇〇さんが作成しているアプローチリストは非常に質が高く、ぜひチーム全体で共有してほしいと思います。 |
| 改善点 | 既存顧客との関係構築力は高い評価に値します。今後はその強みを活かしつつ、新規顧客の開拓にもより一層力を入れることで、営業としての幅がさらに広がると期待しています。 |
事務職の貢献は、数字に表れにくい場合も多いため、業務の正確性や効率化への貢献、他部署との連携といった点を具体的に言語化することが大切です。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 正確性・迅速性 | 請求書処理において、この半年間ミスが一度もありませんでした。〇〇さんの正確かつ迅速な業務遂行能力のおかげで、部署全体の業務が非常にスムーズに進んでいます。 |
| 業務改善 | 従来のアナログなファイリング方法を見直し、クラウドストレージを活用した管理方法を提案・実行してくれました。これにより、資料検索時間が大幅に短縮され、部署全体の生産性向上に大きく貢献しました。 |
| 協調性・サポート | 常に周りに気を配り、多忙なメンバーの業務を率先して手伝う姿勢は、チームの潤滑油のような存在です。〇〇さんのサポートのおかげで、チームの雰囲気が非常に良くなりました。 |
医療・福祉の現場では、専門知識や技術はもちろん、患者・利用者への対応やチームでの連携が極めて重要になります。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 患者・利用者対応 | 常に患者様の立場に立った丁寧なケアを実践しており、ご家族からの信頼も厚いです。特に、認知症のA様に対して根気強くコミュニケーションを取り、笑顔を引き出していた場面は印象的でした。 |
| チーム連携 | 医師やリハビリスタッフとの情報共有を密に行い、常に最適なケアを提供しようとする姿勢は素晴らしいです。カンファレンスでの的確な報告は、チーム医療の質向上に不可欠なものとなっています。 |
| 改善点 | 高い専門知識を持っていますが、時にご自身の判断で業務を進めてしまう傾向が見られます。安全な医療・ケアを提供するためにも、必ずチームで報告・連絡・相談を徹底するようお願いします。 |
保育士の評価では、子どもたちの安全を守り、健やかな発達を支えるという基本に加え、保護者との信頼関係構築も重要なポイントです。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 園児への対応 | 一人ひとりの子どもの発達段階や個性を深く理解し、それぞれに合った声かけや関わり方ができています。〇〇先生のクラスの子どもたちが、のびのびと安心して過ごしている様子が何よりの証拠です。 |
| 保護者との連携 | 保護者への連絡ノートの記述が非常に丁寧で、日々の園での子どもの様子が目に浮かぶようだと好評です。懇談会での誠実な対応は、園と家庭との信頼関係構築に大きく貢献しています。 |
| 企画・実行力 | 運動会の企画では、子どもたちの自主性を引き出す新しいプログラムを提案・実行してくれました。準備段階から子どもたちを巻き込む工夫は、他の職員の参考にもなりました。 |
公務員の評価では、法令遵守や公正性といった基本姿勢に加え、住民サービス向上への貢献や、前例踏襲にとらわれない業務改善への意欲などが評価されます。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 住民対応 | 窓口業務において、常に丁寧で分かりやすい説明を心がけており、住民の方から感謝の声が届いています。複雑な手続きについても、相手の立場に立って根気強く対応する姿勢は、全体の模範です。 |
| 業務改善 | 〇〇申請手続きのオンライン化を提案し、関係各所との調整を粘り強く進めてくれました。これにより、住民の利便性向上と職員の業務効率化の両方を実現できた点は、高く評価します。 |
| 法令・知識 | 担当分野の関連法規について深い知識を有しており、法改正にも迅速に対応しています。他の職員からの問い合わせにも的確に回答しており、部署の知識レベル向上に貢献しています。 |
製造・技術職では、専門的なスキルや知識はもちろん、品質や生産性の向上、安全への意識、そしてチームでの協力体制が評価のポイントとなります。
| 評価ポイント | コメント例文 |
|---|---|
| 品質・生産性向上 | 製造ラインの工程を見直し、新たな治具を導入したことで、不良品率を5%改善し、生産性を10%向上させました。データに基づいた的確な分析と実行力を高く評価します。 |
| 技術力・問題解決 | 〇〇の不具合が発生した際、原因を迅速に特定し、再発防止策まで策定してくれました。その深い技術的知見と冷静な問題解決能力は、チームにとって不可欠です。 |
| チームワーク・指導 | 自身の技術や知識を惜しみなく後輩に伝え、チーム全体の技術力向上に貢献しています。〇〇さんの丁寧な指導のおかげで、若手メンバーの成長が著しいです。 |
自社の評価シートの項目に合わせて、表現のバリエーションを増やせるように、一般的な評価項目別のフレーズ集を用意しました。
これらのフレーズを組み合わせることで、より具体的で説得力のあるコメントが作成できます。
結果だけでなく、そのプロセスや組織への貢献度も評価することが重要です。
| 評価の方向性 | フレーズ例 |
|---|---|
| 目標達成 | – 目標であった売上〇〇円を120%達成した点は、素晴らしい成果です。 – 〇〇という行動が、新規契約数〇件という結果に繋がりました。 – 常に高い成果を出し続けており、安定してチームの業績に貢献しています。 |
| 目標未達成 | – 目標には一歩届きませんでしたが、〇〇という新しい試みに挑戦した点は評価できます。 – 結果は伴いませんでしたが、目標達成に向けたプロセスには見るべきものがありました。 |
| 貢献度 | – 個人目標の達成のみならず、チーム全体の目標達成にも大きく貢献しました。 – 〇〇さんの上げた成果は、部署全体の士気を高める良い影響を与えました。 |
保有スキルが業務でどのように発揮され、成果に繋がったのかを具体的に示しましょう。
| スキルの種類 | フレーズ例 |
|---|---|
| 企画・立案力 | – 課題の本質を捉えた的確な企画を立案し、プロジェクトを成功に導きました。 – 斬新な視点からの提案は、議論を活性化させるきっかけとなりました。 |
| 実行・遂行力 | – 計画を着実に実行に移し、困難な状況でも最後までやり遂げる責任感があります。 – 関係各所との調整を粘り強く行い、計画を円滑に推進しました。 |
| 専門知識 | – 〇〇分野に関する深い専門知識は、部署内でも随一です。 – 新しい技術の習得に意欲的で、その知識をチームに還元してくれています。 |
主観的になりがちな項目だからこそ、具体的な行動事実に基づいて評価することが納得感を高める鍵です。
| 評価項目 | フレーズ例 |
|---|---|
| 積極性 | – 常に現状に満足せず、より良い方法を模索する姿勢が見られます。 – 誰も手を挙げたがらない業務にも、自ら率先して取り組んでくれました。 |
| 協調性 | – チームの目標達成のために、自分の役割を理解し、他メンバーと効果的に連携しています。 – 意見が対立する場面でも、冷静に双方の意見を聞き、合意形成に努めていました。 |
| 責任感 | – 自身の担当業務に対して強い責任感を持ち、最後までやり遂げる姿勢は高く評価できます。 – ミスが発生した際も、隠さず迅速に報告し、誠実に対応していました。 |

優れた例文を知ることも大切ですが、応用力を身につけるためには、コメント作成の根底にある「考え方」を理解することが不可欠です。
ここでは、部下のモチベーションを高め、上司としての信頼を得るための5つの基本原則を解説します。
これらの原則を意識すれば、あなたのコメントは単なる評価ではなく、部下の成長を力強く後押しするメッセージへと変わるはずです。
評価コメントで最も重要なのは、「具体性」と「客観性」です。
なぜなら、根拠が曖昧な評価は部下の納得を得られず、不信感に繋がるからです。
日頃の行動や成果を、具体的なエピソードや数値を交えて記述しましょう。
| 比較 | コメント例 |
|---|---|
| 悪い例(抽象的) | 今期もよく頑張ってくれた。積極性もあって素晴らしい。 |
| 良い例(具体的) | 担当したA案件で、自ら追加提案を行い、結果として前年比150%の売上を達成した点は高く評価します。 |
人事評価は、過去の成績を裁く場ではありません。
その目的は、評価を通じて部下の未来の成長を促すことにあります。
コメントの最後は、必ず次期の目標や期待する行動を示す、前向きな言葉で締めくくりましょう。
「今回の成果を活かして、来期はリーダーとして後輩指導にも挑戦してほしい」のように、具体的な期待を伝えることが重要です。[^3]
良い点だけではお説教になり、悪い点だけでは部下を追い詰めてしまいます。
部下がフィードバックを素直に受け入れるためには、強みと改善点の両方をバランス良く伝えることが効果的です。
特に改善点を伝える際は、まずポジティブな点を認めてから本題に入る「ポジティブ・サンドイッチ」の手法が有効です。
これにより、部下は心理的な抵抗なく、自身の課題と向き合うことができます。
評価は上司からの一方的な押し付けであってはなりません。
コメントを作成する前に、必ず部下が提出した自己評価に目を通しましょう。
もし、上司の評価と部下の自己評価にギャE.T.ップがある場合は、その差がどこから生まれているのかを考え、面談での対話を通じてすり合わせる準備が必要です。
「自分ではこう評価しているが、あなたはどう思う?」と問いかける姿勢が、部下の納得感を引き出します。
質の高い評価コメントは、一朝一夕には書けません。
評価期間の終わりに慌てて思い出そうとしても、直近の出来事ばかりが印象に残ってしまう「期末効果」に陥りがちです。
日頃から1on1ミーティングなどで部下と対話し、気になった行動や成果をメモしておく習慣が、最終的に客観的で説得力のあるコメント作成に繋がります。

良かれと思って書いたコメントが、実は部下のやる気を削いでいるとしたら、それは非常にもったいないことです。
ここでは、管理職が陥りがちな、絶対に避けるべきNGコメントの4つの特徴を解説します。
無意識のうちに部下を傷つけ、信頼関係を損なわないためにも、ぜひチェックしてください。
| NGな特徴 | 具体的なNG例文 | なぜNGか? |
|---|---|---|
| 人格・性格の否定 | 「君は慎重な性格だから、決断が遅い」 | 変えられない人格を指摘されると、部下は改善のしようがなく、自己否定に陥ってしまう。評価すべきは「行動」。 |
| 他者との比較 | 「同期の〇〇君は、もう新規契約を5件も取っているぞ」 | 他者比較は、不公平感や劣等感を生むだけ。評価はあくまで本人の過去との成長度で測るべき。 |
| 根拠のない主観 | 「なんとなく、今回の成果には物足りなさを感じる」 | 具体的な事実に基づかないコメントは、部下にとって「上司の好き嫌い」としか受け取れず、不信感に繋がる。 |
| 曖昧な指示 | 「もっと主体性を発揮してほしい」 | どうすれば「主体的」と評価されるのかが分からず、部下は次の行動に移せない。 |
「〇〇さんは心配性だから、行動が遅い」
「もう少し明るい性格だったら、チームも活性化するのに」
これらは、評価ではなく人格攻撃です。
評価の対象は、あくまでも客観的に観察できる「行動」と、その「結果」でなければなりません。
「同期のAさんはもうリーダーを任されているのに、君は…」
このような他者との比較は、部下の間に無用な競争心や劣等感を生み出し、チームワークを阻害します。
比較対象は、常に「過去の本人」あるいは「設定した目標」であるべきです。
「君には期待しているんだけど、どうも物足りないんだよな」
具体的な事実に基づかない、上司の「印象」や「感覚」で語られたコメントは、部下を混乱させるだけです。
なぜそう感じるのか、具体的なエピソードやデータを添えて説明できなければ、それは単なる個人的な感想に過ぎません。
「来期はもっとリーダーシップを発揮してほしい」
このコメントを受け取った部下は、「具体的に何をすれば良いのか」が分からず、行動に移せません。
「来期は、週次の定例ミーティングで進行役を務めることから始めてみよう」のように、次のアクションに繋がる具体的な指示や提案をすることが不可欠です。

毎年繰り返される人事評価。
そのコメント作成に多くの時間を費やし、精神的な負担を感じている方も多いのではないでしょうか。
その悩みを根本的に解決する手段として、近年注目されているのが「タレントマネジメントシステム」の活用です。
ここでは、評価業務を効率化し、かつコメントの質をも高めるシステムの可能性について、具体的な事例を交えて解説します。
人事評価システムの導入は、単なる業務効率化に留まらない多くのメリットをもたらします。
ここでは、より具体的なイメージを持っていただくために、当サイトの関連サービスである飲食店向けタレントマネジメントシステム「ニュートン」の事例をご紹介します。
飲食業界特有の課題解決ノウハウが詰まっていますが、その考え方は多くの職場で応用可能です。
「ニュートン」は、従業員のスキルレベルや勤務態度、実績などのデータを日々収集・蓄積します。
これにより、上司は「〇〇さんは今月、接客スキル評価項目で平均点を5点上回った」といった客観的な事実に基づいてコメントを作成できます。
上司の主観や記憶だけに頼らない評価は、従業員の納得感を飛躍的に高めます。
「ニュートン」の大きな特徴は、評価と教育がシステム上で連動している点です。
例えば、評価面談で「新メニューの提案力が課題」という結果が出た場合、システムが自動で関連する調理マニュアルや提案方法の研修動画を本人に提示します。
これにより、評価が「やりっぱなし」にならず、具体的な成長アクションへとスムーズに繋がるのです。
「ニュートン」を導入した企業では、評価業務にかかる時間が平均で40%削減されたというデータがあります。
評価シートの作成や集計といった作業から解放されることで、管理者は本来最も時間をかけるべき「部下との1on1ミーティング」などの対話に時間を使えるようになります。
システムはあくまでツールであり、それによって生まれた時間を、人と人とのコミュニケーションに投資することが、最終的にチームの成長を加速させます。

この記事では、人事評価における上司コメントの具体的な例文から、部下の成長を促すための基本原則、そして避けるべきNG例まで、幅広く解説しました。
改めて、重要なポイントを振り返ります。
人事評価のコメント作成は、決して簡単な仕事ではありません。
しかし、それは同時に、部下のキャリアに深く関わり、その成長を直接支援できる、非常にやりがいのある役割でもあります。
今回ご紹介した例文やポイントが、あなたの評価業務の負担を少しでも軽くし、部下とのより良い関係を築く一助となれば幸いです。
的確なフィードバックは、部下一人ひとりを、そしてチーム全体を力強く育てる最強のツールなのです。

人事評価のコメントは、従業員の成長やモチベーションアップにつながるように書くことが重要です。
人事評価コメントの根拠となる社員のスキルや経歴、評価実績や目標に対する進捗などのデータは【システム化】することで、人材育成の戦略人事に効率よく展開できるでしょう。納得度の高い人事評価制度により組織の成長に繋がる人材育成を目指したいなら、タレントマネジメントや人材育成に特化した特許取得済のツール「ニュートン」がおすすめです。
工数のかかる「人事評価」業務を「人事評価ツールNewton(ニュートン)」でシンプルに効率化してみてはいかがでしょうか。
激しい競争環境に常にさらされている飲食店業界ですが、その中で生き抜くためには店舗の効率的な運営が不可欠です。
離職率が高いといわれる飲食業界では、業界特有の課題に合わせた人事評価制度を整え、業績に応じて賃金コントロールを行う必要があるでしょう。
本記事では、飲食店や外食チェーンの人事評価制度について解説します。
人事評価制度の目的や必要性、一般企業との違い、飲食店向けの評価制度の作成ポイントについても解説していきます。
人事評価制度の導入を考えている方や、見直しを検討している方はぜひ参考にしてください。
人事評価制度は、従業員の業務遂行能力や行動、パフォーマンス、業務への貢献度などを可視化して評価し、それに基づいて従業員個々の給与・報酬・賞与・昇進などに反映させる制度です。
飲食業界は離職率が高く人手不足といわれているからこそ、人員の評価はしっかり適正に行う必要があります。
人事評価制度を導入することで、自社の企業目標を明確化することができ、企業が従業員に期待し求める能力や行動が明確になります。
会社からの評価や判断基準を理解することで、従業員自身が目指すべき行動・戦略を取りやすくなるため、従業員の能力・意欲形成にも繋がり、業績の向上も期待できるでしょう。
また人事評価制度で社員それぞれの長所や短所、特徴をデータベース化することで、個々の技術や経験も明確化することができ、適切な人材配置にも繋がります。
この時、どのような人事制度を策定すべきかは重要なポイントです。
人事評価システムは競合が導入していない可能性が高いため、率先して導入することがおすすめです。
人事評価を行う際には、自社がどのような目的で人事評価を行うのか、必要性をしっかりと理解し、各従業員の評価を適正におこないましょう。

飲食店や外食チェーンの経営を発展させていくためには人材の育成・定着は必要不可欠なため、人事評価制度の導入は非常に効果的でしょう。
しかし、飲食業界と一般企業とでは大きな違いがあるため、しっかりと理解しておく必要があります。
ここでは、飲食店と一般企業との人事評価の違いをまとめます。
飲食店の場合、職場には正社員だけでなくアルバイトやパートの従業員もいます。
アルバイトやパートも正社員に近い業務を任されることになるため、アルバイトやパートの従業員の時給の決定のために、正社員と同じように評価していく必要があります。
飲食業界における人事課題で最も大きいのは定着率の低さによる人材不足のため、いかにモチベーションを保ちながら働いてもらえるかが重要になりますが、このとき人事評価制度を活用するのは大変有効です。
入社間もない従業員であっても、働いた年数ではなく能力値で評価してもらえる環境を整えることで、待遇を良くするために意欲的に働いてくれる可能性があります。
人事評価制度を活用して優秀な人材を確保することは、飲食業として生き残っていくためには必要不可欠でしょう。
飲食店においての人事評価制度では、一般企業で評価基準となる定量評価(売上金額、業績など)ではなく、数値化できない定性評価(対応力、自主性など)が中心になります。
売上や営業利益といった業績で目標達成していたとしても、スタッフ教育が不十分ではクレームに繋がり、店の評判も落ちてしまいます。
飲食業界で欠かせない評価項目として、QSC(クオリティー・サービス・クリンリネス)レベルのチェックがあり、これもそれぞれに評価ポイントを数値化していく必要があります。
たとえばホールスタッフであれば、「お客さまのニーズに応えているか」「丁寧な接客を心がけているか」などが大枠となるでしょう。
ただしQSCに関しては、社内だけで行うのは難しいため、お客さまアンケートを通して調査し、その結果を反映させるのがおすすめです。

飲食店で人事評価制度を導入する際、活用されることが多い方法と、そのメリットデメリットをご紹介します。おもな評価の仕方を把握しておきましょう。
MBO(目標管理制度)はManagement by Objectivesの略で、明確な目標(「少し」頑張れば達成できそうな身近なもの)を設定する手法です。
目標達成度を評価基準とするため、客観的な評価が可能であることと、従業員が目標達成に向けた自分の役割を理解しやすくなるため、モチベーションを保ちやすいのがメリットです。
その反面デメリットとして、昇給に反映させるため目標設定を低くしてしまったり、適切な設定ができなかった場合は逆効果になり、やる気を削いでしまう可能性があるでしょう。
360度評価制度は、従業員の業務遂行能力や行動を、自己評価だけでなく、上司・部下・同僚など、社員に関係するさまざまな立場から多画的に調査し、評価を行う手法です。
異なる立場の複数人からの意見を反映させることにより、従業員の総合的な評価が可能となります。
客観性や公平性を保った評価ができるのがメリットですが、評価対象との関係性によっては甘く評価してしまう可能性があるのがデメリットです。
結果主義評価制度は、業務成果によって従業員の評価を決定する制度です。
勤務歴や年齢を問わず数値的な指標などで評価されるため、納得感が高いのが特徴です。
平等に評価できるのがメリットですが、業務成果だけを重視するため、過度な競争やチームワーク面でのトラブルに繋がる可能性があるのがデメリットです。

飲食店における人事評価シートを作成する場合、意識しておくべきポイントが存在します。
飲食店では、店長やアルバイトなど、従業員ごとに立場や責任も違ってきます。
例えばお客様からの評判が良くないホールスタッフが多ければ、それは店長の責任になってくるため、能力評価が低い点数となるでしょう。
店長の人事評価シートの場合、店長に必要な重要な項目として、人材育成や店舗内のチームワーク強化などがあります。
その他、経営理念への理解、売上高、原価率、人件費率、営業利益など、定量化できる業績目標達成率も評価対象になります。
アルバイトの人事評価シートの場合は、ホール、キッチンなど仕事内容により評価内容も異なるでしょう。
店長と違い、お客様対応やホスピタリティ、調理に使用する食材の知識や技術向上へのモチベーションなどの定性面がメインとなります。
各スタッフに目指すべき行動指針を指導することで、双方にとっても働きやすい環境になるでしょう。
飲食店の人事評価シートを作成する際には、評価の基準を明確にしておく必要があります。評価する人によって基準がずれてしまうと、不公平感が生まれ、業務効率の低下や離職に繋がってしまう可能性があるでしょう。
従業員の不安を煽ることのないよう注意が必要です。
評価者の主観で判断することのないよう、人事評価システムを通し複数人からの明確な評価
を受けて客観的な評価を受けるようにするのがおすすめです。
細かく項目を定めてルール化し、評価基準を明確にしていくよう心がけましょう。
人事評価制度で得たデータは、ただ保管するだけでなく、しっかりと分析し、活用することが重要です。
活用のイメージがつきづらい場合は、人事評価システムを導入するのがおすすめです。
ツールを使用することにより、職場の課題や、スキル・マネジメント・スタンスなどの多くの情報量を、調査を挟むことなく瞬時に判断できるため、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な評価制度が目指せるでしょう。
また評価シートは一度作ったらそのままずっと使わなければならないわけではありません。定期的に追加・修整を繰り返し、満足度の高い人事評価制度を構築してください。
人事評価シートで得たデータをもとに、従業員へのフィードバックをするのも大切です。
その際、結果をどうフィードバックするかで、従業員の満足度が変わると言っても過言ではないでしょう。
面談では、従業員に対して具体的、建設的なフィードバックを提供することが大切です。
フィードバックの質を高め、従業員のモチベーション向上を促すための対策として、フィードバック担当者に対する研修や教育の機会などを設けるのもおすすめです。

飲食業界では常に人材不足、人材の流動性の高さという課題があります。
以下2点に着目しながら、飲食業界の人事課題について見ていきましょう。
飲食業界・外食産業の最大の課題は、人材の定着率の低さだと言われています。
飲食業界は3K(きつい、きたない、きけん)のイメージを持つ人も多いことに加え、入れ替わりが激しくスタッフ間の情報共有がしづらいこと、残業や休日出勤が多いこと、賃金体系への不満が人材の定着率を下げてしまう要因となっています。
これらは飲食業界の「当たり前」といわれてきましたが、時代の移り変わりと共に、根本的にこの業界常識を改めなければならなくなっています。
人材不足だが応募が来ない、そのため人材確保ができず既存スタッフの負担が増え、既存スタッフの疲弊から離職に繋がり、さらなる人材不足に、といった負のスパイラルから抜け出せない状況の会社も多いかもしれません。
飲食業界は常に人手不足のため、しっかりと評価されなければ離職してしまう可能性が高くなってしまいます。貴重な人材を効率的に育成するためにも、適正な人事評価制度が必要となるわけです。
飲食店において、一番重要なポジションが「店長」です。とはいえ、同じ「店長」でも、店によって質は大きく違い、アルバイト・パートの定着にも影響を及ぼします。店長の育成を怠ってしまえば、部下も店も育たず、業績も上がることはないでしょう。
人材難な今日では少数精鋭で回さなければならないため、マネージメント能力やモチベーションが備わっていない、会社の経営理念への理解がない人材を人がいないからという理由で店長に任命したりしてしまうことが多いのも原因の一つでしょう。
人事評価の際には、店長に何を求めるかを明確にした上で評価項目を整備し、会社が店長自身に何を求めているかを伝える必要があります。本部とのやりとりが行えているかどうかも重要なポイントです。
さらに、各階層の役割が不明確だと、店長に業務が集中してしまい、大きな負担になってしまうことも考えられます。一般社員やアルバイトと差別化した評価項目を設定しましょう。
これらの課題を改善するためにも、人材育成ツールを取り入れ、各階層・立場によって評価項目を管理し、効率的な店舗運営を目指すのがおすすめです。

飲食業界は大きな課題を抱える業界だからこそ、優秀な人材の雇用・育成を実現するのが重要です。激しい店舗間競争を勝ち抜き、生き残るためにも、正しい人事評価と業務効率化を実現し、評価制度自体を大きく改革して、飲食店経営向けの評価制度を導入するのがおすすめの対策です。
人事評価ツールNewton(ニュートン)は、社員教育や給与水準に対しての課題や、スキル・マネジメント・スタンスなどの個人の評価が見やすく多くの情報量を瞬時に判断できるシステムで、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な評価制度が特徴です。
評価制度の構築から運用までワンストップでのサービス・サポート体制を提供しているため、人事評価に課題や不安を感じている飲食店様でも安心して利用できます。
単独ではなく、複数人による評価を自動取得できることにより評価者の納得度も高まります。(※特許取得済)
まだ競合が導入していない可能性が高いからこそ、率先して導入し、業界を強く生き抜く飲食店を目指していきましょう。
人事評価制度により組織・企業の成長に繋がる人材育成を実現し、業務効率化を目指したいとお考えの方は、ぜひニュートンをご活用ください。
人事評価シートは、従業員の業績や能力、一人ひとりの目標や自己評価をふまえて昇進や昇給、賞与などの処遇を適切に決めるための明確な根拠となる書類です。
人事評価シートは企業の経営戦略の構築や組織開発にとって重要ですが、評価項目やフォーマットは各企業ごとに設定されているため、どのように書いたらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、人事評価シートの目的や重要性に加え、職種別の評価項目サンプルもご紹介します。
適切で公平な評価基準を保った人事評価に繋げるために、ぜひ参考にしてください。
人事評価シートは、従業員の業績や能力を公平に評価する際の評価項目や、従業員ごとの目標を管理するための書類で、多くの企業が組織開発のために活用しています。
人事評価シートの他、人事考課シートや成果効果シート、行動評価シートなどとも呼ばれます。
具体的には、各従業員の意欲・スキル・成果に加え、積極性・規律性・協調性など、業務に取り組む姿勢も評価します。
これらの情報を各従業員の昇格・昇給・賞与などの処遇や、さまざまな人事施策に役立てます。
ただし、この人事評価が適切に行われず不公平な結果となってしまうと、従業員間で不満が生まれ、モチベーションの低下や離職率の増加につながる可能性があるため注意が必要です。

多くの企業で活用されている人事評価シートですが、公平かつ公正に人事評価を行うことが一番の目的・前提になります。
下記が、人事評価シートを作成する主な目的です。
一つずつ紹介します。
人事評価シートや人事評価制度を活用することにより、組織の目標やビジョン、独自の価値観やルール、経営戦略を明示することができます。
これにより、企業が求める働き方が明確となり、企業と従業員間での共通認識が生まれ、従業員が企業の指針に沿った行動を取りやすくなります。
結果として、各従業員の能力とのエンゲージメントも高まるでしょう。
人事評価シートを作成し、人事評価項目を定めておくことで、評価基準や根拠が明確になり、評価結果にも納得しやすくなります。
公平かつ公正な人事評価で、従業員が働きやすさと納得感を感じることにより、会社への愛着や忠誠心も高まり、退職リスクの低減にも繋がります。
作成した人事評価シートを元に、社員の能力や技能、業績を客観的に調査・測定し、昇進や昇給、賞与や人事異動などを決定します。
この人事評価制度では、評価項目となる必要な成果や能力などが明確に示されるため、従業員は具体的な目標を設定しやすくなり、成長の機会を得られるようになります。
また、フィードバックや面談・面接の場を設けることで上司と部下が直接話せるため、従業員は自分自身の強みや課題、努力の方向性やキャリアプランなどを考えるきっかけになり、双方間での信頼関係を築くことができるでしょう。

人事評価シートは、人事評価の評価基準をもとに構成されます。
人事評価の評価基準となる項目は、「成果評価(業績評価)」「能力評価」「情意評価」の3つを主軸として成り立っています。
それぞれみていきましょう。
業績評価、成果評価とは、一定期間に設定した目標に対して、どの程度達成できて、会社へ貢献できたかを評価する方法です。
従業員の成果や目標の達成・成長度合い、成果に至るまでのプロセスを部門や個人単位で評価します。
業務目標に対する達成度の「業務目標達成度」と、目標達成のための課題の達成度の「課題目標達成度」に分けて評価することが多いでしょう。
能力評価とは、保有している能力や技能を業務でどれだけ発揮できたかを評価するもので、職務を遂行する上で求められるスキルや知識といった従業員の能力や、その能力自体がどれくらい発揮されたかを評価します。
主に評価基準となる能力には、「企画力」「計画力」「実行力」「問題解決力」「リーダーシップ」などがあり、元々の能力をどれだけ発揮できたかに加え、新たな能力を開発できたかも評価します。
なお、職位や職種によって求められる能力やレベルは異なります。
情意評価とは、従業員の日頃の遅刻早退の勤怠や、業務意欲などを評価する方法です。
主な評価基準には、規律性、責任感、協調性、積極性など、仕事に対する姿勢や態度があります。
数値化できない部分を評価する方法のため、評価者の主観が入りやすくなり、あいまいな評価になりがちです。
客観的に評価するために、自己評価や上司からの評価に加え、同僚や部下からの評価も加味するのが一般的です。

ここからは人事評価シートの評価項目サンプルを、職種別にご紹介します。
具体例として下記の4つの職種をご紹介します。
なお、情意評価は社内共通であることが多いでしょう。
事務職は、ノルマなどの明確な指標が少ない職種のため、「成績」の評価に必要な数値目標を設定しづらい職種のため工夫が必要です。
| 評価 | 評価項目 | 評価内容 | 評価点 |
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか | 5・4・3・2・1 |
| 課題目標達成度 | 業務目標の達成に向けて設定した課題を達成できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に企画提案できたか | 5・4・3・2・1 |
| 実行力 | 独力で業務を行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| 知識 | 担当業務に関する知識が備わっているか | 5・4・3・2・1 | |
| スケジュール管理 | 設定した納期を守り、予定通りに業務を行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| 正確性 | 与えられた仕事をミスなく正確に行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 情意評価 | 積極性、意欲 | 積極的にスキルアップや業務効率改善に取り組んでいたか | 5・4・3・2・1 |
| 規律性 | 就業規則やルールに則った行動ができていたか | 5・4・3・2・1 | |
| 協調性 | 上司・同僚・他部門とコミュニケーションを取り、協力して業務を推進したか | 5・4・3・2・1 | |
| 責任感 | 自分の役割に責任を持って最後まで計画通りに遂行したか | 5・4・3・2・1 |
営業職は、とくに売上などの数値目標を重要視する傾向にあるため、「業務目標達成度」と「目標達成過程」をはじめ、商談に関わる「計画力」や「企画力」「コミュニケーション能力」が重要な評価項目になります。
営業職は定量的な評価がしやすいため、売り上げ目標金額に対する売り上げ実績などに比重をおいて評価します。
| 評価 | 評価項目 | 評価内容 | 評価点 |
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか | 5・4・3・2・1 |
| 課題目標達成度 | 業務目標の達成に向けて設定した課題を達成できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に企画提案できたか | 5・4・3・2・1 |
| 実行力 | 独力で業務を行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| 知識 | 担当業務に関する知識が備わっているか | 5・4・3・2・1 | |
| スケジュール管理 | 設定した納期を守り、予定通りに業務を行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| 正確性 | 与えられた仕事をミスなく正確に行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| コミュニケーション | 顧客と綿密なコミュニケーションを取り、信頼を得ていたか | 5・4・3・2・1 | |
| 交渉力 | 的確に説明や交渉し、有利な条件を引き出せたか | 5・4・3・2・1 | |
| 情意評価 | 積極性、意欲 | 積極的にスキルアップや業務効率改善に取り組んでいたか | 5・4・3・2・1 |
| 規律性 | 就業規則やルールに則った行動ができていたか | 5・4・3・2・1 | |
| 協調性 | 上司・同僚・他部門とコミュニケーションを取り、協力して業務を推進したか | 5・4・3・2・1 | |
| 責任感 | 自分の役割に責任を持って最後まで計画通りに遂行したか | 5・4・3・2・1 |
技術職は、資格などを通して専門的な知識を身に付けたかのスキルを評価する技術力と、その業務をミスなく行えたかの正確性が重要な評価項目です。
顧客満足度に大きく関わるスケジュール管理も、重要なポイントといえます。
| 評価 | 評価項目 | 評価内容 | 評価点 |
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか | 5・4・3・2・1 |
| 課題目標達成度 | 業務目標の達成に向けて設定した課題を達成できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に企画提案できたか | 5・4・3・2・1 |
| 技術力 | 業務を行うための技術が備わっているか | 5・4・3・2・1 | |
| 知識 | 担当業務の専門分野に関して深い知識が備わっているか | 5・4・3・2・1 | |
| スケジュール管理 | 設定した納期を守り、予定通りに業務を行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| 正確性 | 与えられた仕事をミスなく正確に行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| コミュニケーション | 顧客と綿密なコミュニケーションを取り、信頼を得ていたか | 5・4・3・2・1 | |
| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 交渉力 | 的確に説明や交渉し、有利な条件を引き出せたか | 5・4・3・2・1 | |
| 情意評価 | 積極性、意欲 | 積極的にスキルアップや業務効率改善に取り組んでいたか | 5・4・3・2・1 |
| 規律性 | 就業規則やルールに則った行動ができていたか | 5・4・3・2・1 | |
| 協調性 | 上司・同僚・他部門とコミュニケーションを取り、協力して業務を推進したか | 5・4・3・2・1 | |
| 責任感 | 自分の役割に責任を持って最後まで計画通りに遂行したか | 5・4・3・2・1 |
管理職は、メンバーの育成やチーム・部署・部門の生産性向上などを担うため、リーダーシップと指導・育成を重視して評価します。
また、管理者は面談なども行うため部下との関係構築や他部門との連携が必要なため、コミュニケーション力も重要な評価項目となります。
| 評価 | 評価項目 | 評価内容 | 評価点 |
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか | 5・4・3・2・1 |
| 課題目標達成度 | 業務目標の達成に向けて設定した課題を達成できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に企画提案できたか | 5・4・3・2・1 |
| 計画立案 | 部門計画の立案と実行ができたか | 5・4・3・2・1 | |
| 改善力 | 業務効率化のため、業務改善に取り組めたか | 5・4・3・2・1 | |
| リーダーシップ | 管理者としてのリーダーシップを発揮して部門全体をまとめ、課題解決に取り組めたか | 5・4・3・2・1 | |
| 指導力 | 部下を成長させることができたか | 5・4・3・2・1 | |
| スケジュール管理 | 設定した納期を守り、予定通りに業務を行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| 正確性 | 与えられた仕事をミスなく正確に行えたか | 5・4・3・2・1 | |
| コミュニケーション | 顧客と綿密なコミュニケーションを取り、信頼を得ていたか | 5・4・3・2・1 | |
| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | 5・4・3・2・1 | |
| 交渉力 | 的確に説明や交渉し、有利な条件を引き出せたか | 5・4・3・2・1 | |
| 情意評価 | 積極性、意欲 | 積極的にスキルアップや業務効率改善に取り組んでいたか | 5・4・3・2・1 |
| 規律性 | 就業規則やルールに則った行動ができていたか | 5・4・3・2・1 | |
| 協調性 | 上司・同僚・他部門とコミュニケーションを取り、協力して業務を推進したか | 5・4・3・2・1 | |
| 責任感 | 自分の役割に責任を持って最後まで計画通りに遂行したか | 5・4・3・2・1 |

人事評価シートは社員の能力や成果を正確かつ公平に評価するための重要な書類ですが、書き方を間違えると従業員の不信感にも繋がりかねません。
人事評価シートの項目作成のポイントは下記の通りです。
一つみていきましょう。
人事評価シートの項目作成する場合、自社の企業目標や理念を把握した上で設定することが大切です。
それらを明確化した上で、達成すべき成果や必要な能力に落とし込み、従業員の現状スキルや能力の差を評価するようにしましょう。
記入の際は、評価できる点と合わせて、問題点や改善点も具体的に書くのがおすすめです。
定量化しやすい業務以外の達成条件を明確にするようにしましょう。
先述の通り、定量化しやすい達成条件とは、例えば営業職における「売り上げ目標金額に対する売り上げ実績」のような場合です。
それ以外の業務における達成条件を曖昧に設定してしまうと、公平性が失われ、従業員の不満の元になったり、退職に繋がる可能性もあります。
このように人事評価シートの評価基準は「成績」「能力」「情意」の3つに分類され、職種によって、業務内容や必要な能力が異なります。
評価項目は職種別に設定する必要があり、人事評価シートから得た評価データを、人事評価ツールでシステム化することにより、タレントマネジメントなどが実現でき、人材育成システムの戦略人事に展開することが可能です。
このようなタレントマネジメントの仕組み化には、人事評価ツールNewton(ニュートン)がおすすめです。
社員教育や給与水準に対しての課題や、スキル・マネジメント・スタンスなど個人の評価が見やすく、多くの情報をひと目で確認できます。
また独自のシステムにより、顧客満足度の向上・生産性の向上を兼ね備えた詳細な仕様が特徴です。
工数のかかる「人事評価」業務を「人事評価ツールNewton(ニュートン)」でシンプルに効率化してみてはいかがでしょうか。